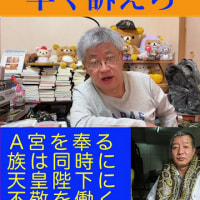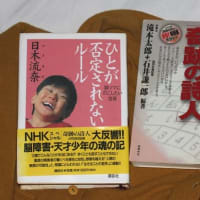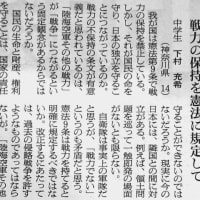以下、相変わらず大昔も大昔の話ばかりで申し訳がない。
先日、母に連れられて幼稚園に行った話しを書いたが、言い直しておく必要があった。私は幼稚園児ではなかった。幼稚園にも保育園にも通った形跡はない。あの日幼稚園に行ったのは、たまたまその日、入園説明会か見学会のような行事があったのだと思う。もちろん、そうした園の行事に私を連れ出したことは、私を幼稚園に入れることも、少しは考慮していたのだろうが当日のわたしの様子をみて、母も入園させることを断念せざるを得なかったのだろう。わたしなりに母の魂胆に察しがついて、これに激しく抵抗してみたのだろう。幼稚園の記憶は、その日だけのことで他には思いつかないし、誰に聞いても私が一時なり幼稚園に通っていたという話は出てこない。それより当時の父母の関係は非常にやっかいなものになっていて、のん気に長男である私を幼稚園に通わせるどころの話ではなかったようだ。
だから、母も参考までに幼稚園に私を連れて行って見学してきたという程度のことかもしれない。私も就学前のこの時期は、記憶が錯綜している。しばしば北関東の父の実家で暮らしていたこともあった。都営住宅と父の実家とが入り組んで思い出され、この頃の時間の後先がかなり錯綜しているのである。今となっては、詳しい事情を母から聞き出すことも難しくなっている。弟と会って飲んだ折など、よく、この頃のことが話題に出るのだが、それでも、なかなか頭の中で上手に整理ができないのである。なにしろ長男のわたしの記憶が定かではないのだから、どうしようもない。いずれにしても、わたしは都下にあった都営住宅から小学校に入学したのだが、そこにいたのは二学期の終わりまでで、年が明けてすぐ都営住宅を引き払い、二度と、そこに帰ってくることはなかった。私たちの一家は父の実家の世話になることになったのである。父の実家は典型的な農家で父は、その家の次男坊だった。
父の実家のある村の小学校に転入したのは一年生の三学期の途中からだった。母の手を引かれて戦前は父も通ったというその学校を訪れたのはもう一月半ばかあるいは二月に入ってからだったか。先生は黒板に私の名を大きく書きクラスのみんなに紹介してくれた。この時驚いたのは、辞めてきた学校の先生と今度の先生がそっくり似ていたのだ。女の先生である。もちろん名前は違っていた。私のためにわざわざ向こうの先生がこっちの学校に来てくれていたと自分勝手な妄想に走った。我ながらあまりにばかばかしくて、それは誰にも漏らさなかったが、しばらくの間、密かな愉悦となった。さて、先生は私を紹介するとそのまま教壇に立たせ、靴箱の使い方を説明するからと母だけを導いて教室から出ていってしまったのである。50名近い坊主頭と頬の赤い女の子たちに、一人向き合わされて、わたしはすっかり困ってしまった。先生と母がいなくなり、わずかな沈黙の時があって、突然誰かが私を指さし何事かはやし立て笑い出したのである。するとクラス全員が一斉に唱和してきた。歓迎とも排斥(はいせき)ともつかない実に奇妙な哄笑だった。
私はいわゆる「坊ちゃん刈り」のままだった。それが異様に見えたらしい。たしかに男の子は全員が坊主頭だった。最初私は、彼らが何をおかしがっているのか分からずに困りはて恥じ入るばかりだったが、泣き出した風には覚えていない。むしろ豪快で明るすぎるほどの笑い声に同調させられ照れ笑いぐらいは浮かべていただろう。彼らの笑いに悪い気はしなかったのである。さっそく次の日には母に頼んで頭を丸めて登校した。
以後、その学校を卒業し町の中学校に自転車で通うようになるまで、祖父やら叔父やらによくいじめられ、ひどい貧乏を強いられたまま矢面に立たされていた母の苦労は並大抵のものではなかったが、私にしてみれば山間の自然に恵まれ友達に恵まれ、おおむね幸せな子ども期を過ごせたと思っている。もし、あのまま東京都下の暮らしをしていたならば、おそらく私は尋常には育たなかったかも知れないと、最近はそんな感じがしているのである。父が病気になり実家に帰っていたのである。私の弟ふたりも父の実家の近くの縁者に預けられていたような状態だった。収入は閉ざされていた。母としては、このまま都下に住んでいても、にっちもさっちも行かない状態が続いていた。おびえたような戦々恐々たる日々が続いていたのである。父の家のものたちは、母を良くは思っていなかった。父が病気にいたった責任の半分ぐらいは妻にもあるだろうというのが彼らの言い分だった。八方塞りになっていた母の心理が、二人暮しをしていた私の性格にたぶんに影響していたように思われるのである。都営住宅での暮らしは、年を追うごとに私を内向的にさせていった。
父は療養と称して一足先に実家に舞い戻っていてわたしが小学校に入った時には都営住宅には影も形も見えなかった。父は母と結婚前から自分の縁者ばかりに左右されていたようなところがある。それがいつも母をないがしろにする結果となった。病気と言えば仕方はないが、気持ちの上で妻子を見捨てていたようなところがあった。この時期のわずか2年ほどの間に父の失職とか発病とかいろんなことがあった。母としては、次から次へと父によって引き起こされてくる心痛に絶えながら自活の道を探っていた。離婚することも考えていたらしい。必死に職を探していたようだが、子どもたちのことが気になってまともな仕事は見つからなかった。それでもときどきはパートタイマーのようなことをしていたようだ。家計はいよいよ逼迫(ひっぱく)していた。母と二人きりの食事もおかずが一つもなく、ご飯に醤油(しょうゆ)をまぶしながら食べたこともあった。とりわけ昼下がりのわびしい食事を覚えているのは、私が登校していなかった時期で、家で母と二人きりだったからか。醤油ご飯も子どもにはさほどの苦ではなかったし、どんなものでもまずい感じはしなかった。大人の気持ちは子どもとは違う。同じ事でも大人には耐えられないということもある。だが、親の心理はそっくり子どもにも伝わってしまうだろう。母と私は、完全に孤立していたのである。
当時4歳と2歳になる弟がいたはずだが、家の中にその姿が見えないのは、二人ともすでに父の実家に移されていたのだろう。ある日母が町に働きにでも出ていて留守にしていた昼下がり、弟たちと庭先で遊んでいると、母の姉がやってきて下の弟だけを連れていこうとするのである。もちろん母と叔母との示し合わせがあった上のことだったに違いない。弟があまりに激しく泣くので、隣の家の母親がパンを持ってきて弟に持たせた。パンをしゃぶっている弟を叔母が抱きあげ連れていった。別離にともなう寂しい実感はないのだが、衝撃は大きかった。泣きながら連れられていく2歳の弟よりもそれを見ているすでに物心つき始めている兄のほうがうける痛手は大きい。しばらくすると今度は母が上の弟をともなって父の田舎に行き、帰ってきたときには弟の姿が見えなかった。
話は戻るが都下の小学校に上がった当時のことで鮮明に記憶している場面がある。それがずっと気になっていた。前後に関連のない独立した一こまの残像だが、幼稚園の時のように学校に行きたくないという強烈な感覚がはり付いている。その感覚がどこから来ているのか。長い間、我ながらさっぱり説明できないままだった。自分の傾向を振り返ってみれば、学校嫌いはいくらでも証明できるのだが、その場面と前後の生活的事実が必ずしもつながってこない。どうしてあの場面だけに学校が嫌だという強い感じが貼り付いているのだろうか。
その日学校を休んだことは確かに覚えている。だが実際は、傘を捨てた日以前から私はほとんど登校しなくなっていたらしい。とすれば年を越えて3学期より田舎の学校に転入するまでの結構長い期間、私は学校を休み続けたということになる。四月に入学してからまともに登校したのは夏休みまでの三ヶ月だけならば、最初の学校のことが記憶にないのも当然だった。台風でも来ていたのか激しい風雨の朝だった。雨をついて私は学校に向かっている。林を抜けたところに小川があり橋が架かっている。そこをわたりながら下を見ると、いつもの優しい流れとはうって変わって、この日は橋もろとも足下がすくい取られるほどまでに増水していた。視点を固定して水面を見ていると吸い込まれそうだった。
私はしばらくはそこに佇み、いつもに違う暴力的な流れを驚嘆して見ていた。そして何を思ったのか、さしている傘を閉じ川の中に放りこんだ。コウモリ傘は濁流に飲み込まれ、見る見る流れ去った。買ったばかりの傘なのに、という母の難詰が待っている。だがこの朝ばかりは登校するよりは母の小言の方がよほど心地よいように思えた。傘がない以上、この雨の中をこれ以上進むことはできない。今になって弁明するわけではないのだが、登校しない理屈を作るために傘を捨てたというよりは、傘を捨ててから理屈が思いついたように覚えている。真新しい傘を川に投げ捨てる。その犯罪的快挙を成し遂げる自分の力を確認したかったのか。正直なところ、行為にいたる最初の動機はこれ以外に考えられない。
5年ほど前に母から聞いたところによると、先の都下の小学校では二学期の途中から、私はすでに登校しなくなっていたという。自分のことながら初耳だった。記憶の彼方にうっすらとそんな感触がないではなかった。そう言われてみれば、覚えているあの一こまに説明がついてきたのである。母親から引き離される不安に怯え、捨てられる夢にうなされた。私の場合は不安だけですんだのだが、この時期、弟たちは父の実家の祖母とか、叔母のもとで育てられていた。母が都会での生活を断念して田舎行きを決めざるを得なかった大きな理由がここにもあった。家計は最終的に破綻を迎えていた。こうして間もなく都営住宅を引き払い、田舎に身を寄せることに決めたらしい。夜逃げ同然だった。「父さんさえ、まともだったら」という嘆きは以後母が昔のことを話すさいの枕言葉になってしまった。
その日、もちろん家に引き返してきた。登校できない理由を傘のせいにすることだけは分かっていたが、母には傘をなくした状況の説明が必要だった。あれこれ考えながら家の玄関にたどり着いたときには、もうすっかりずぶぬれだった。傘が途中で風に飛ばされてしまったので、登校できないと、言い訳したのだと思う。子どものウソはすぐ見抜けたはずだ。だが、この時母から叱責された覚えはない。彼女は「ああ、そんなんじゃ風邪を引くよ」と言いながら、あわただしく体中をタオルで拭いてくれた。やっとのことで学校に向かわせた息子が間もなくずぶぬれで引き返してきたのでは、母もさぞかしがっかりしたことだろう。だが帰ってきてしまった子どもにそれ以上何を言っても無駄だった。
雨の中を再度子どもの手をつかんでまで強行には出なかった。それが登校しなくなる最初の日だったのか、それとも事前から休みがちだったのか。後者だったとすると、前日のうちに台風襲来(しゅうらい)を聞きつけて、新しい傘で私の機嫌をとり登校させようとしてみたのか。多分そんなところだろう。子どもは親の本意などだいたい察知してしまうものだ。学校に行きたくなかった私を無理矢理追い出した母の下心の形象が、玄関を出たとたんにコウモリ傘に乗り移った。だから私はその傘を川の中に投棄したのだ。しのつく雨に打たれながら仁王立ちしている。そんな傲慢な姿が浮かんでくるのだ。
<2007.01.30 記>