ベトナムのカンボジア国境に近いあフーコック島には世界最長のtロープウウェイがあり、ロープウェイに乗って訪れる島は花がいっぱいで水遊びができるテーマパークでした。一方、世界で最も高いところへ連れていってくれるロープウェイはスイスにあって、マッターホルンを展望する標高3883mのクライン・マッターホルンまで登るものです。ヨーロッパアルプスで最も高い山は、マッターホルンではなくモンブランですが、このモンブランの展望台であるエギューユ・デュ・ミディに上るロープウェイは、マッターホルンのロープウェイができるまでは世界一で標高3777mと富士山よりも1m高いところまで乗せていってくれます。今回は、このロープウェイのあるシャモニー・モンブラン近辺を紹介します。






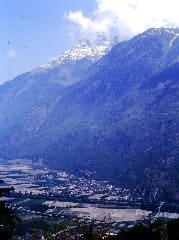

ロープウェイの麓駅のあるシャモニーはフランスの町ですがスイスのジュネーブの近くの東南にあり、フランスのサンジェルヴェ・レ・ヴァンやスイスのマルティニーから登山電車で行くことができます。シャモニーの一つ東寄りの駅が国境で、この駅が両線の接続駅になります。フランス側からは粘着区間としては最も急な90‰の勾配を上っていきます。一方のスイス側からは、ラックレールで上る電車が走っていますが、ともに電気を架線唐ではなく第三軌条から取っていたように思います。踏切もあるような路線に800Vもの電圧のある第三軌条があるわけで、なんでも危険といって排除する日本ではありえないシステムです。ラックレールで谷底にあるマルティニーまで降りていく車窓はなかなか雄大です。ただ、いつも思うのですが、谷の向こう側の山腹に民家が見えるのですが、日常の移動はどうしているんだろうと思ってしまいます。






さてモンブランですが、標高は4800mあまりでヨーロッパアルプス最高峰ですが、この標高は測量するごとに訂正され2021年9月の測量では4807.81mでしたが21世紀に入って毎年平均で13cmずつ低くなってるそうです。シャモニーからのロープウェイは、途中で一度乗り継ぎがありますが、2800mもの標高差を一気に上ってしまいます。特に乗り継ぎ後の区間は、標高2317mの途中駅から1470mの標高差を支柱無しで上りきるので圧巻です。この様子は、頂上の展望台から見ることができ、まるでゴンドラがエレベータのように垂直に上ってきます。



筆者は麓のシャモニーに宿泊したので、朝2番のロープウェイに乗ることができましたが、観光客の姿はまばらで、ほとんどはスキー板を担いだ乗客でした。大柄でスキーを持ってる乗客に周りを取り囲まれて、押しつぶされそうな感じがしました。スキーヤの連中は、頂上に着くやいなやスキー板を履いて滑り降りていきましたが、崖のすぐ縁のところを滑っていくので、雪庇のために転落しないか、見ているほうがハラハラします。モンブランへの登山客がいたのかどうか確認はできませんでしたが、頂上駅から標高差にして1000m程なので簡単に登れそうに思いますが、高山病や滑落の危険があり、出来心で上れる山ではなさそうです。
モンブランの頂上はフランスとイタリアとの間にあって、長く国境線の争いがあったようですが、現在はモンブラン山頂は両国の双方の領土ということになっているそうです。国境の山ということなので、フランス側だけでなくエギューユ・デュ・ミディからロープウェイを後次いでイタリアに行くこともできます。現在ではフランスもイタリアもEUで国境でパスポート・コントロールはありませんが、EUが生まれる前には富士山の頂上のようなところでイミュグレーションがあったんでしょうか。
日本では第三軌条の電車は一部の例外を除いて地下鉄、それも古くに開通した路線で採用されtます。人間が触れる可能性の低い路線で安全が確保できるとの理由ですが、そもそもは架線を張らなくて済むのでトンネルの高さを低くできるメリットから採用されました。シャモニーなどで採用されたのは、架線が無い分景観への影響が少ないとの理由のようです。かつてのユーロスターは、イギリスの走行区間が第三軌条のためユーロトンネルを出るとスピードがガクンと落ちていましたが、現在は路線が変わって架線方式になりました。ヨーロッパでは、国を跨がる多くの特急がありますが、国によって終電方式だけでなく、異なる信号方式をものともせず猛スピードで走り回っています。この切り替えってコンピュータ制御なのでしょうか、人間が判断しているのでしょうか。






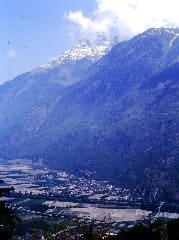

ロープウェイの麓駅のあるシャモニーはフランスの町ですがスイスのジュネーブの近くの東南にあり、フランスのサンジェルヴェ・レ・ヴァンやスイスのマルティニーから登山電車で行くことができます。シャモニーの一つ東寄りの駅が国境で、この駅が両線の接続駅になります。フランス側からは粘着区間としては最も急な90‰の勾配を上っていきます。一方のスイス側からは、ラックレールで上る電車が走っていますが、ともに電気を架線唐ではなく第三軌条から取っていたように思います。踏切もあるような路線に800Vもの電圧のある第三軌条があるわけで、なんでも危険といって排除する日本ではありえないシステムです。ラックレールで谷底にあるマルティニーまで降りていく車窓はなかなか雄大です。ただ、いつも思うのですが、谷の向こう側の山腹に民家が見えるのですが、日常の移動はどうしているんだろうと思ってしまいます。






さてモンブランですが、標高は4800mあまりでヨーロッパアルプス最高峰ですが、この標高は測量するごとに訂正され2021年9月の測量では4807.81mでしたが21世紀に入って毎年平均で13cmずつ低くなってるそうです。シャモニーからのロープウェイは、途中で一度乗り継ぎがありますが、2800mもの標高差を一気に上ってしまいます。特に乗り継ぎ後の区間は、標高2317mの途中駅から1470mの標高差を支柱無しで上りきるので圧巻です。この様子は、頂上の展望台から見ることができ、まるでゴンドラがエレベータのように垂直に上ってきます。



筆者は麓のシャモニーに宿泊したので、朝2番のロープウェイに乗ることができましたが、観光客の姿はまばらで、ほとんどはスキー板を担いだ乗客でした。大柄でスキーを持ってる乗客に周りを取り囲まれて、押しつぶされそうな感じがしました。スキーヤの連中は、頂上に着くやいなやスキー板を履いて滑り降りていきましたが、崖のすぐ縁のところを滑っていくので、雪庇のために転落しないか、見ているほうがハラハラします。モンブランへの登山客がいたのかどうか確認はできませんでしたが、頂上駅から標高差にして1000m程なので簡単に登れそうに思いますが、高山病や滑落の危険があり、出来心で上れる山ではなさそうです。
モンブランの頂上はフランスとイタリアとの間にあって、長く国境線の争いがあったようですが、現在はモンブラン山頂は両国の双方の領土ということになっているそうです。国境の山ということなので、フランス側だけでなくエギューユ・デュ・ミディからロープウェイを後次いでイタリアに行くこともできます。現在ではフランスもイタリアもEUで国境でパスポート・コントロールはありませんが、EUが生まれる前には富士山の頂上のようなところでイミュグレーションがあったんでしょうか。
日本では第三軌条の電車は一部の例外を除いて地下鉄、それも古くに開通した路線で採用されtます。人間が触れる可能性の低い路線で安全が確保できるとの理由ですが、そもそもは架線を張らなくて済むのでトンネルの高さを低くできるメリットから採用されました。シャモニーなどで採用されたのは、架線が無い分景観への影響が少ないとの理由のようです。かつてのユーロスターは、イギリスの走行区間が第三軌条のためユーロトンネルを出るとスピードがガクンと落ちていましたが、現在は路線が変わって架線方式になりました。ヨーロッパでは、国を跨がる多くの特急がありますが、国によって終電方式だけでなく、異なる信号方式をものともせず猛スピードで走り回っています。この切り替えってコンピュータ制御なのでしょうか、人間が判断しているのでしょうか。



















