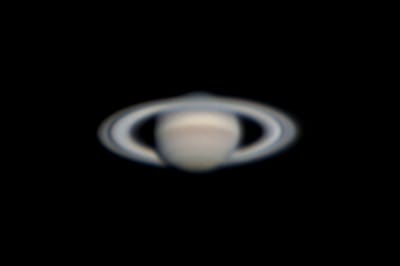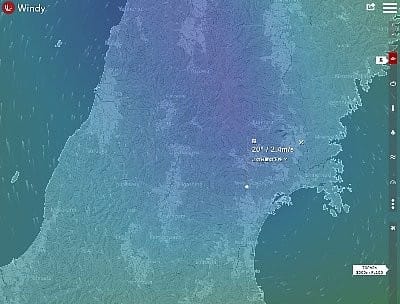東北地方の梅雨が明けた7月16日に撮影した土星です。
しか~も、記念すべき今シーズン初撮影で~す。撮影システムは、µ-210+powermate2×+ADC+Imaging Flip Mirror + UV/IRcut + ZWO ASI290MC です。

2021/7/16 23h47m36s(JST) 180sec Shutter=52.68ms Gain=350 (58%)
Diameter=18.43" Magnitude=0.26 CMI=26.0° CMIII=123.0°

2021/7/16 23h51m37s(JST) 120sec Shutter=54.55ms Gain=350 (58%)
Diameter=18.43" Magnitude=0.26 CMI=28.1° CMIII=125.0°

2021/7/16 23h57m49s(JST) 180sec Shutter=46.45ms Gain=362 (60%)
Diameter=18.43" Magnitude=0.26 CMI=32.0° CMIII=128.7°
さて、時刻は0時を過ぎました。土星の南中は0時58分ですが土星の撮影はここまでとして、
このあとはこちらも今シーズン初となる木星の撮影を行いました。
その様子は次回のブログで~。

しか~も、記念すべき今シーズン初撮影で~す。撮影システムは、µ-210+powermate2×+ADC+Imaging Flip Mirror + UV/IRcut + ZWO ASI290MC です。

2021/7/16 23h47m36s(JST) 180sec Shutter=52.68ms Gain=350 (58%)
Diameter=18.43" Magnitude=0.26 CMI=26.0° CMIII=123.0°

2021/7/16 23h51m37s(JST) 120sec Shutter=54.55ms Gain=350 (58%)
Diameter=18.43" Magnitude=0.26 CMI=28.1° CMIII=125.0°

2021/7/16 23h57m49s(JST) 180sec Shutter=46.45ms Gain=362 (60%)
Diameter=18.43" Magnitude=0.26 CMI=32.0° CMIII=128.7°
さて、時刻は0時を過ぎました。土星の南中は0時58分ですが土星の撮影はここまでとして、
このあとはこちらも今シーズン初となる木星の撮影を行いました。
その様子は次回のブログで~。