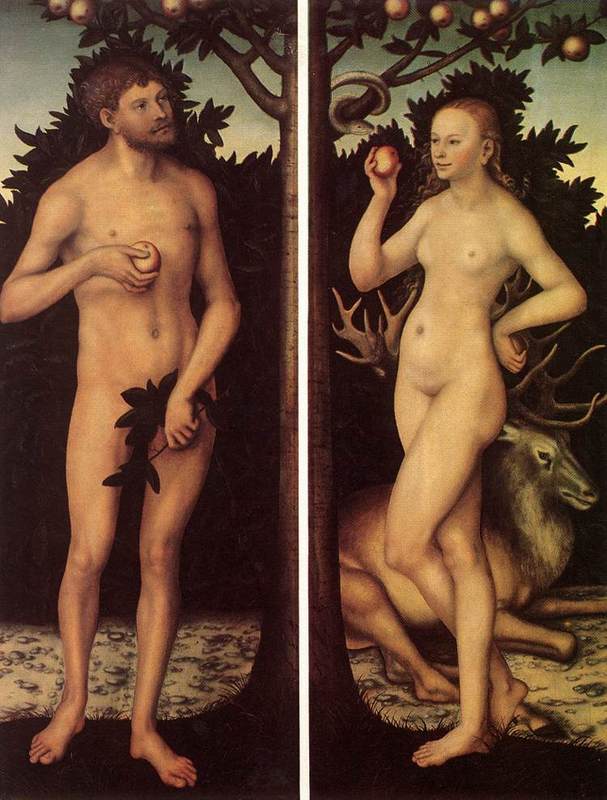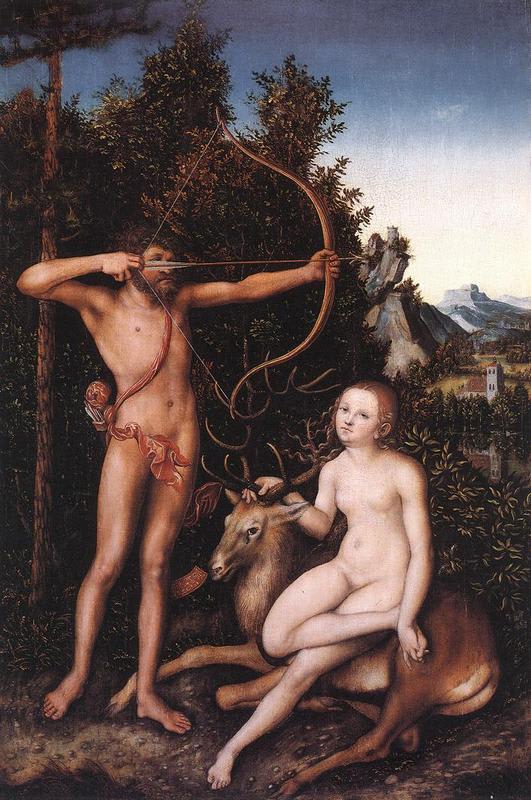 目に見えない脳の中だけで起こっているらしいことは、なんとなく他人とも分かり合えるような気がすることもあるけれども、本当は分かり合えないような気もする。そういう頼りないところがあります。人間どうしの相互理解の、その根本的な頼りなさを無視してしまえば、いくらでも難しい哲学が作れるし、立派な心理学も作れます。
目に見えない脳の中だけで起こっているらしいことは、なんとなく他人とも分かり合えるような気がすることもあるけれども、本当は分かり合えないような気もする。そういう頼りないところがあります。人間どうしの相互理解の、その根本的な頼りなさを無視してしまえば、いくらでも難しい哲学が作れるし、立派な心理学も作れます。
しかし物質ではないものの存在感は、物質の存在感とは、確かさのレベルが違う。人間の内部には、たとえば「悲しさ」というものが存在する、と言ってみたい。だれもが賛成してくれるでしょう。むしろ、それを認めない人は変人です。認めないでがんばると、毎日がとても不便なことになる。でもその話の確かさについては、改めて考えると、だれも実は自信がないはずです。「悲しさ」というものがこの世に存在することの確かさのレベルは、物質である涙やタマネギが存在することに比べると圧倒的に頼りない。「悲しさ」はカメラに写らない。涙やタマネギはカメラに写ります。
その違いはだれも認めるでしょう。それを強調すれば、物質ではないものの存在感は、物質の存在感とは区別できる。心の中にあるもの、人間の内面、主観、そういうものは物質として目に見えない。手で触れない。本人だけが直接感じられる。
その本人でさえも、自分の身体のどこで「悲しさ」を感じているのか分からない。自分の「悲しさ」は、目には見えない。耳にも聞こえない。手で触れない。匂いも味もしない。涙が口に入ってきてしょっぱかったりはします。結局、自分の「悲しさ」でも、直接の五感では感じられない。脳のどこにあるか、はっきりとは分からない感情回路が感じているらしい、と思われるだけです。
客観と主観。一方はだれでもが感じられる。他方は、その人自身しか感じられない。両方とも存在感はある。私たちは、どちらの存在感を感じても、無意識に身体が反応します。たとえば、もっと知りたくなる。怖くなる。逃げたくなる。あるいは好きになったり嫌いになったりする。同時にその感情と一緒にそのことを記憶する。それで、それがあると感じる。ここは同じです。しかし、だれとも共有できる物質的存在感と、人間の内面にあるものを感じる存在感とは、明らかに違う。その違いを人間は、客観とか主観とか、外界とか内面とか、現実とか心の中とか、言うようになったのです。
拝読サイト:映画『CUBE』
拝読サイト:カント『純粋理性批判』批判のための10冊