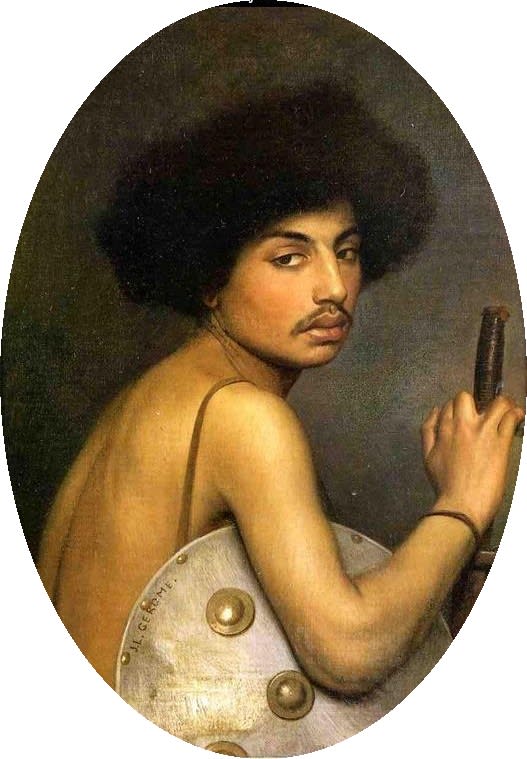つまり、ケニヤの草原でライオンがシマウマを襲う場合も、台風が九州地方を襲う場合も、経済不況が中小企業を襲う場合も、「襲う」という言葉を使う人は、それがそれを襲う目的を知っている。XがYをする、という形で物事の認知をするとき、私たちはXがYをする目的をすでに知っている。
逆に言えば、台風が九州を襲う場合、気象現象である台風は自分が九州を襲う目的を知らない。この光景を観察している人間が台風の行為の目的を知っている、ということでしょう。
観察者が台風の行為の目的を知っているかのごとく、その行為を「台風が九州を襲う」と表現している。この場合、「襲う」という表現は比喩として使われている。台風のなす行為の目的は台風の内部にはなくて、その行為を遠くから観察している人間の内部にある。台風のその行為を、言葉で述べようとする人間の内部にある。台風の観察者は「台風が九州地方に襲いかかり、大災害をもたらした」と実況ニュースで述べる。あるいはブログに書く。つまり、拙稿の見解を使えば、「襲う」という行為は台風の内部にはなくて、それを観察し叙述する人間の内部にある。
XがYをするとき、そのことを「XがYをする」と言うのは、その話し手が、XがYをする、と思っているからです。
拝読ブログ:相対性理論をわかりやすく説明してみる(2)
拝読ブログ:マイナークラブハウスの森林生活」木地雅映子