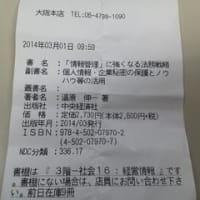最近、消滅時効によって結論が左右する事案が多く報道されているような気がします。
例えば、つい最近では、ドミニカ共和国への移民訴訟につき、東京地裁は国の責任を認めたものの消滅時効が完成したとして、原告側の請求を棄却しています(当ブログ6月7日)。
また、我々法曹界で話題になった事例として、訴訟提起が消滅時効完成の1日後であったがために請求が棄却された医療過誤訴訟があります(当ブログ5月29日)。
そして今回、新生児の取り違えによって、実際には血のつながりのない親の子として育てられた子供等が、生き別れになったのは、病院を経営していた東京都に責任があるとして損害賠償請求を行っていたところ、東京高裁で救済的要素の強い判決が出ました。
民法では、不法行為は不法行為時から20年の除斥期間の壁があり(ちなみに不法行為を知ったときから3年という消滅時効もあります)、また、債務不履行では、債務不履行の時から10年という消滅時効の壁があります。
この点、本件の原告は、訴訟提起時には既に46歳であったとのことであり、単純に民法の規定を当てはめてしまうと、不法行為で請求するにせよ、債務不履行で請求するにせよ消滅時効が成立してしまいそうです。
ところが、東京高裁は、不法行為については消滅時効が成立しているが、債務不履行については、債務不履行の時点を「取り違えの事実を知ることが出来る時点」と解釈することが出来ると判断した上で、客観的に取り違えの事実が生じたときではなく、後日、検査等によって取り違えの疑いが出てきた時点からスタートするとして、債務不履行に基づく損害賠償請求については消滅時効が成立していないとしました。
形式を重視する法律論だけで見た場合には、かなり場当たり的な解釈ではないかという気もします。
が、原告が取り違いを知ることが出来たのが、20年以上も経過してからという事実が存在したことからすると、単純に消滅時効だからといって請求を棄却するのは心情的にはかなり抵抗が大きいのも分かります。
ちなみに、消滅時効制度の趣旨は、「権利の上に眠る者は保護に値しない」という風に言われています。
権利の有無は、請求者本人の主体ではなく、客観的に発生しているか否かによって判断されますので、「本人が事情を知らないところで、消滅時効だなんておかしい!」といっても、法形式上は通用しないことになっています。
ただ、こう度々消滅時効によって結論が左右される事例を目の当たりにすると、法律学を学んだ者は、上記消滅時効制度の趣旨が本当に適切なのか再考する必要があるのかも知れません。
関連するニュースへのリンク
http://www.asahi.com/national/update/1012/TKY200610120306.html
例えば、つい最近では、ドミニカ共和国への移民訴訟につき、東京地裁は国の責任を認めたものの消滅時効が完成したとして、原告側の請求を棄却しています(当ブログ6月7日)。
また、我々法曹界で話題になった事例として、訴訟提起が消滅時効完成の1日後であったがために請求が棄却された医療過誤訴訟があります(当ブログ5月29日)。
そして今回、新生児の取り違えによって、実際には血のつながりのない親の子として育てられた子供等が、生き別れになったのは、病院を経営していた東京都に責任があるとして損害賠償請求を行っていたところ、東京高裁で救済的要素の強い判決が出ました。
民法では、不法行為は不法行為時から20年の除斥期間の壁があり(ちなみに不法行為を知ったときから3年という消滅時効もあります)、また、債務不履行では、債務不履行の時から10年という消滅時効の壁があります。
この点、本件の原告は、訴訟提起時には既に46歳であったとのことであり、単純に民法の規定を当てはめてしまうと、不法行為で請求するにせよ、債務不履行で請求するにせよ消滅時効が成立してしまいそうです。
ところが、東京高裁は、不法行為については消滅時効が成立しているが、債務不履行については、債務不履行の時点を「取り違えの事実を知ることが出来る時点」と解釈することが出来ると判断した上で、客観的に取り違えの事実が生じたときではなく、後日、検査等によって取り違えの疑いが出てきた時点からスタートするとして、債務不履行に基づく損害賠償請求については消滅時効が成立していないとしました。
形式を重視する法律論だけで見た場合には、かなり場当たり的な解釈ではないかという気もします。
が、原告が取り違いを知ることが出来たのが、20年以上も経過してからという事実が存在したことからすると、単純に消滅時効だからといって請求を棄却するのは心情的にはかなり抵抗が大きいのも分かります。
ちなみに、消滅時効制度の趣旨は、「権利の上に眠る者は保護に値しない」という風に言われています。
権利の有無は、請求者本人の主体ではなく、客観的に発生しているか否かによって判断されますので、「本人が事情を知らないところで、消滅時効だなんておかしい!」といっても、法形式上は通用しないことになっています。
ただ、こう度々消滅時効によって結論が左右される事例を目の当たりにすると、法律学を学んだ者は、上記消滅時効制度の趣旨が本当に適切なのか再考する必要があるのかも知れません。
関連するニュースへのリンク
http://www.asahi.com/national/update/1012/TKY200610120306.html