
話を1933年12月23日の現場に戻そう。私は秋笹とともに京王線幡ヶ谷駅近くの査問会場(二階建て民家)で、宮本たちの来るのを待っていた。
やがて・・小畑と宮本が何か話しながら階段を上ってきた。私は彼らが部屋に入り、襖をしめたとたんに小畑にいった。「今日は君をスパイ容疑で査問する。大声を出したり暴れたりしないように」。小畑は一瞬顔面蒼白となり、その場に尻から崩れるように座った・・・約二十分後、今度は大泉が逸見とともにやってきた・・・私が大泉を査問しているうちに小畑が少しずつ体を移動し始めた。
しばらくすると部屋の入り口側のところまでいざって行き、体を壁にもたせかけているのがわかった。私は、その様子を承知していたが、小畑にしても、前日からの査問でもあるし、大目に見てやろうとそのまま見逃していた。それからどれぐらいたっただろうか。小畑はいつのまにか、外に面している窓のところに移っており、いまにも飛び出そうとしているではないか・・・私は小畑の膝の裏あたりをかかえるようにして押さえた。
逸見は頭の部分を押さえた。宮本は右膝を小畑の背中にのせ、彼自身のかなり重い全体重をかけた。さらに宮本は、両手で小畑の右腕を力いっぱいねじ上げた。それは尋常な力ではなかった・・・苦しむ小畑は、終始、大声を上げていたが、宮本は手をゆるめなかった。しかも、小畑の腕をねじ上げればあげるほど、宮本の全体重をのせた右ひざが、小畑の背中をますます圧迫した。やがて、ウォーという小畑の断末魔の叫び声が上がった。
小畑は宮本のしめ上げに息が詰まり、ついに耐え得なくなったのだ。小畑はぐったりしてしまった。このとき、階下から物音を聞きつけて、秋笹正之輔が駆け上がってきた。「何をやったんだ」彼はそういうなり、大急ぎで小畑の脈をとった。たしかに小畑の脈は止まっていた。秋笹が宮本のほうを向いていった。「しょうがないなぁ。殺してしまって・・・」私はとっさに、「いや、殺すつもりでやったんじゃないんだ」と答えた。
そのときの宮本が、殺意をもっていたかどうかは分からない。しかし、宮本のあの小畑への攻撃は、誰が見ても普通ではなかった。宮本が抑制をきかせ得なくなっていたのは、そのものすごい形相や動作を見てもわかった。あんなことをしなくても、彼を取り押さえることは可能だったはずだ。ましては宮本は柔道三段である。どのように力を加えれば相手がどうなるかは、当然わかっていたはずである。宮本は明らかに、自分の若さにまかせてしまったのだ(宮本:25歳)。
小畑が絶命したあと、われわれは予想もしなかった結果を前にして、誰一人、口を開こうとする者はいなかった。困ったことになった事態の重さに、じっと耐えていた。ところが宮本だけはその瞬間から、自らの責任の回避に走ったのである。
しばらくして、宮本が拡大中央委員会を開こうというので、われわれは小畑の死体を押入れに入れ、その場に木島を残して、階下に降りた。そのときも宮本は小畑の死体に手を触れようともしなかった。階下に下りると、彼は逸見と相談し、私と秋笹にいった。
「君たちを中央委員にすることにした。これからは四人が、党のすべてのことに責任を持つ」
私と秋笹は、心の引き締まる思いで宮本の言葉を聞いた。査問中、思わぬ事態に見舞われ、党の前途はますます困難を極めるに違いないのである。それを乗り切るためには、われわれは死力を尽くして協力し合わねばなるまい・・・。
ところが不思議なことに、この会議で宮本の口からは、肝心の小畑の死体の処理については一言も発せられなかったのである。いや、小畑の死体の処理についてばかりではない。このときから宮本は「スパイ査問問題」の真実について、一言も話さない歴史が始まるのである。
宮本は自分に責任があるにもかかわらず、小畑の死体には触れようとも近づこうともせず、その処理について口を出そうともしなかった。ために秋笹と木島がその夜、苦労して床下に埋めたのだが、のちに裁判になって、この点を問われると、宮本は「あれは、自分が命令してやらせたものではない。
自分は、小畑の死後は、翌25日の夜、現場に立ち寄って、そのことを聞いただけだから、死体遺棄については一切関知しない」という意味のことを堂々と主張しているのである。あのとき、私と秋笹を中央委員に任命し、「これからは、この四人がすべての責任を持つ」といった意味もおのずと分かるではないか。
彼は査問のあと、街頭連絡があるといって外出しようとしたので、私は「いったい誰と会うのだ」と尋ねた。だが宮本は私の忠告も容れず、「これが最後だ」と言って出かけ、スパイに売られて逮捕されてしまった。文字通り最後の連絡となったわけだが、それにしても宮本はどういう意味で「これが最後」などと私に言ったのか。考えれば考えるほど意味深長ではないか。
一昨年(1976年)、例の「立花論文(日本共産党の研究)」が出たあと、宮本があまりにも。査問事件のときの小畑の姿勢にこだわり、なにがなんでも私を屈服させようとするので、査問の直後に彼が逮捕されたことにふれて一言いってやったことがある。
「ぼくはいつも君を守ってきてやった。そのことが君にはわからないのか。たとえばスパイのこともそうだ。あのとき君は、行ったらやられてしまうと、ぼくがしきりに忠告したにもかかわらず、出かけていき逮捕された。だが、このことだって、ぼくは誰にも話したことはないぞ」。すると宮本は「なに、あのとき捕まらなくても、すぐに捕まったよ」と事もなげに答えたのいは大いに驚いた。
・・・私は遺書のつもりでこの本を書いた。
以上、新潮社「昨日の同志 宮本顕治へ」袴田里見著より。袴田里見は1977年に党から除名され、1990年に死去した。享年86。宮本顕治よりは4歳年上だった。33年、宮本が逮捕された直後に逮捕され、非転向のまま戦後をむかえ、以後、宮本につぐナンバー2の党幹部として働いてきた。戦後ともなれば、査問事件の真相を知っているものは、宮本のほかには袴田一人であった。宮本としては、袴田がなにを言い出すかが、ずっと気がかりだった。袴田さえ、黙っていてくれればわが身は安泰だと、戦々恐々たる思いで、戦後の後半生を過ごしてきたに違いない。続けて、立花隆著の「日本共産党の研究」から、現場の様子を見てみよう。
しばらく一同呆然としていたが、事後処理をしなければならない。とりあえず小畑の死体を押入れに押し込んだあと、木島だけを二階に残して、宮本、逸見、秋笹、袴田の四人は階下に下りて会議を持った。善後策が協議され、大泉の査問はここで打ち切り、当分の間これを監禁しておく、大泉、小畑は除名処分、それに代えて秋笹、袴田の両名を中央委員に昇格させ、木島を中央委員候補とすることにして、各自の仕事の分担を決めた。
小畑の死体の処置については、はっきりと決めなかったが、床下に埋める以外に手がなしとの暗黙の了解があり、会議の後で袴田が八畳間の畳を持ち上げると、秋笹が昼間からそんなことをするなと制した。また大泉、小畑の所持していた計600円については、逸見と秋笹が200円、宮本と袴田が100円ずつ取り、大泉の腕時計は袴田が取った。 会議を終えたところで木島が呼ばれ、大泉の監視役をすること、これから党の清掃をする必要があるから下部党員の経歴書を至急取ることなどが宮本から命ぜられた。
それから宮本、袴田、逸見、木島の四人は街頭連絡があるので、順次アジトを出た。木島は出がけに、秋笹から金を渡されシャベルと釘抜きを買ってこいと命じられた。 夕方七時ごろ、木島はシャベルを買って帰り、しばらく秋笹と雑談していた。木島の記憶では、宮本が明日の明け方に皆で小畑を埋めようといっているというのだが(宮本は否定)、何時になっても、誰もアジトに戻ってこなかった。
秋笹と木島は憤慨しながら仕方なく二人で埋めようと決心し明け方まで三時間交代で寝た。 午前四時半ごろ、二人で八畳間の畳二枚をあげ、床板を上げにかかった。釘を抜くとき異様に大きな音がするので、一本抜いては一休みしながら畳一枚分の床板を上げた。 木島が床下に入り穴を掘り始めると、秋笹がしきりに「二階の見張りが木俣(女性:秋笹のハウスキーパー)一人で大丈夫だろうか」と繰り返すので、木島は、秋笹は気味が悪くて逃げ出したいのだなと思い、「いいですよ一人でやりますから二階に行っていてください」といって、一人でニ、三十分かけて穴を掘りあげた。
すでに夜明けになっていた。 小畑の死体は掛け布団の上にのせ、兵児帯でしばりつけてから引きずって運んだ。木島が頭のほうを持って先に立ち、秋笹が足の方を持ちながら苦労して階段を降ろしてから、兵児帯をほどいて小畑の足首に結いなおし、今度は木島が足を持ち、秋笹が肩のあたりを持って穴の中へ死体を落とした。
小畑の死体は両脚を折り曲げて天井を向く格好になった。その上に木島は自分の古オーバーをかけた。小畑のものの方が良いオーバーを着ていたので、これを木島が貰うことにしたのである。
木島がスコップで、秋笹が床板で死体の上に土をかけた。 この夜、木島は、小畑のネクタイ、ハンカチ、細引き、針金などと「赤旗」の刷り損ないを風呂場で燃やしはじめたが、くすぶってなかなか燃えないので、庭に穴を掘り、揮発油をかけて燃やしたが、なおもくすぶるので、土をかけて埋めてしまった。 これは事件発覚後すべて掘り出され、証拠品として法廷に提出されることになる。また出刃包丁、斧などは風呂敷にまとめ、後に木島が下部党員に処分を依頼した。
要するに後始末は全部木島がやったのである。翌日これをアジトにやってきた宮本に報告すると「ご苦労さん」と言った。そして木島が「穴掘りは一人で三十分ぐらいでやってしまった」というと、宮本は「さすが労働者だ」とほめた。 しかし宮本は、後に裁判で死体遺棄の共謀共同正犯に問われると、自分は小畑の死体処分にはまったく関係がなく、あれは秋笹、木島が勝手にやったことだとの主張をつづけ今日に至っている。
当事件についての顕治の言い訳が、妻である百合子が死んだ直後に書かれた「百合子断想」(1951年)と題された文章のなかに次のようにある。彼の主張は終始、他人事である。結局、事件については、それ以上のことは死ぬまで具体的にはいっさい話さなかった。
中央委員会に入ったスパイが査問中、はからずも急死したことを特高警察は、私刑による殺人事件として大々的に号外入りで新聞に宣伝していた・・・。長い公判による再鑑定の結果、殺人事件ではなく、ショック死であったことが確認されてこのデマは打ち破られた。
さて、引用ばかりが長くなったが読んでみて、まず驚くのは現場における宮本顕治という男の尊大にして傲慢な言動である。事件は宮本の指揮のもと始まり、そして終わった。若干25歳の若造である。入党してから二年しかたっていなかった。事件の直前に、委員長の野呂栄太郎が逮捕され、宮本にリーダー役がまわってきた。当日アジトに集結した者以外に党幹部は残っていなかった。査問される側としての小畑、大泉。彼らを査問する側の宮本、逸見の計4名が中央委員のすべてだった。
ようするに、二人づつが二派に分かれて党の指導権を争っていた「やるかやられるか」の生死をかけた内ゲバ闘争である。それも数日後、自力でアジトから脱出した大泉は、その後の資料や証言などで特高に飼われていたスパイであることは明白になったが、殺された小畑はスパイでもなんでもなかったのである。
人にとって、革命思想やイズムなど、いざとなったら、何の役にも立ちはしない。イデオロギーなど、とってつけたようなものである。若さという自覚もまた偏向思想のひとつなのである。それは青年にヒロイズムによる慢心を呼び起こす。いわゆる「怖いもの知らず」というやつだ。「敗北の文学」という論文が懸賞されたのは、この事件から3年前のことである。
事件の前年にはソ連邦帰りとしてすっかり有名になっていた9歳年上の女流作家中条百合子と結婚している。これら短期日の間にもたらされた望外の恩寵が宮本顕治という白面の革命児の内面に、はなはだしいうぬぼれを湧出させ、のぼせ上がらせていた、ということはなかっただろうか。
さても、下は「信義について」と題されて1946年、すなわち敗戦の翌年に「東大新聞」に発表された宮本百合子の文章である。3千字ほどの短いものなのだが、みなさんにも、ぜひ一読してほしいと思い、青空文庫より全文コピーさせていただいた。この文章に対する私の文芸上の評価は、いたって否定的なものであり、その意味では悪い見本として、ここにコピーするわけでいささか心苦しい。
去る四月一日の『大学新聞』に逸見重雄氏が「野呂栄太郎の追憶」という長い文章を発表した。マルクス主義を深く理解している者としての筆致で、野呂栄太郎の伝記が細かに書かれ、最後は野呂栄太郎がスパイに売られて逮捕され、品川署の留置場で病死したことが語られている。
「昭和八年十一月二十八日敵の摘発の毒牙にかかって遂に検挙され」当時既に肺結核を患っていた野呂は「警察における処遇に抗しかねて僅か二ヶ月に足らずして品川署で最後の呼吸をひきとった。数え年三十五歳であった。」
当時私の友達が偶然野呂さんのいた警察の留置場に入れられていた。そのひとは看護婦の心得があったので、自分で体の動かせなくなった野呂さんのために世話をしてあげた。
「どこへか運ばれてゆくとき留置場から自動車まで抱いて行ったんです。女のわたしが、軽々と抱き上げるほど小さくなってしまっていらしたのよ。抱き上げた途端はっとして、涙が出て、かくすのに本当に困ったの」そのひとは、そう話した。「自分も病気だったけれど、わたしは、本当に本当に何とも云えない気がした。私は死なないこと丈はたしかだったんですもの」これを話した人は、おそらく一生この光景を忘れることはないだろう。
逸見氏の文章を、私は様々のことを思いながら、読んだ。未完であったその「追憶」はつづけて四月十一日の『大学新聞』にのった。筆者はたっぷり、いい気持に、一種調子の高いジェスチュアをも加えて文章を進めているのであった。「マルクス主義は論壇で原稿稼ぎに使われるような、そんな生やさしいものではないのである。その理論の命ずるところは必ずプロレタリアートの実践と結びつく。」「この理論と実践との結びつきを、身を以て野呂が、あの健康をもって示したことは、今後のマルクス主義者に多くの範を示すものである」と。
それを読み、二度三度くりかえして読み、私の心には烈しく動くものがあった。この一節を書くとき、筆者逸見氏は、自分のうちにどんな気持がしていたのであろうか、と。
逸見重雄氏は、野呂を売って警視庁に捕えさせたスパイの調査に努力した当時の党中央委員の一人であった。特高が中央委員であった大泉兼蔵その他どっさりのスパイを、組織の全機構に亙って入りこませ、様々の破廉恥的な摘発を行わせ、共産党を民衆の前に悪いものとして映そうとして来たことは、三・一五以来の事実であった。そして、これは、今日の事実であり、明日の事実であるであろう。現に新聞は共産党への弾圧を挑発するためマ元帥暗殺計画を企てた新井輝成という男の記事を発表している。
当時の中央委員たちによって、スパイとして調べられていた小畑達夫が特異体質のため突然死去したことは、警視庁に全く好都合のデマゴギーの種となった。共産党員は、永い抑圧の歴史の中で沢山の誹謗に耐えて来たのであったが、この事件に関係のあった当時の中央委員たちは、人間として最も耐えがたい、最も心情を傷められる誹謗を蒙った。人殺しとして扱われ、惨虐者として描き出され、法律は、法の無力を証明して支配者の都合に応じて顎で使われ、虚偽の根拠の上に重刑を課した。
私は、一人の妻として計らずもこの事件の公判の傍聴者であり目撃者であった。一九四〇年(昭和十五年)春ごろから非転向の人たちだけの統一公判がはじまった。事件のあった時から足かけ八年目である。
転向を表明した人々の公判が分離して行われ、大泉兼蔵の公判も行われた。当時傍聴席は、司法関係者と特高だけで占められていた。家族として傍聴する者さえ殆どなかった。たまに誰か来ると、特高は威脅的にその人にいろいろ訊いたし、私のように関係の知れ切っている者に対してさえ、今日こそ無事には帰さないぞという風の無言の脅迫をくりかえした。
私は、その事件については、全然何も知らず、すべてを新しい駭(おどろ)きと、人間としての憤りとをもって傍聴したのであった。そして、この駭き、この憤りを感じてここにかけている一人の小さい女は、妻ではあるが同時に作家である。その意味では、民衆の歴史の証人である責任をも感じつつ、春から夏へと、傍聴をつづけた。
分離の公判で、はじめて逸見重雄氏を見た。そのときは、上下とも白い洋服で瀟洒たる紳士であった。仏語に堪能で、海軍の仏印侵略のために、有用な協力をしているというような地位もそのとき知ったように思う。
「野呂栄太郎の追憶」の終りにかかれている堂々の発言を見て、私の心が激しくつき動かされたのは、今から七年前の暑い夏、埃くさい公判廷で幾日も見た光景が、まざまざと、甦って来たからである。一個のマルクシストであり、中央委員であった人物が、残酷な悪法に挫かれて、理性を偽り、これからは共産主義に対してたたかうことを生涯の目的とするという意味の上申書を公表しなければならなかったことは悲劇である。どんなに日本の治安維持法は暴虐で、通常人の判断も意志も破壊するものであったかを語っている。
日本を今日の全面的破局に導くために、支配者の用いた暴力は、そのように人間ばなれのしたものであった。野呂栄太郎は、その治安維持法によって殺され、その直接の売りわたし手の査問を担当した事件の裁判に当って、自身もまた同じ悪虐な法律のしめなわにかけられ民衆に対する責任と義務と信頼とを裏切る仕儀に陥った。追憶の文章を流暢に書きすすめるとき、逸見氏の胸中に去来したのは、いかなる思いであったろうか。
野呂を尊敬し、後進する人間的な社会理念にとってその生きかたこそ一つの鼓舞であると感じることが真実であるならば、逸見氏は、どうして知識人の勇気をもって、自身の辛苦の中から、野呂栄太郎こそ、嘗て生ける屍となった自身やその他の幾多のものの肉体を超えて、今日生きつづけるものであることを語らなかったのであろうか。
そういう人間の物語こそは、私たちを励し、筆者への理解を正しくし、真に若い世代をゆたかにするものである。逸見氏はあれほどの汚辱に身を浸しながら、どうして今こそ、自身のその汚辱そのものをとおして、復讐しようと欲しないのだろう。悪逆な法律は、人間を生ける屍にするけれども、真実は遂に死せる者をしてさえも叫ばしめるという真理を何故示そうとしなかったのであろうか。肉体において殺されたものが、小林多喜二にしろ、野呂栄太郎にしろ、人類の発展史の裡に決して死することなく生存している。肉体においては生存していても、歴史の進む方向を判断する精神において既に死んでいる者が、死して死なざる生命に甦らされて今日物を云うという場合、死者に甦らされた生者として語るべき唯一のことは、真実あるのみである。信義ある言葉のみが語るべき言葉である。
戦時中、日本の青春は、根柢からふみにじられた。権力が行ったすべての悪業のうち最も若き人々に対してあやまるべき点は、若い人間の宝であるその人々の人間的真実を愚弄したことである。活々として初々しい理性の発芽を、いきなり霜枯れさせた点である。今日、聰明で、誠実な若い世代は、自身の世代が蒙った損傷をとりかえそうとして苦闘しているのである。
その努力の一つの表現として、自分たちの新聞一枚も出そうとしている人々に対して、守るべき信義というものは厳然と立っている。それは歴史を偽らぬ、ということである。 〔一九四六年七月〕
百合子の「信義について」が、まず私に不信をもたらすのは、これだけで文章量で、読者にいかなる心象がもたらされるであろうかという疑念である。上記の一編から百合子の主張の、なにが読者に伝わったであろうか。逸見重雄(へんみしげお)という人物が、百合子によれば「信義」にもとる論難されているのだが、結局、どういうことなのか、よく伝わってこないのである。
百合子は書いている。自分は、逸見氏を語るに当然の立場があると、なぜなら彼の姿を公判にて見かけたこと、また自分は、その公判で罪を着せられた関係者の妻であり、作家であると自分の立場を証明しているが、それは一応のところ首肯できるとしても、百合子は意図的に問題を、文章の外に向かわせてしまっている。
逸見氏の書いた野呂栄太郎の功績と思い出話を、非の打ち所のないものとして認めておきながら、問題は、それ以外にあると言うのである。そこが、事情の知らない読者には、実に、あいまいにベールがかぶされたままなのだ。
百合子の文章には、よく散見できる手法なのだが、人や社会現象を毀誉褒貶を与えるに実に安易な固定観念におぶさったり、一種の風評を前提として断定してしまう癖がある。早い話、レッテル貼りの悪癖だ。これが彼女の文学的核心に所在している。
「信義について」も紙数が少ないと弁解できる問題ではない。逸見氏を、そこまで否定的人物として断定的に書くなら、どうして百合子自身は、査問事件により関係者一同の中でももっとも重刑である無期懲役を与えられた宮本顕治の妻であることを明言しないのだろう。正当に名乗った上で、夫だけが無期懲役にされた不当性を正面から訴えないのだろう。実際、宮本に比べて、逸見氏はわずか数年の懲役刑を与えられたに過ぎなかったことが百合子には不満だったのか。
百合子は、査問事件の公判にしげしげと通い傍聴をかかさなかった。それは日記を見ればよくわかる。そうであるなら、逸見氏を難じる前に、当の査問事件について知っている限りの詳細を書き連ねて、不当な裁判であったことを訴えるのが、率直な姿勢ではないのだろうか。当スパイ査問事件は、敗戦の一年前に判決が出された。各自の量刑は次のごとしである。この裁判は原則、治安維持法とは関係ない。小畑の死をめぐる監禁致死事件として裁かれたのである。年齢は事件当時のもの。量刑は原則、戦後も続いていた。宮本と袴田は、政治犯釈放のGHQ命令に乗じて、いわばどさくさにまぎれて監獄から放り出されたというのが真相のようである。
宮本顕治 ----無期懲役 25歳
袴田里見 ----懲役13年 29歳
秋笹正之輔----懲役7年 31歳(公判で転向)
逸見重雄 ----懲役5年 34歳(早期転向)
木島隆明 ----懲役2年 26歳(早期転向)
大泉兼蔵----34歳 懲役5年
小畑達夫----28歳 査問現場にて死亡
「信義について」が書かれた同じ年。岩波書店で「野呂栄太郎全集」が出版の準備にかかっていた。生前の野呂にもっとも親しかった逸見重雄氏も当然、編集委員として名をあげられていた。この折に、逸見氏がこうむったある不幸な事件をプロレタリア文学研究家の栗原幸夫氏が、次のように回想している。
昭和21年、敗戦の翌年に、当時、岩波書店から刊行される予定だった『野呂栄太郎全集』の編集の仕事を私は手伝っていた。その編集委員の一人に「リンチ」事件の逸見重雄がいた。間もなく宮本顕治から強硬な異議が出て、彼は編集委員会から去った。逸見のような裏切り者を入れることは、野呂を冒涜するものだという宮本の申し入れによったのである。逸見は長い手紙を野呂未亡人に送って、われわれの前から姿を消した。私はまだ二十歳になるかならないかの学生だったが、宮本の強さにひどく胸をつかれたのを今に覚えている。逸見重雄が逮捕されてすぐ屈服し、官憲の要求するような供述をすすんでおこなったのは事実であったにしても、また、そのような人間が野呂の全集をつくるという仕事にふさわしくないという宮本の主張が正当なものであるにしても、やはり少年の私には、かつて野呂の秘書であり協働者であった、銀ぶち眼鏡の学者風の物静かな逸見が気の毒に思えてならなかった。敗戦によって日本は変わったけれど、変わったゆえに、また恐らく彼もまた変わることを望んだがゆえに、彼の前にはこれからも苦しい日々がつづくだろうな、というのが、そのときの私の感慨だった。
「戦前日本共産党史の一帰結」より (『リンチ事件とスパイ問題』三一書房所収)
周知のように宮本顕治と百合子は夫婦である。作家である妻は巧みに粉飾された文章で党派根性にもとづく特定者に対する陰湿な攻撃をなし、獄中12年が自慢の夫の方といえば裏に回って、あちこちのジャーナリズム相手に圧力をかけつつ自分にとって都合の悪い人物を表世界から排斥することに余念がなかったのである。政治活動とは聞こえはよいが、その内実たるや隠蔽工作による自己正当化に他ならなかった。いずれにせよ、こんな風にして戦後の共産主義運動が始まったと言っては、現代の日本共産党に対して失礼だろうか。
それにしても宮本らは、なにゆえに査問事件にかかわる他者の言動と彼らの存在を嫌ったか。彼らの口から真実が話されることが、こわかったのである。党と自分の無謬性が崩れるからである。共産主義の教条の信奉性が壊されるからである。その一点である。徹底的に査問事件の真実を隠し続ける。これが戦後共産党の政治的出発のとなっていたことは言を待たない。
事件当初逸見氏は、大泉、小畑を査問することに反対だったという。宮本らに押し切られ、しぶしぶ行動に加わった。当日、アジトに集結した党員の中では、逸見氏が最年長者だった。宮本などは9歳年下の25歳の若造だった。査問は終始宮本が仕切った。逸見氏は逮捕されて、まもなく転向することを表明した。予審から公判を経て、逸見氏の証言は真実に満ちており、それだけにまた、戦後にいたっても逸見重男氏の存在が宮本夫妻にとっては、なによりの目の上のタンコブとなっていた。
袴田はすでに戦後の始めから身も心も宮本にすっかりと懐柔されてしまい口を封じられ党中央に椅子を与えられ、そこにふんぞり返って喜んでいた二流の人物である。彼が老齢にいたるや、どうも自分が党からいじめられていると思ったらしい。さてもまた戦前の査問事件について、耄碌したあまりよからぬことを口走るようになってきた。そこで、党中央委員会なり幹部会なりに出頭し、まるで被告あつかいにされ、さんざんにいじめられ言質をとられ除名となった次第。齢73。
この袴田が、鬱憤晴らしの暁に善人面して党を統括して、いい気になっている宮本顕治の戦前の内ゲバ「殺し事件」をつぶさに書き上げたのが「同志宮本顕治へ」であった。一種の内部告発文書だが、これが共産主義という輸入思想によってデッチ上げられたイデオロギーの悪事の根幹を、まざまざと露呈させている。
袴田里見は「宮本は明らかに、自分の若さにまかせてしまった」と書いているが、その言葉が宮本のすべてを言い当てているように思われる。早すぎる賛辞は自省することを知らない若者を愚劣な人間にしか育てない。賛辞の多くは流行病を患った衆愚庶民の一過性の錯覚に過ぎないことは歴史が示している。宮本も20歳そこそこで自分の書いた論文『敗北の文学』(昭和六年 顕治 23歳 雑誌『改造』懸賞論文 一等賞・・・ちなみに二等賞は小林秀雄の『様々なる意匠』)が世間で賞賛を浴びたのである。この時に得た二三の栄光にしがみつき、他にはなに一つ己を顧みることもなく100歳近くまで生き恥さらし、つい先日老衰で死んでいった。
(2007.07.20記)

















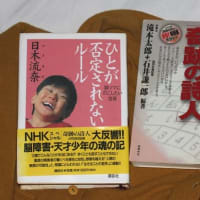

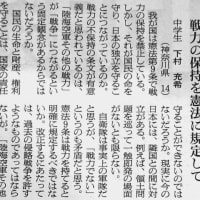






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます