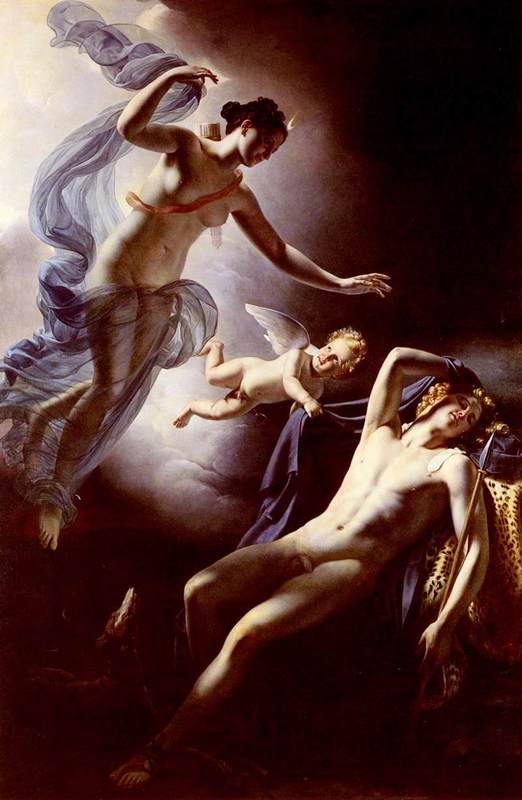「化け物」という言葉の意味は、たとえば、「あいつは化け物だよ、と言って、皆でにやっと笑う」という身体運動が集団的に共鳴することで作られる身体運動‐感覚受容シミュレーションに対応する。つまり、「化け物」という言葉は、何かの物質に関する経験ではなくて、「化け物」と聞いて皆がにやっと笑う、という集団的共鳴運動に関する経験からできている。物質に関する経験ではなくて、言葉に対する集団的運動共鳴の経験が、その言葉に対応する身体運動‐感覚受容シミュレーションの内容です。つまり、こういう場合、話し手と聞き手の脳の内部状態は、どちらも、その言葉に対応して共鳴する身体運動‐感覚受容シミュレーションで表現されている。その意味で、同じ内部状態になっている、といえます。それで、この言葉は通じる。
「化け物」という言葉を聞いた場合、人によって、エイリアンとか、いろいろ化け物的なイメージが頭の中に浮かぶが、ふつう、そのイメージ自体はだれも重要とは思っていなくて、「あいつは化け物だよ、と言って、皆でにやっと笑う」という言葉の使い方についての集団的共鳴運動こそが重要だ、と皆が思っている。言葉を学ぶ子供は、その言葉の使い方に関する集団的運動共鳴を学習することで、その言葉が身につく。そういう言葉の使い方に関する集団的運動共鳴について、皆の脳の内部状態は、ほぼ同じです。この場合、「化け物」と聞いて皆がにやっと笑う、という集団的運動共鳴に「ば・け・も・の」という音節列発音運動が連結した身体運動‐感覚受容シミュレーションが脳内にできている。つまり、「化け物」という言葉を働かせる脳内の物質的実体は、その運動共鳴シミュレーションを表現する神経ネットワークの連結構造である、といえる。
拝読ブログ:かなりの日本人が「funky」という言葉の意味を取り違えていると思うぜ
拝読ブログ:ココCafe のほほん生活 カレー皿の怪。