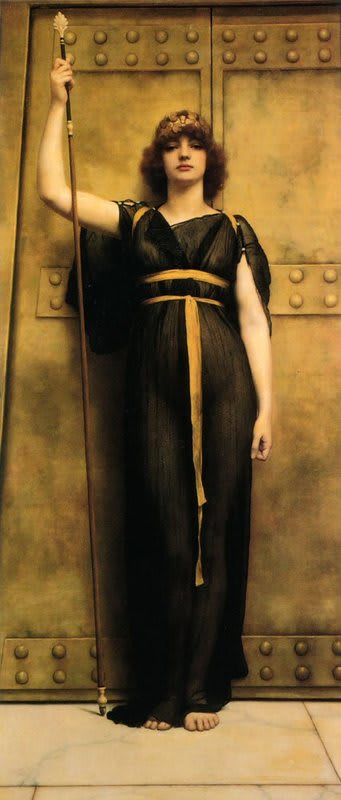こうして言語技術を鍛えられた西洋の知識人たちが使う概念と論理は言葉の信頼感を高めました。言語技術に優れた人々が社会の指導層となり、法律や儀式や制度や書式を作りました。印刷術が発明されて大量の複写が可能となりました。同時に役所や裁判所、学校や教科書や辞典など言葉の使い方を精密に管理する社会的な装置が作られていったのです。それらの装置に言葉の信頼感は担保されて、言葉は話し手や聞き手の人体から離れて客観的に存在できるようになり、ますます信頼され、使いやすく便利になっていきました。
その結果、西洋の人々は何事も言葉で解決しようとするようになりました。それら明瞭な言葉の使用は、宗教、法律、商業、科学、工学の基礎を固め、ルネッサンス以降、西洋文明の大発展を支えました。
しかしそれらのおおもとになっている言葉そのものに関しては、うまく基礎を固めることはできませんでした。言葉とは何か、人間はいまだに理解できない。言葉そのものが何者なのか分からないのに、それを組み合わせて立派な理論が作られる。
もともと言葉だけで作られる理論は、数学のように論理の形式だけは明瞭で完璧ですが、物質世界のどこに正しく当てはまるのか当てはまらないのか、検証のしようがありません。言葉だけで作られる架空の世界の中では、言葉どうしの関係はどこまでも精密に明瞭になれるのですが、その世界と目に見える現実の物質世界との関係はいつまでも曖昧なままで、結局はしっかり繋がりません。