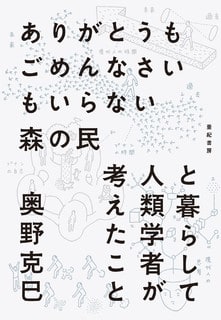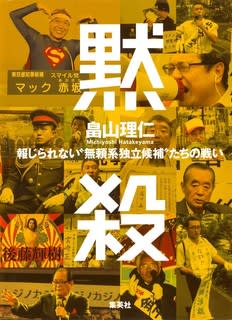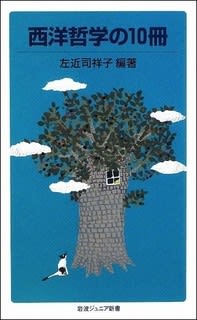大きい方の船はそこそこの速度を保っていてくれているのだが小船のほうは少しづつ速度が落ちてきた。潮は今日がいいのだが、一昨日の予報が雨になっていた。これはきっと「なつぞら」の最終回をきちんと見なさいという神様の命令なのかもしれないと諦めていたら、昨日になって曇りに変わった。作業ができる。これはきちんと9月中にやっておきなさいという神様の命令だと思い、「なつぞら」の神様をあとまわしにして港へと向かった。
前回の塗装では早く陸揚げの段取りをしすぎたのか、進水させるのが午後4時を回ってしまったので、潮汐表をにらみながら午前7時開始とした。
スロープにアプローチしたときはこんな感じ。

ここから潮が引いていくのを待つのだが、待っているとなかなかこう、潮が引いていってくれない。渡船屋の船頭とちょっとしゃべっているとその間にスッと潮が引いている。なんとも時間というのは主観的だ。じゃあどこかで少し時間を潰そうかと三輪車を駆ってツーリングに出発。今日の海はなんとも穏やかだ。

約1時間後、ちょうど後ろの方も着底していた。完全に干上がっている前の方からカキを落としながら艫が干上がるのを待つ。

そこからは一気に作業を加速し午前10時半に作業を終了。道具を片付けて船をコロにセットして午前11時。

午後2時ごろには進水できるはずの計算で、「なつぞら」の最終回を昼の放送でリアルタイムで見た後港に舞い戻ったがどこで計算を間違ったか、全然潮が満ちていない。これじゃあ2時間は待たなきゃならないのじゃないだろうか。で、叔父さんの家で一服して、10月には大きい方も上架したいのでその相談にちからさん仕事場を訪ねてから午後3時、港に三度舞い戻りやっと進水。

塗りたての船は相変わらず恐ろしい速度で海面を疾走してゆく。これで秋の釣りの準備ができた。
家に帰ってあらためて「なつぞら」の録画を見る。記念すべき朝ドラ100作目であったが、どうも脚本がつぎはぎだったという印象が拭えない。最後は「火垂るの墓」まで出てくるとは・・。
なんとか泰樹さんの魅力となっちゃんの可愛さで持ちこたえたというところだろうか。
僕もせっかくだから主題歌の「かわいいあのこ」の替え歌を作ってみた。
♬♬
古い小舟をこぎ出したら
暗い海が続いてて
めげずに巻いていたその先も
釣れなかった世界
上りの釣れる潮すら味方にもできないんだな~
釣り上げたことのない
悪い妄想の獲物
優しいあの子に 笑われる
ルルル・・ルルル・・ルルル~ルル~
♬♬
今日はこれでおしまい・・。
前回の塗装では早く陸揚げの段取りをしすぎたのか、進水させるのが午後4時を回ってしまったので、潮汐表をにらみながら午前7時開始とした。
スロープにアプローチしたときはこんな感じ。

ここから潮が引いていくのを待つのだが、待っているとなかなかこう、潮が引いていってくれない。渡船屋の船頭とちょっとしゃべっているとその間にスッと潮が引いている。なんとも時間というのは主観的だ。じゃあどこかで少し時間を潰そうかと三輪車を駆ってツーリングに出発。今日の海はなんとも穏やかだ。

約1時間後、ちょうど後ろの方も着底していた。完全に干上がっている前の方からカキを落としながら艫が干上がるのを待つ。

そこからは一気に作業を加速し午前10時半に作業を終了。道具を片付けて船をコロにセットして午前11時。

午後2時ごろには進水できるはずの計算で、「なつぞら」の最終回を昼の放送でリアルタイムで見た後港に舞い戻ったがどこで計算を間違ったか、全然潮が満ちていない。これじゃあ2時間は待たなきゃならないのじゃないだろうか。で、叔父さんの家で一服して、10月には大きい方も上架したいのでその相談にちからさん仕事場を訪ねてから午後3時、港に三度舞い戻りやっと進水。

塗りたての船は相変わらず恐ろしい速度で海面を疾走してゆく。これで秋の釣りの準備ができた。
家に帰ってあらためて「なつぞら」の録画を見る。記念すべき朝ドラ100作目であったが、どうも脚本がつぎはぎだったという印象が拭えない。最後は「火垂るの墓」まで出てくるとは・・。
なんとか泰樹さんの魅力となっちゃんの可愛さで持ちこたえたというところだろうか。
僕もせっかくだから主題歌の「かわいいあのこ」の替え歌を作ってみた。
♬♬
古い小舟をこぎ出したら
暗い海が続いてて
めげずに巻いていたその先も
釣れなかった世界
上りの釣れる潮すら味方にもできないんだな~
釣り上げたことのない
悪い妄想の獲物
優しいあの子に 笑われる
ルルル・・ルルル・・ルルル~ルル~
♬♬
今日はこれでおしまい・・。