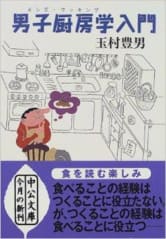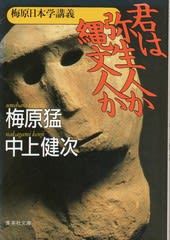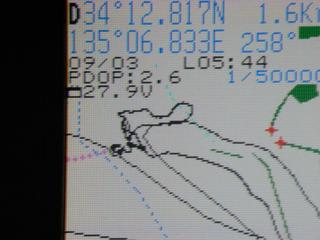玉村 豊男 「男子厨房学入門」読了
タイトルだけを見て買ってみたがいったいどんな人が読むために書かれたものなのかよくわからない。
一応、ビギナーのための入門書となっているが、とくに入門書とは思われない。まあ、そんなことを思いながら読む本ではなくて、玉村豊男が書いた本だということでこの人のファンが読むものだというところか。
いちばん共感したのはあとがきだ。
「男の進化論」と題された論理には、高度経済成長とは、自分自身の生活環境を自分自身の手で整えようとする方向に背を向けて、国のため、社会のため、家族のため・・・つまりすべて“他人”-自分以外の人々-のために自分の力と時間を注ぐことに専心するようになった結果を生み出し、衣食住にかかわる人間にもっとも大切な部分を他人にやらせるようになり、日々の暮らしを営む行為そのものが利潤を生まないものとして軽視されるもとになったものである。
だからいまこそ男は進化しなければならないのだ。再び、他人本位の生活から自分本位の暮らしへ、外の生活よりウチの生活を大切にする方向へ脱却をはかるべきだ。と、説かれている。
これにはうなずかされてしまう。西暦2000年を前にして書かれた文章であるが、2014年の今にはもっと真剣に考えられなければならない論理ではないだろうか。
しかし、たまに魚を釣ってきたときだけ、この魚はこんな料理で食ってみようと思索をめぐらせるだけで、毎日まいにち献立を考えている奥さんには絶対にかなわないとあらためて思い知らされる一冊であった。
タイトルだけを見て買ってみたがいったいどんな人が読むために書かれたものなのかよくわからない。
一応、ビギナーのための入門書となっているが、とくに入門書とは思われない。まあ、そんなことを思いながら読む本ではなくて、玉村豊男が書いた本だということでこの人のファンが読むものだというところか。
いちばん共感したのはあとがきだ。
「男の進化論」と題された論理には、高度経済成長とは、自分自身の生活環境を自分自身の手で整えようとする方向に背を向けて、国のため、社会のため、家族のため・・・つまりすべて“他人”-自分以外の人々-のために自分の力と時間を注ぐことに専心するようになった結果を生み出し、衣食住にかかわる人間にもっとも大切な部分を他人にやらせるようになり、日々の暮らしを営む行為そのものが利潤を生まないものとして軽視されるもとになったものである。
だからいまこそ男は進化しなければならないのだ。再び、他人本位の生活から自分本位の暮らしへ、外の生活よりウチの生活を大切にする方向へ脱却をはかるべきだ。と、説かれている。
これにはうなずかされてしまう。西暦2000年を前にして書かれた文章であるが、2014年の今にはもっと真剣に考えられなければならない論理ではないだろうか。
しかし、たまに魚を釣ってきたときだけ、この魚はこんな料理で食ってみようと思索をめぐらせるだけで、毎日まいにち献立を考えている奥さんには絶対にかなわないとあらためて思い知らされる一冊であった。