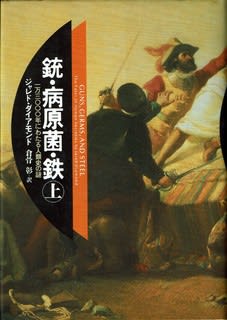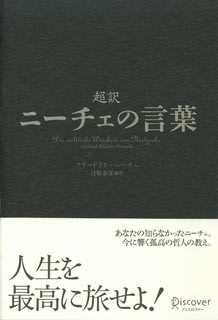赤松利市 「鯖」読了
毎年年末は毎年めったに読まない小説を借りて読むことにしている。今年も宇江敏勝の本を借りようと郷土資料の本棚を物色していると「鯖」と表紙に大きく書かれた本を見つけた。小説の本棚にあったので小説だとは分かったが、中身を見ずにタイトルだけが気に入って借りてしまった。
ストーリーを紹介するとこれから読もうと思う人に申し訳ないが、さわりの部分だけを少し書きたい。
登場人物は、紀州は雑賀崎の漁師。その中で、日本中を船団を組んでその場その場で漁獲を売りながら暮らす人たちだ。漁法はもちろん一本釣りだ。カッタクリと書かれているけれどももうこれはほぼチョクリ仕掛けだろう。まあ、チョクリ竿を使った釣りではなさそうなのでカッタクリということになるのだろうけれども、せっかくだからチョクリ釣りという言葉を採用してもらいたかった。
そんな時代遅れ(と書かれている)な漁師たちも一人減り、二人減りし今では船団と名ばかりの1隻での操業だ。旅から旅への漁では先がないと見た船頭はなけなしの資金をはたいて日本海に浮かぶ小島を買い、そこを拠点にした。
一本釣りでは早朝におこなわれる市場のセリに間に合わない。そんなときに拾ってくれたのが地元の料亭の女将であった。そこへ中国からやってきたビジネスウーマンが鯖のヘしこビジネスを持ちかけてくる。
へしこの漁獲とビジネスウーマンの過去、船団を復活させたい統領や女将の思惑が交錯し物語は進んでゆく・・・。という感じだ。
著者は作家でありながら「住所不定」だそうだ。エリートサラリーマンから実業家そしてホームレスへと転落し、1週間で書き上げた短編が大藪春彦新人賞を受賞した経歴を持っているそうだ。「金と色に狂った人間を書き続けたい。」という言葉通りのストーリーである。
そして、物語の語り部であり主人公の名前は、「水軒新一」。“ミズノキシンイチ”と読むけれでも、この名前はまさしく僕が釣りの拠点にしている水軒の集落がもとになっているにちがいない。作家は香川県出身とのことで雑賀崎ともましてや水軒という土地に何の縁もなかったのだろうけれども、きっとここにロケハンに訪れてこの変わった地名に気付いてくれたのに違いないと思うとうれしくなる。「雑賀丸」という船名や「海の雑賀衆」と言葉にもそそられる。
しかし、主人公たちを雑賀崎の漁師にしてみようとどうして思い立ったのだろう。それも知りたい。
日本人も食べない(こともないだろうが・・)マイナーな食材がビッグビジネスなるのかとか、貧乏漁師が島を買えるのかとかということと和歌山弁をしゃべらない雑賀崎漁師に違和感があることはさておいて、登場する漁師の面々の無頼さや土曜ワイド劇場っぽいストーリーはちょっとわざとらしいけれども普通に面白い。
和歌山が舞台の物語ではないけれどもこの書架になければまずは読むことのないジャンルだ。この本をここに分類してくれた司書に感謝だ。
毎年年末は毎年めったに読まない小説を借りて読むことにしている。今年も宇江敏勝の本を借りようと郷土資料の本棚を物色していると「鯖」と表紙に大きく書かれた本を見つけた。小説の本棚にあったので小説だとは分かったが、中身を見ずにタイトルだけが気に入って借りてしまった。
ストーリーを紹介するとこれから読もうと思う人に申し訳ないが、さわりの部分だけを少し書きたい。
登場人物は、紀州は雑賀崎の漁師。その中で、日本中を船団を組んでその場その場で漁獲を売りながら暮らす人たちだ。漁法はもちろん一本釣りだ。カッタクリと書かれているけれどももうこれはほぼチョクリ仕掛けだろう。まあ、チョクリ竿を使った釣りではなさそうなのでカッタクリということになるのだろうけれども、せっかくだからチョクリ釣りという言葉を採用してもらいたかった。
そんな時代遅れ(と書かれている)な漁師たちも一人減り、二人減りし今では船団と名ばかりの1隻での操業だ。旅から旅への漁では先がないと見た船頭はなけなしの資金をはたいて日本海に浮かぶ小島を買い、そこを拠点にした。
一本釣りでは早朝におこなわれる市場のセリに間に合わない。そんなときに拾ってくれたのが地元の料亭の女将であった。そこへ中国からやってきたビジネスウーマンが鯖のヘしこビジネスを持ちかけてくる。
へしこの漁獲とビジネスウーマンの過去、船団を復活させたい統領や女将の思惑が交錯し物語は進んでゆく・・・。という感じだ。
著者は作家でありながら「住所不定」だそうだ。エリートサラリーマンから実業家そしてホームレスへと転落し、1週間で書き上げた短編が大藪春彦新人賞を受賞した経歴を持っているそうだ。「金と色に狂った人間を書き続けたい。」という言葉通りのストーリーである。
そして、物語の語り部であり主人公の名前は、「水軒新一」。“ミズノキシンイチ”と読むけれでも、この名前はまさしく僕が釣りの拠点にしている水軒の集落がもとになっているにちがいない。作家は香川県出身とのことで雑賀崎ともましてや水軒という土地に何の縁もなかったのだろうけれども、きっとここにロケハンに訪れてこの変わった地名に気付いてくれたのに違いないと思うとうれしくなる。「雑賀丸」という船名や「海の雑賀衆」と言葉にもそそられる。
しかし、主人公たちを雑賀崎の漁師にしてみようとどうして思い立ったのだろう。それも知りたい。
日本人も食べない(こともないだろうが・・)マイナーな食材がビッグビジネスなるのかとか、貧乏漁師が島を買えるのかとかということと和歌山弁をしゃべらない雑賀崎漁師に違和感があることはさておいて、登場する漁師の面々の無頼さや土曜ワイド劇場っぽいストーリーはちょっとわざとらしいけれども普通に面白い。
和歌山が舞台の物語ではないけれどもこの書架になければまずは読むことのないジャンルだ。この本をここに分類してくれた司書に感謝だ。