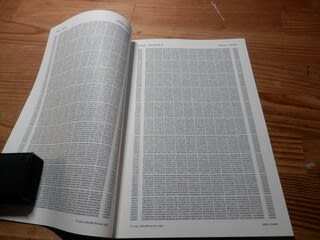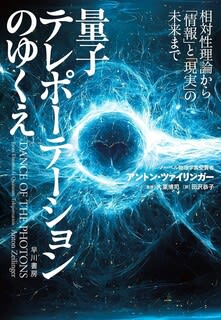ロブ・ダン/著 今西康子/訳 「家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしている」読了
僕の奥さんがこの本を読んでしまったらきっと卒倒してしまうだろう。そして、家の中を歩くとき、つま先立ちで歩くどころか、超能力があるのならきっと肉体を浮遊させて歩くところだ。
しかし、それでも彼女は幾多の生物の呪縛からは逃れられないのだというお話である。
家の周りの生態系(=生物たち)に初めて科学的な目を向けた人というのはアントーニ・ファン・レーウェンフックという人だったそうだ。「歴史上はじめて顕微鏡により微生物を観察した人」として知られている。それから100年あまり、誰も家の周りに潜んでいる生物たちを顧みる人はいなかった。そんな中、著者たちの研究グループのほかいくつかのグループがそれに注目し始めたという。
その結果というと、おそらく数百程度と考えられていた生物種が20万種を超える生物が発見されたのである。
屋内環境生物の研究のほとんどは害虫や病原体に関するものだったので継続的に大規模な調査を行ったのは著者たちのグループが初めてあった。どうしてこんなに身近な環境が調査されてこなかったのか。それは研究者たちの偏見にあったのではないかと著者は考えている。生物の研究のフィールドは、例えばコスタリカのような熱帯地域でしかできないという近視眼的な考えや、同じく潜在的経済価値をもった生物はきっとこんな身近な場所にはいないという思い込みからなのだと学会の見識の狭さを嘆いている。
20万種の生物のうち、ほぼすべてと言えるのは細菌や菌類で、肉眼で見える生物でも大半は節足動物である。脊椎動物は数十種から数百種というところだそうだ。
この本にはそれらの生物は人間の生活にどういった影響を及ぼしているのかが書かれている。しかし、こういった調査が始まったのはつい最近(この本が本国で出版されたのは2018年だ。)のことであり、まだまだ仮説の域を出ない部分もあるようだが、それでもなかなか衝撃的な事実が書かれている。
第1章は細菌の世界についてというところから始まるが、これはいちばん最後に書くとして、まずは節足動物の世界はどうなっているかということを書いてゆきたいと思う。
節足動物に限らず、家に棲む生物たちの大半は人間に危害を与えるものではないと考えられている。無害か、むしろ益虫と考えられるもののほうが多い。クモなどはその最たるもので、伝染病を媒介する虫を捕らえてくれるのである。人間も過去からその特性を利用してきた。アフリカの一部地域では集団性のあるクモの巣の塊を家の中で飼っていたりもしたそうである。
また、人の経済活動の役に立つ生物があるかもしれないという。家に棲む生物というのは、少なからず家を食べている(=分解している)のであり、その能力を利用することで大量のゴミを効率よく分解したり、その分解物から経済的に役に立つ物質を取り出すことができるかもしれないというのである。
この本では、カマドウマが例として挙げられている。カマドウマは体内にリグニンを分解する細菌を宿している。リグニンというのは植物の細胞壁を構成する物質のひとつだが、自然界では分解されにくい物質で強いアルカリ性を示す。製紙の過程で出てくる物質でゴミにしかならないものだったそうで、焼却処分するしかなかったのが、この細菌を使うと効率よく処分できる可能性がある。また、これを分解することによって樹脂や燃料などに変換できる可能性もあるそうだ。
そのほか、チャタテムシという昆虫にはセルロースを分解できる酵素を持っていることがわかった。これはバイオ燃料の生産に役立たせることができるかもしれないということだ。
そういったこともすごいことだが、この本の圧巻といえる部分は家に棲む細菌たちの働きだ。
家の中には20万種を超える生物が棲んでいるというのであるが、先にも書いた通り、そのうちの4分の3は細菌、4分の1が真菌、そのわずかの残りが節足動物、植物などである。
それはあたかも家全体が細菌や真菌でコーティングされているかのようであり、人体も同じである。消化管を含めて体外と言われる部分にはどっさりと細菌が付着している。
これは家だけでなく、ISSの中でも同じである。人が住むところには必ず細菌がいる。特にISSでは人間由来の細菌(人間の体に付着している細菌類)が多いのであまり想像したくない臭いがするらしい。プラスチックと生ごみ、体臭の臭いが混じり合った臭いというが、いったいどんな臭さなのだろう。
壁や床だけではなく、当然のごとく水道管、ガスボイラー、風呂釜、シャワーヘッドなどには特にたくさんの細菌が棲んでいる。こういうところのねばねばは全部細菌のコロニーだ。水を出すたびにそれらが飛び出てくる。水道水といえども無菌ではない。時すでに遅しで水道水だけでなくペットボトルの水にでも細菌は混ざっているという。
まあ、それだけどこにでも細菌は潜んでいるというのである。
しかし、それらすべての細菌が有害かというと、そうではなくてほとんどの細菌はまったく無害か逆に有益であるというのである。
細菌の有益性には3つのパターンがあるという。ひとつは免疫力を高める働き、ひとつは有害な細菌の増殖を排除する働き、ひとつは免疫の暴走を抑止する働きだ。
免疫力を高めるというのはいちばんよくわかる。普段からたくさんの異物に遭遇することで免疫細胞たちを鍛えることができるのである。
有害な細菌の増殖を排除する働きというのは、無害な細菌が繁殖していれば、そこはすでに占拠されているので、有害な細菌がやってきて餌を探してもそれらに喰われてしまっているのである。目に見える生物に当てはめても同じで、隠れ場所を探してもすでに別の生物が潜んでいてたたき出されてしまうのである。
これは生態系が多様であればあるほどその効果が生まれる。病院などはその多様性を撲滅すべく殺菌、滅菌に勤しむものだから、一度悪玉菌が侵入してしまうと院内感染が爆発することになる。
歴史的には、1960年代、黄色ブドウ球菌ファージ型80/81という病原菌対策として、502A型という黄色ブドウ球菌を事前に接種させるなどをして効果を得たことがあったけれども数例の事故によってとん挫し、世界の医療機関はまったく逆の道を進むことになったらしい。
免疫の暴走を抑止する働きについてはエビデンスはないものの、喘息やアレルギーその他の免疫異常の疾患というのは公衆衛生のシステムやインフラが整っている地域ほどその発生頻度が高いという事実がある。そういう事実から、様々な細菌に暴露することが免疫の暴走を食い止めるための何かの役にたっているというのである。
確かにそう思えるという事実が僕のそばにもあった。僕の友人のひとりは駅の裏の豪邸に住んでいるがその友人は長く大腸性潰瘍を患っていた。相当裕福なのには違いないが、食生活はそうと貧しいようだ。貧しいというのにはかなり語弊があって、僕に比べれば相当高級な食材を食べているに違いない。まず、業務スーパーで売っている食いものなんて食べたことがないだろう。しかし、10年ほど前、自然薯を採ってきた話をしたとき、そんなものを食ったことがないというので少しだけ分けてあげたものの、それを煮て食べたというのである。新鮮なサバをあげたと気にも、「ウチの家ではだれも魚をさばくことができない。」という。あのサバはひょっとしてゴミ箱に直送されたのではないかと心配をしたものだ。
自分で取ってくる食材を食べない生活というのは普通なら普通の生き方だと考えるべきなのかもしれないが、様々な細菌に暴露したほうがいいという意味では僕の食生活のほうがはるかに健全だと言いたいのである。
さらに家に棲む生物たちはひとの性格形成までにも影響を与えているという。
この本では、トキソプラズマ原虫について書かれている。この原虫は、猫科の動物を最終宿主として世代交代をする生物だ。ネズミを媒介者としてライフサイクルを形成していて、最終宿主の猫の身体に入るためにネズミの脳に影響を及ぼして活動的な状態にすることで猫の目の前に現れる確率を上げて食われやすくしている。
人間にも感染して脳の中に入り込んで重篤な症状を引き起こすこともあるらしい。
重篤な状態にならなくても、自分の性格が少しおかしいと感じた研究者がいた。その研究者は、戦場で恐怖を感じなかったり、交通事故を恐れないような行動をしたり、反政府的な発言が自分の命の危機を招いてしまうような環境でも発言することに不安を感じなかったそうだ。
自分自身でも不可解と思える行動はきっと何かに感染しているのではないかと考えて血液検査をしたところ、トキソプラズマ抗体が陽性であったということがわかった。
この研究者はさらに同僚の研究者たちも検査をしてみると、陰性だった同僚の教授たちのうち、3分の1は学科長、福学部長、学部長という要職に就いていた。これは、トキソプラズマに感染していなければ冷静沈着に物事を考える傾向になりリーダー的な役割を任せられるからだと考えられるというのだ。逆に、トキソプラズマ原虫への暴露歴のある人は交通事故の起こしやすさが2.5倍になるという調査もある。暴露歴があるひとは危険を冒す傾向が強いという結論になるのだ。
まあ、これにも確たるエビデンスはない。トキソプラズマ原虫が誘導する性格は女性ではその傾向が現れないというところからも少し説得力に欠けるし、僕の友人の大腸性潰瘍も彼だけがその病気になっただけで彼の家族もそうであるということがない。
すべては確率の問題であるのかもしれないと思いながらも、いやいやそうとも言い切れないぞという思いもしてくる。生物多様性が重要だということはきっと間違いがないとは思う。ただ、自分のひと嫌いも性格の悪さも、ヒトギライ原虫とセイカクワルイゾ細菌に感染してしまっているからだと思うとなんとなく諦めがつくというものだ。
現在の家屋というのは密閉断熱というのが基本だそうだ。この性能がよければよいほど所得控除が高かったりもするらしい。
著者の理論からすると、こういう家屋は生物多様性の乏しさの極みだということになる。もう、僕には関係のない話だが、これか先の人たちはどんな病気を患いどんな性格になっていくのかと心配にはなってきたりもするのである。
なかなか面白い本であった。
僕の奥さんがこの本を読んでしまったらきっと卒倒してしまうだろう。そして、家の中を歩くとき、つま先立ちで歩くどころか、超能力があるのならきっと肉体を浮遊させて歩くところだ。
しかし、それでも彼女は幾多の生物の呪縛からは逃れられないのだというお話である。
家の周りの生態系(=生物たち)に初めて科学的な目を向けた人というのはアントーニ・ファン・レーウェンフックという人だったそうだ。「歴史上はじめて顕微鏡により微生物を観察した人」として知られている。それから100年あまり、誰も家の周りに潜んでいる生物たちを顧みる人はいなかった。そんな中、著者たちの研究グループのほかいくつかのグループがそれに注目し始めたという。
その結果というと、おそらく数百程度と考えられていた生物種が20万種を超える生物が発見されたのである。
屋内環境生物の研究のほとんどは害虫や病原体に関するものだったので継続的に大規模な調査を行ったのは著者たちのグループが初めてあった。どうしてこんなに身近な環境が調査されてこなかったのか。それは研究者たちの偏見にあったのではないかと著者は考えている。生物の研究のフィールドは、例えばコスタリカのような熱帯地域でしかできないという近視眼的な考えや、同じく潜在的経済価値をもった生物はきっとこんな身近な場所にはいないという思い込みからなのだと学会の見識の狭さを嘆いている。
20万種の生物のうち、ほぼすべてと言えるのは細菌や菌類で、肉眼で見える生物でも大半は節足動物である。脊椎動物は数十種から数百種というところだそうだ。
この本にはそれらの生物は人間の生活にどういった影響を及ぼしているのかが書かれている。しかし、こういった調査が始まったのはつい最近(この本が本国で出版されたのは2018年だ。)のことであり、まだまだ仮説の域を出ない部分もあるようだが、それでもなかなか衝撃的な事実が書かれている。
第1章は細菌の世界についてというところから始まるが、これはいちばん最後に書くとして、まずは節足動物の世界はどうなっているかということを書いてゆきたいと思う。
節足動物に限らず、家に棲む生物たちの大半は人間に危害を与えるものではないと考えられている。無害か、むしろ益虫と考えられるもののほうが多い。クモなどはその最たるもので、伝染病を媒介する虫を捕らえてくれるのである。人間も過去からその特性を利用してきた。アフリカの一部地域では集団性のあるクモの巣の塊を家の中で飼っていたりもしたそうである。
また、人の経済活動の役に立つ生物があるかもしれないという。家に棲む生物というのは、少なからず家を食べている(=分解している)のであり、その能力を利用することで大量のゴミを効率よく分解したり、その分解物から経済的に役に立つ物質を取り出すことができるかもしれないというのである。
この本では、カマドウマが例として挙げられている。カマドウマは体内にリグニンを分解する細菌を宿している。リグニンというのは植物の細胞壁を構成する物質のひとつだが、自然界では分解されにくい物質で強いアルカリ性を示す。製紙の過程で出てくる物質でゴミにしかならないものだったそうで、焼却処分するしかなかったのが、この細菌を使うと効率よく処分できる可能性がある。また、これを分解することによって樹脂や燃料などに変換できる可能性もあるそうだ。
そのほか、チャタテムシという昆虫にはセルロースを分解できる酵素を持っていることがわかった。これはバイオ燃料の生産に役立たせることができるかもしれないということだ。
そういったこともすごいことだが、この本の圧巻といえる部分は家に棲む細菌たちの働きだ。
家の中には20万種を超える生物が棲んでいるというのであるが、先にも書いた通り、そのうちの4分の3は細菌、4分の1が真菌、そのわずかの残りが節足動物、植物などである。
それはあたかも家全体が細菌や真菌でコーティングされているかのようであり、人体も同じである。消化管を含めて体外と言われる部分にはどっさりと細菌が付着している。
これは家だけでなく、ISSの中でも同じである。人が住むところには必ず細菌がいる。特にISSでは人間由来の細菌(人間の体に付着している細菌類)が多いのであまり想像したくない臭いがするらしい。プラスチックと生ごみ、体臭の臭いが混じり合った臭いというが、いったいどんな臭さなのだろう。
壁や床だけではなく、当然のごとく水道管、ガスボイラー、風呂釜、シャワーヘッドなどには特にたくさんの細菌が棲んでいる。こういうところのねばねばは全部細菌のコロニーだ。水を出すたびにそれらが飛び出てくる。水道水といえども無菌ではない。時すでに遅しで水道水だけでなくペットボトルの水にでも細菌は混ざっているという。
まあ、それだけどこにでも細菌は潜んでいるというのである。
しかし、それらすべての細菌が有害かというと、そうではなくてほとんどの細菌はまったく無害か逆に有益であるというのである。
細菌の有益性には3つのパターンがあるという。ひとつは免疫力を高める働き、ひとつは有害な細菌の増殖を排除する働き、ひとつは免疫の暴走を抑止する働きだ。
免疫力を高めるというのはいちばんよくわかる。普段からたくさんの異物に遭遇することで免疫細胞たちを鍛えることができるのである。
有害な細菌の増殖を排除する働きというのは、無害な細菌が繁殖していれば、そこはすでに占拠されているので、有害な細菌がやってきて餌を探してもそれらに喰われてしまっているのである。目に見える生物に当てはめても同じで、隠れ場所を探してもすでに別の生物が潜んでいてたたき出されてしまうのである。
これは生態系が多様であればあるほどその効果が生まれる。病院などはその多様性を撲滅すべく殺菌、滅菌に勤しむものだから、一度悪玉菌が侵入してしまうと院内感染が爆発することになる。
歴史的には、1960年代、黄色ブドウ球菌ファージ型80/81という病原菌対策として、502A型という黄色ブドウ球菌を事前に接種させるなどをして効果を得たことがあったけれども数例の事故によってとん挫し、世界の医療機関はまったく逆の道を進むことになったらしい。
免疫の暴走を抑止する働きについてはエビデンスはないものの、喘息やアレルギーその他の免疫異常の疾患というのは公衆衛生のシステムやインフラが整っている地域ほどその発生頻度が高いという事実がある。そういう事実から、様々な細菌に暴露することが免疫の暴走を食い止めるための何かの役にたっているというのである。
確かにそう思えるという事実が僕のそばにもあった。僕の友人のひとりは駅の裏の豪邸に住んでいるがその友人は長く大腸性潰瘍を患っていた。相当裕福なのには違いないが、食生活はそうと貧しいようだ。貧しいというのにはかなり語弊があって、僕に比べれば相当高級な食材を食べているに違いない。まず、業務スーパーで売っている食いものなんて食べたことがないだろう。しかし、10年ほど前、自然薯を採ってきた話をしたとき、そんなものを食ったことがないというので少しだけ分けてあげたものの、それを煮て食べたというのである。新鮮なサバをあげたと気にも、「ウチの家ではだれも魚をさばくことができない。」という。あのサバはひょっとしてゴミ箱に直送されたのではないかと心配をしたものだ。
自分で取ってくる食材を食べない生活というのは普通なら普通の生き方だと考えるべきなのかもしれないが、様々な細菌に暴露したほうがいいという意味では僕の食生活のほうがはるかに健全だと言いたいのである。
さらに家に棲む生物たちはひとの性格形成までにも影響を与えているという。
この本では、トキソプラズマ原虫について書かれている。この原虫は、猫科の動物を最終宿主として世代交代をする生物だ。ネズミを媒介者としてライフサイクルを形成していて、最終宿主の猫の身体に入るためにネズミの脳に影響を及ぼして活動的な状態にすることで猫の目の前に現れる確率を上げて食われやすくしている。
人間にも感染して脳の中に入り込んで重篤な症状を引き起こすこともあるらしい。
重篤な状態にならなくても、自分の性格が少しおかしいと感じた研究者がいた。その研究者は、戦場で恐怖を感じなかったり、交通事故を恐れないような行動をしたり、反政府的な発言が自分の命の危機を招いてしまうような環境でも発言することに不安を感じなかったそうだ。
自分自身でも不可解と思える行動はきっと何かに感染しているのではないかと考えて血液検査をしたところ、トキソプラズマ抗体が陽性であったということがわかった。
この研究者はさらに同僚の研究者たちも検査をしてみると、陰性だった同僚の教授たちのうち、3分の1は学科長、福学部長、学部長という要職に就いていた。これは、トキソプラズマに感染していなければ冷静沈着に物事を考える傾向になりリーダー的な役割を任せられるからだと考えられるというのだ。逆に、トキソプラズマ原虫への暴露歴のある人は交通事故の起こしやすさが2.5倍になるという調査もある。暴露歴があるひとは危険を冒す傾向が強いという結論になるのだ。
まあ、これにも確たるエビデンスはない。トキソプラズマ原虫が誘導する性格は女性ではその傾向が現れないというところからも少し説得力に欠けるし、僕の友人の大腸性潰瘍も彼だけがその病気になっただけで彼の家族もそうであるということがない。
すべては確率の問題であるのかもしれないと思いながらも、いやいやそうとも言い切れないぞという思いもしてくる。生物多様性が重要だということはきっと間違いがないとは思う。ただ、自分のひと嫌いも性格の悪さも、ヒトギライ原虫とセイカクワルイゾ細菌に感染してしまっているからだと思うとなんとなく諦めがつくというものだ。
現在の家屋というのは密閉断熱というのが基本だそうだ。この性能がよければよいほど所得控除が高かったりもするらしい。
著者の理論からすると、こういう家屋は生物多様性の乏しさの極みだということになる。もう、僕には関係のない話だが、これか先の人たちはどんな病気を患いどんな性格になっていくのかと心配にはなってきたりもするのである。
なかなか面白い本であった。