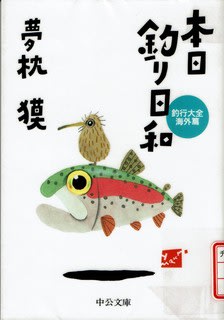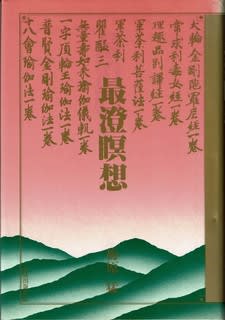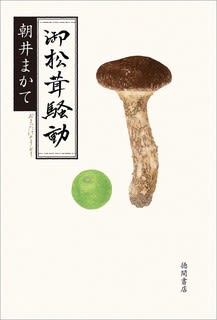常見陽平 「僕たちはガンダムのジムである」読了
筆者は元リクルート社員で「労働社会学」という学問の講師や労働に関するコメンテーターなどもやっている人だそうだ。
今年の流行語にもなった、働き方改革の真っ只中にいる人のようでもある。
タイトルが面白くて読んでみた。タイトルにある、「ジム」というのは機動戦士ガンダムに出てくるロボット兵器で、主人公が搭乗するガンダムは連邦軍のプロトタイプなので機能的にも優れているしその主人公も最終的にはエスパー並みの能力を発揮して連邦軍を勝利に導く。対して、「ジム」はガンダムをベースに量産型として製造されたもので搭乗者も一般兵であり兵器としての能力もガンダムに比べるとかなり劣っている。物語の中ではやたらと数は出てくるものの大して活躍することも無く、赤い彗星のシャアにはボコボコにされるという役回りを演じている。仮面ライダーでいうとショッカーの戦闘員という感じだ。
日本のサラリーマンは、過酷な就職戦線を勝ち残り(この本の初版は2012年の出版なので、まだ就職氷河期の時代を引きずっているころだ。)その自信から一度は自分はガンダムであるという錯覚に陥り、夢を見るけれども大半は主役でもなくエスパーでもない、その他大勢の「ジム」であると言っている。だから、ジムはジムらしい世の中の渡り方をするべきだ。そういう内容の本である。
ひとの人生をガンダムになぞらえるとうのも奇をてらいすぎているとは思うのだが、そこは新書の悲しさ。もっと若い人、自分はガンダムでありたいと思いながらも現実はジムであると認識せざるおえない人たちが読むべき本ではあった。
すでに自分はジムであり、悩み終わったおじさんサラリーマンには郷愁でしかない。もっとも僕はジムよりもっと弱そうな、ミジンコがデザインの元ではないかと思える「ボール」という兵器程度であったのだが・・・。
僕がそう悟ったのはいつごろだっただろうか、大きな転機は上司が亡くなったことだった。このブログにの何度か書いたけれども、いつも一緒に釣りに行っていた上司が癌で入院してから半年ほどであっけなく亡くなった。最後の釣行の時には、最近背中が痛いので病院へ行かなければと言っていてそのまま入院して退院することはなかった。まだ若くて50歳にはなっていなかった。父親ほども歳が離れていない人で身近にいた人が亡くなるというのはショックだった。人は死ぬのだという当たり前のことをはじめて思い知った。その頃、職場ではたくさんのトラブルを抱え込み、毎週日曜日に新聞に入るアイデムをよく眺めていたものだ。その反面、死ぬということを目の当たりにしてやりたいことをやれずに、それもそのバイアスが会社であるのならそんなアホらしいことはない。まずは自分のやりたいことをやらなければもったいない。
その後、自分より先に昇進してゆく同期を見ながら、やっぱり自分はダメだなと思いながら、リストラの陰に怯え、それも50歳を越えると今度は開き直ってくる。休日も出勤して仕事をしている彼らを見ていると僕にはとてもじゃないけど真似ができない。
著者は社畜という言葉をこの本の中でよく使っているけれども、僕は社畜にもなれなかったということだ。まあ、それでもここまで首にならずに来ることができたし、多分、社畜にもなっていない。これから先は一体どうなっていくのかはわからない。まず、これ以上の昇進はあるはずもなく、また、昇進させられて休みが無くなるのはご免だ。役員と面と向かう度胸も能力もない。今の状態で余力を残して流してゆくのが得策でもある。
それを許してくれてきたこの会社にもある意味感謝をしなければならない。
その分、給料は限りなく安いわけではあるけれども・・・。
筆者は元リクルート社員で「労働社会学」という学問の講師や労働に関するコメンテーターなどもやっている人だそうだ。
今年の流行語にもなった、働き方改革の真っ只中にいる人のようでもある。
タイトルが面白くて読んでみた。タイトルにある、「ジム」というのは機動戦士ガンダムに出てくるロボット兵器で、主人公が搭乗するガンダムは連邦軍のプロトタイプなので機能的にも優れているしその主人公も最終的にはエスパー並みの能力を発揮して連邦軍を勝利に導く。対して、「ジム」はガンダムをベースに量産型として製造されたもので搭乗者も一般兵であり兵器としての能力もガンダムに比べるとかなり劣っている。物語の中ではやたらと数は出てくるものの大して活躍することも無く、赤い彗星のシャアにはボコボコにされるという役回りを演じている。仮面ライダーでいうとショッカーの戦闘員という感じだ。
日本のサラリーマンは、過酷な就職戦線を勝ち残り(この本の初版は2012年の出版なので、まだ就職氷河期の時代を引きずっているころだ。)その自信から一度は自分はガンダムであるという錯覚に陥り、夢を見るけれども大半は主役でもなくエスパーでもない、その他大勢の「ジム」であると言っている。だから、ジムはジムらしい世の中の渡り方をするべきだ。そういう内容の本である。
ひとの人生をガンダムになぞらえるとうのも奇をてらいすぎているとは思うのだが、そこは新書の悲しさ。もっと若い人、自分はガンダムでありたいと思いながらも現実はジムであると認識せざるおえない人たちが読むべき本ではあった。
すでに自分はジムであり、悩み終わったおじさんサラリーマンには郷愁でしかない。もっとも僕はジムよりもっと弱そうな、ミジンコがデザインの元ではないかと思える「ボール」という兵器程度であったのだが・・・。
僕がそう悟ったのはいつごろだっただろうか、大きな転機は上司が亡くなったことだった。このブログにの何度か書いたけれども、いつも一緒に釣りに行っていた上司が癌で入院してから半年ほどであっけなく亡くなった。最後の釣行の時には、最近背中が痛いので病院へ行かなければと言っていてそのまま入院して退院することはなかった。まだ若くて50歳にはなっていなかった。父親ほども歳が離れていない人で身近にいた人が亡くなるというのはショックだった。人は死ぬのだという当たり前のことをはじめて思い知った。その頃、職場ではたくさんのトラブルを抱え込み、毎週日曜日に新聞に入るアイデムをよく眺めていたものだ。その反面、死ぬということを目の当たりにしてやりたいことをやれずに、それもそのバイアスが会社であるのならそんなアホらしいことはない。まずは自分のやりたいことをやらなければもったいない。
その後、自分より先に昇進してゆく同期を見ながら、やっぱり自分はダメだなと思いながら、リストラの陰に怯え、それも50歳を越えると今度は開き直ってくる。休日も出勤して仕事をしている彼らを見ていると僕にはとてもじゃないけど真似ができない。
著者は社畜という言葉をこの本の中でよく使っているけれども、僕は社畜にもなれなかったということだ。まあ、それでもここまで首にならずに来ることができたし、多分、社畜にもなっていない。これから先は一体どうなっていくのかはわからない。まず、これ以上の昇進はあるはずもなく、また、昇進させられて休みが無くなるのはご免だ。役員と面と向かう度胸も能力もない。今の状態で余力を残して流してゆくのが得策でもある。
それを許してくれてきたこの会社にもある意味感謝をしなければならない。
その分、給料は限りなく安いわけではあるけれども・・・。