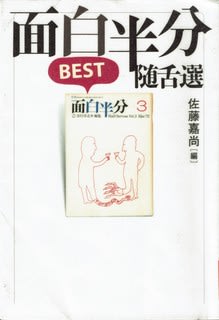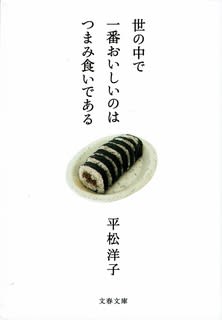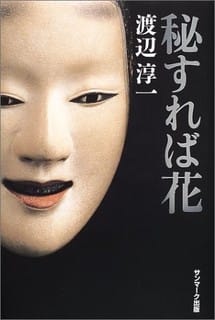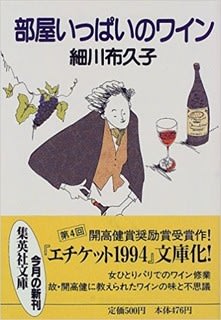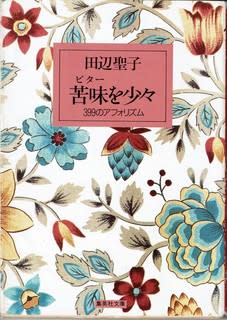佐藤嘉尚 「面白半分BEST随舌選 」読了
「私の開高健」の著者細川布久子のつながりでこの本を読んでみた。
雑誌「面白半分」は、この本の編者である、佐藤嘉尚が1971年に興した株式会社面白半分が発行した月刊誌で1980年に会社が倒産して廃刊になった。編集長は人気作家が(原則)半年毎に交代していた。編集長は吉行淳之介、野坂昭如、開高健、五木寛之、藤本義一、金子光晴、井上ひさし、遠藤周作、田辺聖子、筒井康隆、半村良、田村隆一、一松二生が交代で務めた。「四畳半襖の下張り」はこの雑誌に掲載されて問題になったらしい。
この本は「随舌」というコラムの選集になっている。吉行淳之介が「随筆」は原稿料が高く付くということで談話を録音してそれを原稿に起こしたものらしいが、このコラムは人気があったそうで廃刊まで続いたそうだ。
執筆者のほぼ全員が戦前の生まれですでに物故しているような人たちばかりだが、その語り口、表現方法、語彙の豊富さ、それに、なんというのだろう、艶のある文章とでもいうのか、現代の小説家やコラムニストではなかなか書けない文章ではないだろうか。エロはあっても政治とセックスをテーマにしないような文章が今の時代に受けるのは難しいというのもあるだろうが、それを差し引いてもうまい文章だと思う。
まあ、こういう文章をいいと思うから古本ばかりを探しているというのもあるのだろうから考えが偏っているのかもしれないのでそれは個人的な感想ではある。
しかし、そう思っている人もそこそこの数がいるのか、この本も図書館で借りたものだが、相当手垢がついてしまっている。2007年の出版なのでそれほど古い本でもないのでやっぱり借りる人が多いのではないだろうか。実際、これを借りるときも予約を入れてから3週間待ってやっと手元にきたくらいだ。
いったいどんな人が借りているのか興味が湧いてくるとともに、今風の文章に魅力を感じない僕は世の中に取り残されつつあるのだと実感するのだ。
「私の開高健」の著者細川布久子のつながりでこの本を読んでみた。
雑誌「面白半分」は、この本の編者である、佐藤嘉尚が1971年に興した株式会社面白半分が発行した月刊誌で1980年に会社が倒産して廃刊になった。編集長は人気作家が(原則)半年毎に交代していた。編集長は吉行淳之介、野坂昭如、開高健、五木寛之、藤本義一、金子光晴、井上ひさし、遠藤周作、田辺聖子、筒井康隆、半村良、田村隆一、一松二生が交代で務めた。「四畳半襖の下張り」はこの雑誌に掲載されて問題になったらしい。
この本は「随舌」というコラムの選集になっている。吉行淳之介が「随筆」は原稿料が高く付くということで談話を録音してそれを原稿に起こしたものらしいが、このコラムは人気があったそうで廃刊まで続いたそうだ。
執筆者のほぼ全員が戦前の生まれですでに物故しているような人たちばかりだが、その語り口、表現方法、語彙の豊富さ、それに、なんというのだろう、艶のある文章とでもいうのか、現代の小説家やコラムニストではなかなか書けない文章ではないだろうか。エロはあっても政治とセックスをテーマにしないような文章が今の時代に受けるのは難しいというのもあるだろうが、それを差し引いてもうまい文章だと思う。
まあ、こういう文章をいいと思うから古本ばかりを探しているというのもあるのだろうから考えが偏っているのかもしれないのでそれは個人的な感想ではある。
しかし、そう思っている人もそこそこの数がいるのか、この本も図書館で借りたものだが、相当手垢がついてしまっている。2007年の出版なのでそれほど古い本でもないのでやっぱり借りる人が多いのではないだろうか。実際、これを借りるときも予約を入れてから3週間待ってやっと手元にきたくらいだ。
いったいどんな人が借りているのか興味が湧いてくるとともに、今風の文章に魅力を感じない僕は世の中に取り残されつつあるのだと実感するのだ。