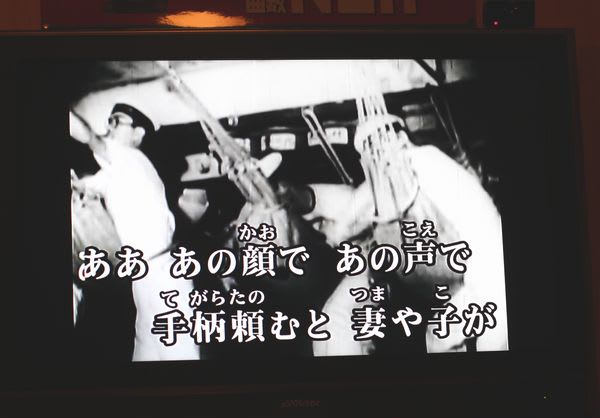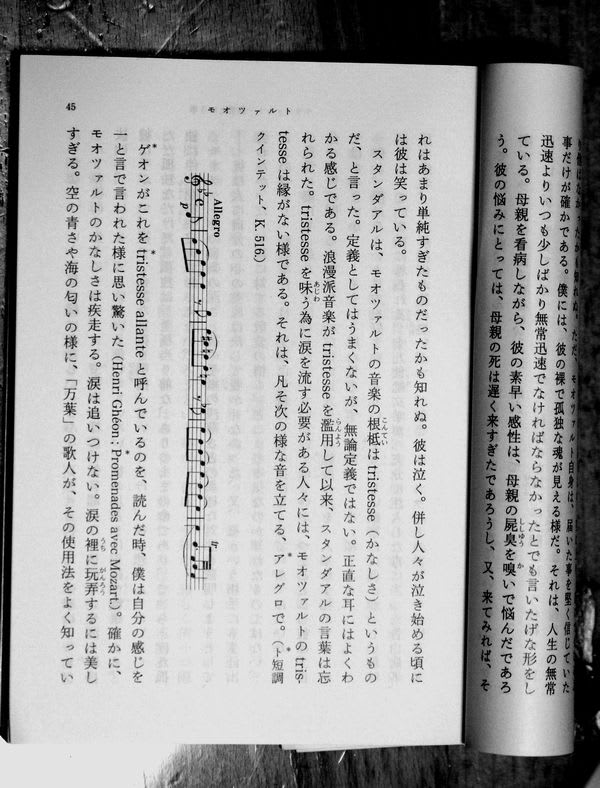<以下、2011.11.10 記>
数日前に素敵な女性が登場している動画を見たので、ここに紹介しておく。
http://www.youtube.com/watch?v=7WRJNIjl7pY
http://www.youtube.com/watch?v=rQEFoyGMMEw
西舘好子さんは日本子守唄協会という団体の理事長をなされているらしい。おそらく西舘さんが、発起人であり創設者なのだろう。この団体名を目にしたときに、わたしは西舘好子さんのことを一発で理解できたと思った。わが国に、何々協会とかNPO法人を名乗る団体は、何万何千とあるに違いない。だが、かくほどまでに美(うるわ)しい団体名は昨日まで、目にしたことも耳にしたこともなかった。
日本子守唄協会
http://www.komoriuta.jp/ar/A05090601.html
そこで本題に入るが、わたしもまた西舘さんの近著『表裏 井上ひさし協奏曲』を読んでみた。驚いたのなんのって、興奮のあまり二日ほど眠れなかった。最初わたしは西舘さんのことは何も知らなかったので、週刊誌などに、よく掲載されている有名人から捨てられた女が、私怨をかざして報復的に彼の知られざる生活を暴露する手記か、なにかかと思いつつ最初のページを開いてみたのだが、それがまったく、そうではなかった。
井上ひさしは、いまや伝説化された感すらあるNHKで放送された児童向けの人形劇『ひょっこりひょうたん島』の脚本を書き、これで世に出た作家である。直木賞も受賞した、自前の劇団も作った。たくさんのベストセラーを書いた。ここまで、なにもかも元妻の西舘さんと二人三脚でやってきたのである。
動画の中で西舘さんが言っている。人間、むしろ偉くなるとあさましい地金が出てきてしまうのだと。なんとか筆一本で食べられるように、世に認められようと夫婦して苦労しているときは、卑しい地金は隠れているものだと。誰でもそうだ。男はとくに、そうである。地位があがったり思わぬ金が入り始めると、それまでの、いと優しき善人ぶったメッキが、みるみるはげてくる。心根の底に隠れていた俗物性が表面に出てきてしまう。面子や沽券というものが、なにより大切になってくる。時には、なかなか凶暴になる。かといって、もちろん井上ひさしは悪党ではない。西舘さんは、一行たりとも元夫の悪口を書いていない。
昨年、井上ひさしは没した。新聞で見たのだが、井上ひさしを偲ぶ会の最後に挨拶に立たれた現夫人のユリさんは、「井上ひさしは天才です」と申していたそうだ。わたしには井上ひさしが天才であったのか鈍才であったのかは分からないし、知ろうとも思わない。彼の本は幸か不幸か、これまでに「米の話」と「日本語教室」という理屈っぽい、この二冊しか読んでいない。芝居も見ていないし話題になった「吉里吉里人」も古本屋で格安で入手したにはしたのが十行ほど読んで、つまらなくなり、押入れに放り込んだままである。
残念ながら、わたしには井上ひさしの諸本から、彼の知見に感銘をうけたこともなかったし文才を感じたこともない。そこで私なりに、西舘さんのご本を読んだ限りで井上ひさしという敗戦後の日本を駆け抜けた一人の流行作家を総括してみるに、何かといえば、「俺が俺が」とわめきつつ、ときには「誰のおかげでメシを食っている」などと妻子を恫喝して、これを励みに自分もなんとか一旗あげなければと思い込み、ひどく上昇志向にこだわる当時の日本なら、どこにでも転がっていた経済的高度成長期に特有の「愛すべき」普通のおっさんだったということだけは確認できた次第である。