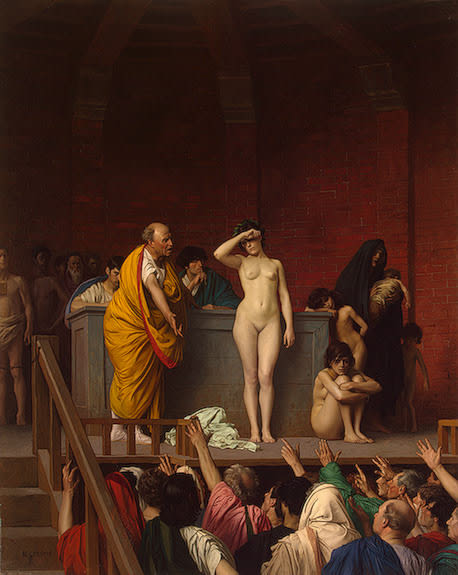 客観的世界モデルのほうは、物質に注目する場面で使う感覚神経系、つまり視覚と聴覚、触覚から構成されている。物質に向けられるこれらの感覚は、他人と共感できる。視覚、聴覚、触覚は、身体の外側にある物質の動きを把握するために発達した感覚システムなので、信号伝達経路も身体の内部感覚とは別になっている。実際、客観的世界モデルは、脳幹や辺縁系に生ずる身体感覚や内部感覚、感情などの情報は使わずに、身体の外側の世界を客観的に表わす情報だけから作られるモデルとなっている。
客観的世界モデルのほうは、物質に注目する場面で使う感覚神経系、つまり視覚と聴覚、触覚から構成されている。物質に向けられるこれらの感覚は、他人と共感できる。視覚、聴覚、触覚は、身体の外側にある物質の動きを把握するために発達した感覚システムなので、信号伝達経路も身体の内部感覚とは別になっている。実際、客観的世界モデルは、脳幹や辺縁系に生ずる身体感覚や内部感覚、感情などの情報は使わずに、身体の外側の世界を客観的に表わす情報だけから作られるモデルとなっている。
客観的世界モデルは、身体内部のことはうまく表せない代わりに、身体外部の物体の運動や変化を表わす場合には完璧です。身体の外側の情報を感知する感覚器官(視覚、聴覚、触覚)を使って、大脳皮質と小脳を使う運動予測シミュレーションを働かせる。過去の整然とした記憶や長期的な将来の予測ができるようになる。実際、この世界モデルは運動の記憶、社会機能、言語機能などの土台になっています。
拙稿の見解では、人間が他人と会話をするときはこの客観的世界モデルを主に使う。そうしないと整然とした分かりやすい話はできません。言語はこの客観的世界モデルを下敷きにして発展した。哲学や科学をするときは、もちろんこのモデルの上で言葉を使っているわけです。
一方、たとえば痛みや恐怖で取り乱して赤子のように泣き叫んだりするときは、自分中心モデルを使っている。こういうときの自分中心的な感情などは、長期的に整然と記憶して適時に想起することがむずかしい。自分中心モデルを使っているときは、たぶん大脳皮質でのシミュレーションをあまり活用していないので、客観的物質世界で使われる運動のイメージや言語につながらず、連想しやすい形で記憶することがむずかしいのでしょう。
拝読ブログ:自己意識の脳
拝読ブログ:微妙な感覚。


















