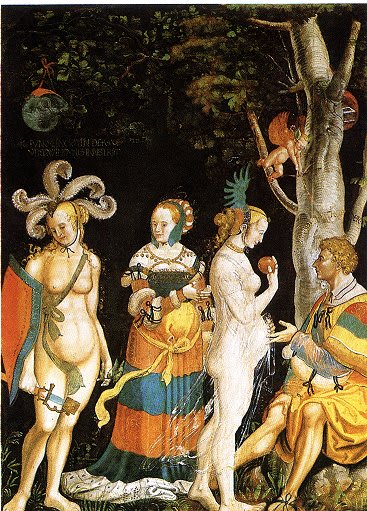脳科学はまだまだという話を長々としてしまいましたが、また、錯覚の話に戻ります。
錯覚は通常、人間の生活に役立ち不可欠なものです。私たち人間は、自分の脳が自動的に作り出す錯覚が映し出している世界を現実と思い込んで、便利に暮らしているといえます。
そもそも物理、化学などの基礎的な科学の実験観測も、脳が作る錯覚にもとづいています。科学者も、測定装置が発生する光エネルギーの変化を写真あるいはデジタルメモリなどに記録し、それを彼または彼女の網膜で受け、脳で変換した錯覚を感知しているわけです。運動シミュレーションを使った錯覚の存在感で得られた空間と時間の感覚にそって、データを観察し理論を作っていきます。科学者が使っている錯覚が現実にうまく対応していなければ、間違った結論が出るだけです。ただ科学者は、同じことを何度も繰り返し理論モデルと照らし合わせながら、慎重に再現性を確認して実験観察を進めます。さらに多数の科学者の共同作業によって、繰りかえし実験や視点の移動、多面的観測事実の統合などを行って錯覚を相殺し、修正し、理論モデルと観測結果を合わせ込んで総合的に判断することで、観察者の作る錯覚から独立した物質に普遍の法則を発見していくわけです。
拝読ブログ:暇人の暇つぶし・おしまい