●危機の時代に弁証法的神学が登場
第1次世界大戦は、ヨーロッパのキリスト教徒が抱いていた希望に満ちた確信を打ち砕いた。たとえば、自由主義神学のハルナックは、神の国は神自身がキリストにおいて建設するものではなく、人間の誠実な努力によってもたらされると楽観的な主張をしていたが、人々は、もはやこうした主張を信じられなくなった。
ドイツの宗教哲学者、ルドルフ・オットーは、大戦中の1917に『聖なるもの』を刊行した。オットーは、神の観念の中心にある「聖なるもの」という言葉を徹底して追求した。そして「聖」の語は、神を示す語としては不十分であるとして、「ヌミノーゼ」という言葉を使用した。ヌミノーゼは、ラテソ語で神性を表すヌーメンに基づく造語である。ヌミノーゼは、人間の理性や概念では理解のできない存在を示唆する。恐るべきもの、超越したもの、神秘であり、しかも、魅せられるものである。オットーによれば、神の合理的な認識はあり得ない。人は、聖なるものを魂の深奥において直観し、感じ取るのみである。
第1次世界大戦の後、ドイツのキリスト教プロテスタンティズムに新たな神学が登場した。それが弁証法神学である。弁証法神学は、ハイデッガーやヤスパースが近代西洋文明の危機を感じ取って思索を進めていた時に現れた危機の時代の神学である。
その神学的な内容に入る前に、弁証法神学が現れるまでの歴史を簡単に振り返ると、18世紀の啓蒙主義の時代には、キリスト教の問題は、理性と信仰の対立だった。カントは、純粋理性と実践理性を区別して、神は純粋理性によって認識することはできず、実践理性の「要請」であると主張した。これによって科学的認識を根拠づけるとともに、信仰の領域を確保した。この一種の二元論に不満を抱く者たちは、18世紀末から19世紀の初めにかけて、カントの批判哲学を超える一元論を生み出そうとした。その一つが、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルらによるドイツ観念論であり、もう一つが、ノバーリス、ヘルダーリンらによるロマン主義だった。
ドイツ観念論はヘーゲルで頂点に達したが、その体系哲学への批判の中から、フォイエルバッハはキリスト教を批判し、唯物論に転じた。マルクスは、フォイエルバッハの説を受けて史的唯物論を説き、キリスト教を含む宗教を否定した。これとは別に、キルケゴールは、ヘーゲルの哲学を批判し、人間的実存の哲学を説いた。
一方、ロマン主義とは、二元論の哲学に対し、二元的なものが現れる以前の根源的なものへの憧憬を表す思想・運動である。そこには、有限なものを超えた永遠への思慕、到達不可能なものへの憧れが見られる。神学におけるロマン主義の代表者が、フリードリヒ・シュライエルマハーである。へーゲルとほぼ同時代を生きたシュライエルマハーは、宗教の本質は神に対する直観と感情であると説いた。自己と対象との対抗関係が統一され合一されるものに対する「絶対的な依存感情」が信仰であると説いた。神との神秘的な結合を強調し、神と人間の直接的な関係を主張した。プロテスタンティズムでは、近代神学の祖とされる。
シュライエルマッハーの神学は、直観と感情を基本とし、体験と価値判断を重視する。彼以後、彼における理性より体験を重んじる側面を継承するか、主観的な価値判断を重んじる側面を継承するかによって、異なる神学の系統が続いた。
体験重視の側面を継承したのが、保守主義の神学である。これには正統主義と敬虔主義が含まれる。保守主義には、ルター、カルヴァン以来の堅固な聖書主義から、歴史的・批評的な立場をある程度受け入れるものまでの幅があった。一方、価値判断重視の側面を継承したのが、自由主義の神学である。シュトラウスによる聖書の批評的研究、リッチェルによる道徳的宗教論、トレルチによる宗教史研究に基づくキリスト教の相対化などが現れた。
20世紀初めのドイツでは、大多数のキリスト者が、宗教改革の教義を保守する正統主義神学の教義を信じていた。ルター、カルヴァンを継承する正統主義神学は、人間の罪を強調し、人間の善を行う自由意思を否定する。これに対し、自由主義神学は、発達を続ける科学の影響を受け、人間の理性を信頼し、自由意志を肯定し、神と人間の質的差異を否定した。また聖書を批評的に分析し、聖書は神から霊感を受けて書かれた書物ではなく、一般の古典と異なるものではないと主張した。そのため、正統主義神学と自由主義神学は、鋭く対立するようになっていた。
こうしたなか1920年代初め、自由主義神学とも正統主義神学とも異なる新しい神学として出現したのが、弁証法神学である。
第1次世界大戦後、敗戦国として混乱の中にあったドイツで、1922年に若手の神学者たちが『時の間』という機関誌を刊行した。カール・バルト、ルドルフ・ブルンナーらが活発に言論活動を行った。ティリヒやブルトマンもその近くにいた。バルトらは、人間の理性への信頼に基づく自由主義神学を批判し、聖書に語られ、宗教改革者が理解したままの「神の言葉の神学」を樹立することを目標とした。神の超越性、人間の罪、神の恵みのみによる救いなどを、従来の正統主義神学とは違って、啓蒙主義以降の近代的視点から捉え直そうとした。
彼らの神学が弁証法神学と呼ばれるようになった。弁証法と言ってもヘーゲル、マルクスの系統の弁証法ではない。神と人間の絶対的な質的差異を強調したキルケゴールの質的弁証法を継承したものである。バルトらは、キルケゴールを再発見し、その実存哲学に啓発を受け、彼らの神学運動の基礎に置いていた。弁証法神学と呼ばれるほか、危機神学・新正統主義神学とも呼ばれる。危機神学とは、大戦後のヨーロッパの危機意識の中から生れたからであり、新正統主義神学とは、宗教改革の神学を忠実に受け継ぐと主張して、既成の正統主義神学を批判したからである。
次回に続く。
第1次世界大戦は、ヨーロッパのキリスト教徒が抱いていた希望に満ちた確信を打ち砕いた。たとえば、自由主義神学のハルナックは、神の国は神自身がキリストにおいて建設するものではなく、人間の誠実な努力によってもたらされると楽観的な主張をしていたが、人々は、もはやこうした主張を信じられなくなった。
ドイツの宗教哲学者、ルドルフ・オットーは、大戦中の1917に『聖なるもの』を刊行した。オットーは、神の観念の中心にある「聖なるもの」という言葉を徹底して追求した。そして「聖」の語は、神を示す語としては不十分であるとして、「ヌミノーゼ」という言葉を使用した。ヌミノーゼは、ラテソ語で神性を表すヌーメンに基づく造語である。ヌミノーゼは、人間の理性や概念では理解のできない存在を示唆する。恐るべきもの、超越したもの、神秘であり、しかも、魅せられるものである。オットーによれば、神の合理的な認識はあり得ない。人は、聖なるものを魂の深奥において直観し、感じ取るのみである。
第1次世界大戦の後、ドイツのキリスト教プロテスタンティズムに新たな神学が登場した。それが弁証法神学である。弁証法神学は、ハイデッガーやヤスパースが近代西洋文明の危機を感じ取って思索を進めていた時に現れた危機の時代の神学である。
その神学的な内容に入る前に、弁証法神学が現れるまでの歴史を簡単に振り返ると、18世紀の啓蒙主義の時代には、キリスト教の問題は、理性と信仰の対立だった。カントは、純粋理性と実践理性を区別して、神は純粋理性によって認識することはできず、実践理性の「要請」であると主張した。これによって科学的認識を根拠づけるとともに、信仰の領域を確保した。この一種の二元論に不満を抱く者たちは、18世紀末から19世紀の初めにかけて、カントの批判哲学を超える一元論を生み出そうとした。その一つが、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルらによるドイツ観念論であり、もう一つが、ノバーリス、ヘルダーリンらによるロマン主義だった。
ドイツ観念論はヘーゲルで頂点に達したが、その体系哲学への批判の中から、フォイエルバッハはキリスト教を批判し、唯物論に転じた。マルクスは、フォイエルバッハの説を受けて史的唯物論を説き、キリスト教を含む宗教を否定した。これとは別に、キルケゴールは、ヘーゲルの哲学を批判し、人間的実存の哲学を説いた。
一方、ロマン主義とは、二元論の哲学に対し、二元的なものが現れる以前の根源的なものへの憧憬を表す思想・運動である。そこには、有限なものを超えた永遠への思慕、到達不可能なものへの憧れが見られる。神学におけるロマン主義の代表者が、フリードリヒ・シュライエルマハーである。へーゲルとほぼ同時代を生きたシュライエルマハーは、宗教の本質は神に対する直観と感情であると説いた。自己と対象との対抗関係が統一され合一されるものに対する「絶対的な依存感情」が信仰であると説いた。神との神秘的な結合を強調し、神と人間の直接的な関係を主張した。プロテスタンティズムでは、近代神学の祖とされる。
シュライエルマッハーの神学は、直観と感情を基本とし、体験と価値判断を重視する。彼以後、彼における理性より体験を重んじる側面を継承するか、主観的な価値判断を重んじる側面を継承するかによって、異なる神学の系統が続いた。
体験重視の側面を継承したのが、保守主義の神学である。これには正統主義と敬虔主義が含まれる。保守主義には、ルター、カルヴァン以来の堅固な聖書主義から、歴史的・批評的な立場をある程度受け入れるものまでの幅があった。一方、価値判断重視の側面を継承したのが、自由主義の神学である。シュトラウスによる聖書の批評的研究、リッチェルによる道徳的宗教論、トレルチによる宗教史研究に基づくキリスト教の相対化などが現れた。
20世紀初めのドイツでは、大多数のキリスト者が、宗教改革の教義を保守する正統主義神学の教義を信じていた。ルター、カルヴァンを継承する正統主義神学は、人間の罪を強調し、人間の善を行う自由意思を否定する。これに対し、自由主義神学は、発達を続ける科学の影響を受け、人間の理性を信頼し、自由意志を肯定し、神と人間の質的差異を否定した。また聖書を批評的に分析し、聖書は神から霊感を受けて書かれた書物ではなく、一般の古典と異なるものではないと主張した。そのため、正統主義神学と自由主義神学は、鋭く対立するようになっていた。
こうしたなか1920年代初め、自由主義神学とも正統主義神学とも異なる新しい神学として出現したのが、弁証法神学である。
第1次世界大戦後、敗戦国として混乱の中にあったドイツで、1922年に若手の神学者たちが『時の間』という機関誌を刊行した。カール・バルト、ルドルフ・ブルンナーらが活発に言論活動を行った。ティリヒやブルトマンもその近くにいた。バルトらは、人間の理性への信頼に基づく自由主義神学を批判し、聖書に語られ、宗教改革者が理解したままの「神の言葉の神学」を樹立することを目標とした。神の超越性、人間の罪、神の恵みのみによる救いなどを、従来の正統主義神学とは違って、啓蒙主義以降の近代的視点から捉え直そうとした。
彼らの神学が弁証法神学と呼ばれるようになった。弁証法と言ってもヘーゲル、マルクスの系統の弁証法ではない。神と人間の絶対的な質的差異を強調したキルケゴールの質的弁証法を継承したものである。バルトらは、キルケゴールを再発見し、その実存哲学に啓発を受け、彼らの神学運動の基礎に置いていた。弁証法神学と呼ばれるほか、危機神学・新正統主義神学とも呼ばれる。危機神学とは、大戦後のヨーロッパの危機意識の中から生れたからであり、新正統主義神学とは、宗教改革の神学を忠実に受け継ぐと主張して、既成の正統主義神学を批判したからである。
次回に続く。










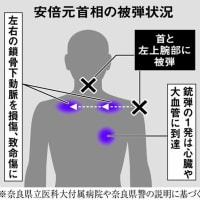









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます