三年生の授業は、俳句から始まります。
あっ、教科書は詩からなんですが、わたしは俳句から始めるのです。その方が、自分としてはスムーズにつながっていくような気がするから。
今年は一年以上前から「取り合わせ」でいきたいと思っていました。ネタもとは夏井いつき「子供たちはいかにして俳句と出会ったか」(創風社)。これがすごいおもしろい本で、国語の教師だった夏井さんの授業を彷彿とさせるのです。
例えば、NHKの子ども番組で「テレビ戦士」に俳句を教える。男子校で句会を開く。俳句による「恋のボクシング」をさせる。
わたしが参考にしたのは、小学生に俳句の基本についてレクチャーする回。有季定形についてわかりやすく教えてくれます。
題材は坪内稔典の「三月の甘納豆のうふふふふ」。
さすがに中学生に甘納豆を食べさせる訳にはいかないので、そこは割愛しましたが。
中七「甘納豆の」を別の食べものに置き換えてみる。「パイナップルの」「五目焼きそば」「甘いはっさく」「しゃきしゃきレタス」「叉焼麺の」といった言葉が出て来る出て来る。
言葉が変わると「三月」とのバランスが崩れてしまうことも理解できます。
で、「春の雲」を使って残り十二音を考えてもらったのです。
その他にも季語当てクイズをはじめ、参考になること満載です。
この句を紹介してから坪内稔典のことが気になって気になって、本も買ったのですが、まだ読んではいません。
ちょっと読み返してみたら、後半で坪内さんのことに結構ふれていたので、また気になりはじめました。
授業だと鑑賞が主で、なかなか俳句実作にはつなげにくいという話題がありました。最近は「句会」をやってみるという部分もあるので、そういう点では実作奨励ができてきているといえるでしょう。こちらがいいと思うような句がなかなか選ばれないこともあるんですけどね。
でも、今でも作者の名前を書かせるようなテストを時々見かけます。国語のテストがクイズみたいなのは、わたしは嫌だな。作者が背後にあるのは作品としてしかたないにしても、もっと言葉の広がりを見たい気がします。
切れ字のもつ広がりから句を読んでほしいという話題もあり、なかなか奥が深いです。まだまだ研究しなくてはなりませんね。
あっ、教科書は詩からなんですが、わたしは俳句から始めるのです。その方が、自分としてはスムーズにつながっていくような気がするから。
今年は一年以上前から「取り合わせ」でいきたいと思っていました。ネタもとは夏井いつき「子供たちはいかにして俳句と出会ったか」(創風社)。これがすごいおもしろい本で、国語の教師だった夏井さんの授業を彷彿とさせるのです。
例えば、NHKの子ども番組で「テレビ戦士」に俳句を教える。男子校で句会を開く。俳句による「恋のボクシング」をさせる。
わたしが参考にしたのは、小学生に俳句の基本についてレクチャーする回。有季定形についてわかりやすく教えてくれます。
題材は坪内稔典の「三月の甘納豆のうふふふふ」。
さすがに中学生に甘納豆を食べさせる訳にはいかないので、そこは割愛しましたが。
中七「甘納豆の」を別の食べものに置き換えてみる。「パイナップルの」「五目焼きそば」「甘いはっさく」「しゃきしゃきレタス」「叉焼麺の」といった言葉が出て来る出て来る。
言葉が変わると「三月」とのバランスが崩れてしまうことも理解できます。
で、「春の雲」を使って残り十二音を考えてもらったのです。
その他にも季語当てクイズをはじめ、参考になること満載です。
この句を紹介してから坪内稔典のことが気になって気になって、本も買ったのですが、まだ読んではいません。
ちょっと読み返してみたら、後半で坪内さんのことに結構ふれていたので、また気になりはじめました。
授業だと鑑賞が主で、なかなか俳句実作にはつなげにくいという話題がありました。最近は「句会」をやってみるという部分もあるので、そういう点では実作奨励ができてきているといえるでしょう。こちらがいいと思うような句がなかなか選ばれないこともあるんですけどね。
でも、今でも作者の名前を書かせるようなテストを時々見かけます。国語のテストがクイズみたいなのは、わたしは嫌だな。作者が背後にあるのは作品としてしかたないにしても、もっと言葉の広がりを見たい気がします。
切れ字のもつ広がりから句を読んでほしいという話題もあり、なかなか奥が深いです。まだまだ研究しなくてはなりませんね。










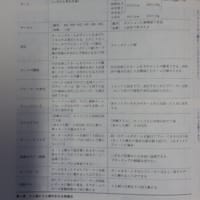

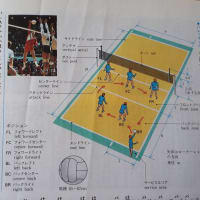

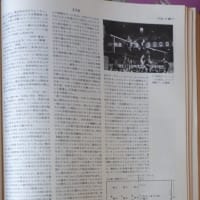

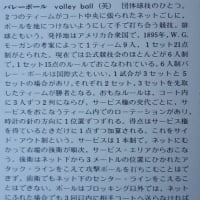

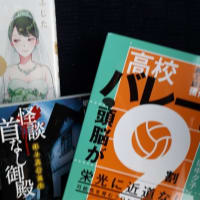
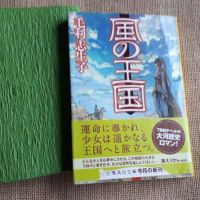
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます