| 毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など |
| てらまち・ねっと |
2005年2月ブログ開始 それから 毎日更新 ランキング 
人気ブログランキングへ
〒501-2112 岐阜県山県市 西深瀬208
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
中日新聞生活面の情報ボードに、2月14日(土)と3月7日(土)に開催する
「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙直前講座」の案内が出ました。 けっこうよく目立つところに、まとまった記事で出ました。 パートナーは、記事を見てのお問い合わせに対応するために、 ノルディックウォーキングはなしにして待機。 なお、パートナーは、あす2月7日(土)は、東京の「都市問題」公開講座に出るので、いちにち不在で、電話に出られませんから、今日金曜日か、日曜日にどうぞ。 (昨日のブログ ⇒ ◆「自治体議会は必要か?」 都市問題公開講座 2月7日/日本プレスセンター) 私は、明日のブログに載せ、10日(火)の新聞折り込みで市内に全戸配布する「新しい風ニュース」の印刷です。 直前講座の主催は、「女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク(む・しネット)」。 2月14日(土)と3月7日(土)、午後1~8時。 記事を読んで、選挙講座に出たいと希望される方は、 ブログ後半の、詳細情報もお読みになってください。 選挙直前講座は、一人でも多くの市民派議員を増やしたいという趣旨で、 4年ごとの統一選の直前に、開催しています。 4年前も中日新聞に案内が掲載されて、お問い合わせが殺到。 立候補者の性別の傾向のとおり、男性が約8割・女性2割。 とはいえ、対象は無党派・市民派に限定していて、 誓約書の提出も義務づけているので、 男性は、保守系や「減税日本」の候補者など条件が合わない方が多くて、 受け入れたのは、女性がほとんどでした。 第一回の開催まであと一週間ですが、できるだけ 受け入れたいと思いますので、出たい人は、 【内容の詳細・タイムテーブル】をお読みになって、お電話ください。 ●人気ブログランキング = 今、1位 人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点情報ボード◇市民派議員になるための選挙直前講座 (2015.2.6 中日新聞) 
|
|
「自治体議会は必要か?」 という明快なテーマでの公開講座がある。
主催は、(公財)後藤・安田記念東京都市研究所(旧 東京市政調査会)。 2月7日(土)13:30~16:30 。 ここに、パートナーがパネリストとして招かれているので、その企画の案内を紹介。 場所は、なんと、日本プレスセンター。 ちょうど、今日が申し込みの締め切り。興味ある方はどうぞ。 ところで、今日は、東京から打ち合わせに来る人がいるので、岐阜で面会、としてある。 ついでに、岐阜市役所にも行ってくる予定。 ●人気ブログランキング = 今、1位 人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点★ 第40回『都市問題』公開講座 
(公財)後藤・安田記念東京都市研究所(旧財団法人東京市政調査会) ホーム  |
|
「転載・転送可/歓迎」「拡散希望」。
このブログへのアクセスで、年末12月ごろから毎日、一番多い分野は、来年の統一地方選の関係のこと。 毎日数百以上の「アクセス・IP」。 だからというわけではないけれど、2月と3月に選挙直前講座を開くので今日は、その内容と参加者募集のお知らせ。 (2014年9月20日ブログ⇒ ◆統一地方選の投票日は「4月12日」「26日」で確定 無党派・市民派に限定することを前提として、自治体選挙の立候補者、および、お知り合いで立候補されようとしている方、などがおみえなら、お知らせいただければ、ありがたいです。 ブログの後半に内容や日程、申し込みのことなどの詳細をまとめますが、まず、概要は次です。 ◇2月14日(土)と3月7日(土) 「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙直前講座」 ◇ 対 象:無党派・市民派の立候補予定者=参加者は所定の誓約書を提出 保守系および政党・組織関係者、政党系会派所属議員は除く ◇ 参加費2万円 (2回通しでの参加が基本) ◇ 主 催:女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク(む・しネット) ◎ 参加を希望される方は、講師の寺町みどり(tel0581-22-4989) まで、まず電話でお問い合わせを。 なお、私たちが10月に出した本は次。 上野千鶴子 プロデュース、寺町みどり・寺町知正共著 2014年10月刊 WAVE出版 『最新版 市民派議員になるための本』-あなたが動けば社会が変わる- 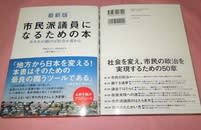 ↑ クリックで拡大 ↑ ★目次=「部・章・節」紹介 ★注文案内はここ ●人気ブログランキング = 今、1位 人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点
|
|
国政選挙の後にはいつも、選挙違反の報道が並ぶ。従来型の買収は相変わらずとして、最近は「電話依頼してもらって、報酬を支払ったことが買収に当たる」という摘発も目立つ。つまり、「有償での選挙の電話」は「買収に当たる」ということが明確になっている。 ともかく、今回は、衆院選の違反摘発としては過去最少だという。 突然の選挙で立候補者が少なかったとか、いろんな面で"準備期間"が短かったから不正の余地もすくなかったとか、そんなことが言われる。 インターネット選挙としてみても、違反の摘発はなかったという。明らかに違反、そんなものもあったけど、ま、・・・・・・・大目に見たのか・・・? ということで、一通り、今回の選挙違反の事例やまとめ的な報道を記録しておく。 ところで、私のブログは、年末年始の休暇期間が、一年でアクセスが一番少ない時期。 それが、今シーズンは違っていた。 gooブログからの昨日15日のアクセス数は「閲覧数 5532」、「訪問者数 1415」 だった。 過去2週間、つまり1月2からのアクセス数は「閲覧数合計 81580」、「訪問者数合計 16553」だった。 日別のグラフやデータの表は、ブログに載せる。 ●人気ブログランキング = 今、1位 人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点gooブログからの通知 「てらまち・ねっと」のアクセスデータ
●石田議員の運動員逮捕=電話依頼に報酬、買収容疑―和歌山県警 [時事通信社]2015.01.12 14:27 昨年12月の衆院選で和歌山2区から当選した自民党の石田真敏議員(62)の選挙運動員が、有権者に電話で投票を依頼した女性らに現金で報酬を渡したとして、県警捜査2課などは12日、公職選挙法違反(買収)容疑で同県海南市幡川、無職追田和之容疑者(74)を逮捕した。容疑を認めているという。 逮捕容疑では、追田容疑者は他の運動員の女性3人と共謀し、選管に届け出ていない海南市など在住の女性6人に対し、有権者に投票依頼の電話をした報酬として、計20万円余りを渡した疑い。 |
| ●維新・升田氏の運動員逮捕 買収疑い 日経 2015/1/7 12:31 昨年12月の衆院選で電話による選挙運動に報酬数十万円を支払ったとして、青森県警は7日までに、農業、吉田俊逸容疑者(64)=同県五所川原市金木町蒔田桑元=ら2人を公選法違反(買収)の疑いで逮捕した。捜査関係者によると、2人はいずれも青森1区から立候補し、比例東北ブロックで復活当選した維新の党、升田世喜男氏の運動員。 ほかに逮捕されたのは無職、渡辺美津江容疑者(50)=青森市三内沢部。 逮捕容疑は、衆院選で升田氏への投票を呼び掛ける電話をかけたことや、今後の選挙運動の報酬として、別の運動員十数人に現金計数十万円を支払った疑い。県警によると、2人はおおむね容疑を認めている。 升田氏は初当選。青森県では衆院選で民主、維新、社民の野党3党が初めて連携し、升田氏は選挙区で当選した自民党候補に3787票差まで迫った。 升田氏の事務所は取材に「逮捕者は選対の役職には就いていない」と説明。「深刻かつ重大に受け止め、捜査の推移を見守り適切に対応する」とのコメントを発表した。〔共同〕 ●<升田氏派選挙違反>公示前も電話作戦か 河北 2015年01月10日 衆院選青森1区を舞台にした升田世喜男氏(維新、比例東北)派の選挙違反事件で、買収に当たるとされる電話作戦が公示前の昨年11月25日から続けられていたことが9日、関係者の話で分かった。公選法で禁じられた事前運動に該当する疑いがあり、青森県警が慎重に調べている。 関係者によると、電話作戦の準備を進めていた農業吉田俊逸容疑者(64)=五所川原市金木町=は11月22日、事前に募った女性らを集め、業務の内容に関する説明会を開いた。電話作戦はその3日後にスタートし、12月2日の公示を経て選挙運動期間最終日の13日まで続けたという。 拠点となった青森、五所川原両市で募った女性は約50人とされ、1人当たり3~5時間のパート形式、時給750円で電話かけをしていたことが関係者の話で分かっている。 電話作戦は19日間に及び、吉田容疑者が自らの資産から工面したとされる原資300万円は、ほぼ使われたとみられる。 公選法によると、選挙運動が認められているのは、立候補者が届け出た日から投票日の前日まで。衆院選では最大12日間の選挙運動ができる。 |
| ●公選法買収容疑、3人逮捕 陣営側「一切関知してない」 朝日 2014年12月17日01時45分 4日投開票の衆院選で、群馬県警は16日、群馬2区に維新の党公認で立候補し、比例区で復活当選した石関貴史氏(42)陣営の運動員とされる3人を公職選挙法違反(買収)の疑いで逮捕し、発表した。警察庁によると、投開票後に警察が摘発した事件のうち、買収容疑での摘発は初めてという。 石関氏の事務所は「一切関知していない。捜査対象者は選対関係者や運動員ではなく、まったく知らない。公選法にのっとって運動しています」とのコメントを出した。一方、県警は3人は石関氏の陣営の運動員だと説明している。 逮捕されたのは、いずれも群馬県伊勢崎市の会社役員本木博幸容疑者(49)と会社役員宮川陽一容疑者(37)、自営業高柳彰寛容疑者(34)。 県警によると、本木容疑者は公示後の12月上旬、宮川、高柳の両容疑者に選挙運動に使う看板を掲示するなどの選挙運動を頼み、報酬としてそれぞれ現金数万円を渡した疑いがある。宮川、高柳の両容疑者はともに受け取った疑いがある。 県警は3人の認否を明らかにしていないが、それぞれ「演説会に多数の有権者を集める目的があった」などと話しているという。3人は看板制作やイベント企画の会社を経営しているという。 ●公選法違反:陣営での立場が焦点 連座制対象か 買収容疑、元秘書送検 /群馬 毎日新聞 2015年01月07日 昨年12月の衆院選を巡る石関貴史氏陣営の公選法違反事件で、県警は6日、公選法違反(運動員買収)容疑で逮捕した石関氏の元秘書で伊勢崎市議の山越清彦容疑者(43)を前橋地検に送検した。石関氏は同日、維新の党の選対委員長を引責辞任した。公選法は選挙運動に使える宣伝物に一定の制限を設け、報酬を支払える対象者も限定している。山越容疑者が陣営内で責任ある立場だった場合、「連座制」で候補者の当選が無効になる可能性があり、県警は山越容疑者の立場を慎重に調べている。 山越容疑者の逮捕容疑は、衆院選公示後の12月上旬、市内の看板製作業、本木博幸容疑者(49)に看板百数十枚の製作と設置を依頼し、現金約50万円を渡したとしている。看板は12月7日にアントニオ猪木参院議員を招いて石関氏を応援する集会を告知するためのもので、現金は看板製作費と設置作業に関わった3人の報酬になったとみられる。県警は容疑者の認否について明らかにしていない。 ◆「運動員買収」とは 公選法は有権者に金品を渡して買収する行為だけでなく、「選挙運動員」の金銭授受も禁じている。選挙運動は無償ボランティアが原則だからだ。しかし、演説会の設営や撤去、運転手など、単純作業を担う人は「労務者」とみなされ、報酬を支払える。県選管は「選管が用意した掲示場にポスターを貼るだけなら労務者。一方、ビラ配布は有権者と直接関わる行為で、看板設置も場所の選定を含めて選挙運動になる」と説明する。本木容疑者と看板を設置したとされる2人の男性は同容疑で逮捕後、処分保留で釈放された。「指示された場所に看板を設置するだけなら単純な労務ともとれるし、選挙運動となるかは個別の判断になる」という。 ◆「連座制」とは 候補者本人が選挙違反に直接関与していなくても、陣営の中心人物が悪質な選挙違反で有罪が確定すれば、「連座制」で失職する可能性が生じる。当選無効だけでなく、5年間は同じ選挙区から立候補できなくなる。 |
| ●投票管理者が選挙運動 公選法違反疑い書類送検 読売 2015年01月14日 昨年12月の衆院選の期間中、岡谷市の投票所で投票管理者を務めていた男(68)が、長野4区で当選した自民党の後藤茂之議員の選挙運動をしたとして、県警捜査2課は13日、この男を公職選挙法違反(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)容疑で長野地検に同日書類送検したと発表した。 発表などによると、男は昨年12月2日の公示後に同市内で行われた後藤議員の応援集会で、4区の有権者に後藤議員への投票を呼びかける発言をした疑い。男は後藤議員の同市の後援会役員で、集会の閉会あいさつで「後藤をよろしく」などと発言したとされる。 男は投票所が置かれた地区の区長。岡谷市では、各投票所の投票事務の責任者として1人ずつ配置する投票管理者に、市選管への推薦に基づき、各区の区長を選任することが多い。選任された間、投票管理者は関係区域内での選挙運動が公選法で禁じられている。 後藤議員の事務所は取材に対し、「後援会役員でありながら投票管理者を引き受けたことに認識の甘さがあった。投票を呼びかけたことが事実なら極めて残念」とコメントした。岡谷市選管の小口佳祐委員長は「大変驚いている。投票管理者の立場に反するような行為があったなら、誠に残念」との談話を出した。 |
|
昨年の5月に第一回を開いて、全5回の「M&T企画/勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座」の最後は、昨日から名古屋で行っている。今日で全日程を終了。
4月に選挙のある人のために、この1月から告示日までの政治活動から、告示日から投票日前日までの選挙運動のすべてのスキルをセッションでお伝えする内容。 その日程と内容を掲載しておく。 今日は、終わったら、そのまま岡山へ。 ●人気ブログランキング = 今、1位 人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点
|
|
毎日新聞の本紙で1月1日から連載「ガラスの天井:女性と政治」「女性の地方政治参画」が続いている。ブログにはその関連の記事の一部を記録しておく。(記事のスタンスには・・・・? もあるけれど)
なお、1月3日の「くらしナビ BOOK」には、パートナーと私が10月に出した本 『最新版市民派議員になるための本 あなたが動けば社会が変わる』の紹介がでていた。 それも併せて紹介するとともに記録。 今日は、ノルディックウォークのあと、今度の土日の選挙講座のレジメづくりと新しい風ニュースの原稿整理。 ●人気ブログランキング = 今、1位 人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点▼『最新版市民派議員になるための本 あなたが動けば社会が変わる』 2015年1月3日 毎日新聞(くらしナビ) BOOK: 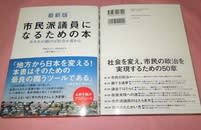 写真のクリックで拡大★目次=「部・章・節」紹介 ★注文案内はここ
|
|
総務省が「衆議院議員総選挙における年代別投票率の推移」というデータ・グラフを出している。
選挙により上下はするけれど、年代別の投票率の最低は「20歳代」「40%程度」、最高は「60歳代」「80%程度」という特徴が一目瞭然。 奇しくも、というべきか、当然というべきか、全体平均は「約60%」。 (ブログ後半に詳しい表を載せた) ともかく、この「60歳代」トップは30年以上前らの連続記録。 政治を左右しているのは高齢世代、ということか。 政治の高齢化は脱したい。 今回の選挙は、いつも以上に「若者の投票」を呼びかける動きが強い印象を受ける。 客観的に投票率を上げることが重要なのは言うまでもない。 だから、このブログでは昨日も整理した「若者」の状況 ⇒ ◆「増え続ける非正規 将来像描けぬ若者ら」/「若者よ、選挙に行こう」「地方が声上げよ」(東京) ●人気ブログランキング = 今、1位 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点
●投票に行こう! “若者たち”の挑戦 テレビ東京 12月8日  衆議院選挙の投開票が14日、今度の日曜日に迫りました。前回の投票率は59.32%でしたが、今回はさらに低くなるのではと懸念されています。特に若い世代の投票率はさらに低調で、20代は2000年以降は50%を下回っています。この流れを変えようと、若者たち自らが選挙や政治に関心を持ってもらおうと独自の取り組みを始めています。 衆議院選挙の投開票が14日、今度の日曜日に迫りました。前回の投票率は59.32%でしたが、今回はさらに低くなるのではと懸念されています。特に若い世代の投票率はさらに低調で、20代は2000年以降は50%を下回っています。この流れを変えようと、若者たち自らが選挙や政治に関心を持ってもらおうと独自の取り組みを始めています。●若者の投票 鍵握る 朝日 2014年12月9日 ●期日前投票 増加傾向だが…  県選挙管理委員会は8日、県内の衆院選の期日前投票者数は7日までで4万6654人に上り、前回2012年の同時期を約13%上回ったと発表した。自民優位の情勢が伝えられる今回の選挙。与野党ともに投票率が選挙結果を左右するとみて神経をとがらせている。 県選挙管理委員会は8日、県内の衆院選の期日前投票者数は7日までで4万6654人に上り、前回2012年の同時期を約13%上回ったと発表した。自民優位の情勢が伝えられる今回の選挙。与野党ともに投票率が選挙結果を左右するとみて神経をとがらせている。期日前投票は、投票日に仕事や旅行などの用事がある人でも投票できるようにする制度。今月3~7日の5日間では、飯舘村が9.85%と最も高く、檜枝岐村(8.18%)、富岡町(7.82%)と続く。都市部では福島市で8968人(3.83%)、郡山市で8812人(3.32%)が投票を済ませている。 ただ、期日前投票の多さが投票率に比例するとは限らない。たとえば2013年参院選では25万172人と、10年参院選を約3万4千人上回ったが、投票率は逆に約7ポイント下がった。 投票率を押し下げているのが、若者の選挙への無関心ぶりだ。県選管が10月の知事選の世代別投票率をまとめたところ、20代の投票率はわずか23.71%。最も高い70代の64.4%を大きく下回った。 若者に衆院選への関心を持ってもらおうと、県選管は動画サイト「ユーチューブ」でCMを配信し、求人情報誌やコンビニのレジ画面に広告を載せている。担当者は「これまでも高校生向けの『模擬投票』などを続けてきた。できることを地道に続ける」と語る。 若者を中心とした無党派層の投票が勝敗を分けかねない―。そんな思惑から、若者の支持の掘り起こしに力を入れる陣営もある。 ある野党候補の陣営はフェイスブックやツイッターといったSNSを積極的に活用しているが、手応えはいま一つ。ホームページに載せている動画の閲覧も「数十件にとどまる」という。「ネットは話題を呼べば一気に拡散する。最後まで何とかおもしろいコンテンツや動画を作るよう、ネット部隊にはっぱをかけている」と力を込める。 有権者の投票態度をめぐっては、00年に森喜朗首相(当時)が「寝てしまってくれればいい」と発言。棄権を期待していると受け取られかねないとして、批判を浴びたことがある。だが自民前職の陣営は「『投票率が下がったほうが有利だべ』という人もいるがそんなことはない。選挙ムードが盛り上がらないと基礎票が落ち込む」と心配する。 ●低だった投票率 今回は回復? カギは若者 テレ朝 (12/09 11:52)  総務省は、7日までに期日前投票をした人が約270万人に上ったと発表しました。投票率に換算すると2.59%で、戦後最低の投票率だった2年前の投票率の時と比べて、わずかな伸びにとどまっています。 総務省は、7日までに期日前投票をした人が約270万人に上ったと発表しました。投票率に換算すると2.59%で、戦後最低の投票率だった2年前の投票率の時と比べて、わずかな伸びにとどまっています。(政治部・千々岩森生記者報告) 投票率について、各党の選挙担当者は、最低だった前回並みに低くなるとみています。 「投票に行かない」人:「全然、よく分からないから行かないです」「親近感がないから遠いです、政治の世界が」 「投票に行く」人:「20歳になったばかりで、選挙権を持っているので。ちゃんと自分の意思を表明しようと思います」 投票率は1996年に初めて6割を切り、「郵政選挙(2005年)」と「政権交代選挙(2009年)」では持ち直したものの、前回の2012年はついに最低を記録しました。ANNの最新の世論調査では、選挙に「必ず行く」と答えた人は77%で、前回の選挙前の調査と同じレベルです。特に20代の投票率は前回37%台と低く、政治が若者向けの政策を後回しにしがちになる要因となっているのが実態です。仮に14日には投票に行かれないとしても、期日前投票であれば9日から13日まで、午前8時半から午後8時まで投票することができます。 ●2014衆院選:大学生が選挙啓発 広告やネットで投票率アップへ /富山 毎日新聞 2014年12月09日 ◇高岡法科大や富山大、学生目線で関心持つきっかけに 県選管は8日、衆院選(14日投開票)の3〜7日の5日間の期日前投票者数を2万2631人と発表した。前回同期比で2875人、14・6%増加した。選挙区別では、2区が同19・9%増で最も増加傾向にある。選挙期間の後半は期日前投票所数も増えるため、県や市町村選管は、場所や投票時間などを広報し、投票率アップに努めている。 ◇ 近年の投票率の減少傾向を受け、県内の学生らの間では、広告やネット動画などで選挙啓発を行う動きが広がりつつある。 高岡法科大の竹田達矢准教授のゼミの学生らは、若い有権者の政治参加意識を高める方法を探ろうと、衆院選富山1区の候補者を取材した動画をフェイスブックのページ「選挙いいね!」で公開した。今年行われた朝日町、入善町の町長選に次いで3回目の取り組みで、国政選挙では初めて。 質問は「他の候補者との違いは」「富山県の魅力」などで、インタビュアーを務めた同大法学部の松本大輝さん(20)は「特定の政策に偏ることなく、学生目線で聞きたい質問にした。『いいね!』を使って広めたい」と話す。 一方、富山大の出版サークル「GROW WORKS(グロウ・ワークス)」は、11月中旬に発行したフリーペーパーの裏表紙用に選挙啓発の広告を制作した。広告では学生に「どんな街に住みたい?」と質問。それぞれの思いをスケッチブックに書いてもらって写真を撮影し、20人分をまとめたデザインとした。 7月にも同様の広告を制作し、今回が2回目。取材に携わった同大経済学部の中田祥平さん(21)は、7月の広告では「あなたが政治家だったら?」の質問に対して、学生は予想以上に回答に時間を要していたが、今回柔らかい内容の質問に工夫すると、すぐに答えが返ってきたと振り返る。中田さんは「柔らかく身近な話の方がイメージしやすいと実感した。政策も分かりやすさを重視して訴えてほしい」と語る。 同サークル代表で同大人文学部の谷内彩夏さん(20)は「取材の時は意図していなかったが、ちょうど総選挙と合う時期になった。目にした学生が選挙に関心を持つきっかけになれば」と話している。【成田有佳】 |
|
今は、衆議院選挙のさなか。私の「新しい風ニュース」は、今朝の新聞各紙の折込で市内(購読)全戸に配布される。
「他の選挙が実施中は、その候補者以外の後援会なども活動休止」という原則があるけど、書き方に気を付ければ、個人版は規制外で自由。 少しそのあたりの整理。 衆議院選挙の始まる前のある記事、「衆院選前哨戦は1日だけ 知事選で『活動制限』 和歌山」(2014年11月26日 朝日)には、 ★《総務省選挙課は「公職選挙法で、街頭演説やポスターの掲示、ビラ配りなどはできない」と説明する》とある。 つまり、知事選の最中の和歌山では「衆議院選挙の予定候補者」の政治団体の活動は大幅に規制される。これは、他の選挙の予定候補者も同様。 基本的ルールなのに、案外知られていない。 たとえば、来年4月の統一地方選、この時も、前半に先立って行われる『知事選・県議選』の最中は、後半に行われる『市町村長・議員選の予定候補者の政治団体の活動』は大幅に制限される。 後述するように、先日出した本にはこのあたりも触れている。 今朝は、インターネットで、分かりやすい選管の解説を探してみた。 新宿区選管の「選挙時における政治活動は何か規制されますか。」が分かりやすい解説だと見た。 他に、都選管の「政治活動の規制 86ページ 『4 選挙期間中の政治活動で何が規制されますか』」も、詳しい。 千曲市選管の「選挙の知識」も、分かりやすくまとめてあった。 それらのリンク・抜粋とともに、規制元の公選法の関連部もブログに抜粋しておく。
★ アマゾン⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』 ★ ブックサービス通販⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』 ところで、今日は、議会の常任委員会の会議。私は所属ではないので傍聴。 ・・・ということで、気温は2度・・ノルディックウォークに出かけよう。 ●人気ブログランキング = 今、1位 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点●衆院選前哨戦は1日だけ 知事選で「活動制限」 和歌山 朝日 2014年11月26日 衆院解散後の3連休、立候補予定者は各地で街頭に立ち、事実上の選挙戦をスタートさせた。だが、和歌山県の予定者たちはこの機会を思うように生かせない。知事選があり、その期間中は政治活動が制限されるからだ。衆院選公示前に活動できる時間は、わずか1日。各陣営とも歯がゆい思いで、訴えを伝えようと知恵を絞る。 衆院解散・総選挙へ 「みなさん、○○候補をよろしくお願いします!」 22日夜、和歌山市内であった知事選候補者の演説会。応援弁士として熱弁を振るう2人の男性がいた。2人とも衆院選の立候補予定者だ。だが、自らのアピールはほとんどせずに席についた。 院選の立候補予定者は投票を呼びかけない限り、公示前でも街頭演説などの政治活動をできる。だが、和歌山県では30日の投開票まで知事選が続く。総務省選挙課は「有権者が知事選と混同する可能性があり、紛らわしい。公職選挙法で、街頭演説やポスターの掲示、ビラ配りなどはできない」と説明する。 知事選2日後の12月2日には衆院選の公示が迫る。公示前の「前哨戦」は1日だけ、ということになる。 和歌山2区で立候補を予定する自民前職、石田真敏氏(62)の陣営は「街頭演説ができず、新たに顔や名前を覚えてもらう機会がない」と困惑する。まずは支持者や推薦団体への地道なあいさつ回りを始めた。 力を入れるのは、知事選で自民が推薦する候補者の応援だ。陣営は「衆院選の話はできないが、『応援』として露出を増やすだけでも意味はある」と期待する。 1区に立候補予定の民主前職、岸本周平氏(58)の陣営も「初めての経験で困っている。これまでの下積みが試される」。駅前やスーパーなど街頭に立つことにこだわってきたが、知事選終了までは街頭演説を封印。かわりに地元のイベントに足を運び、顔を覚えてもらう。知名度には自信があるといい、「どの陣営も活動が制限されるため、むしろ岸本の強さが発揮できるかも」とも話す。2区で立候補予定の維新前職、阪口直人氏(51)の陣営も同様に「割り切って支持者のあいさつ回りに集中する」と話す。3連休は地元の祭りに顔を出し、あとはひたすらあいさつ回りを続けた。 1区から立候補を予定する共産新顔、国重秀明氏(54)は衆院が解散した21日、すぐにJR和歌山駅前に立った。ただし、できるのは行き交う人に手を振るくらい。陣営は「法に触れない限りで、できることをやる」との方針だ。 政党名を記したビラやたすきも用意したが、県選管から法に触れる可能性を指摘された。国重氏は「ややこしいね」と苦笑いする。 公職選挙法は、知事選と衆院選など二つの選挙期間が重複している場合なら、同時期に選挙運動を行うことは可能としている。しかし今回のように選挙が連続するのは極めてまれで、県選管には各陣営から問い合わせが相次いでいるという。 ◇ 和歌山県知事選は、3選をめざす現職の仁坂吉伸氏(64)=自民・民主・公明、社民県連合推薦=、新顔の畑中正好氏(62)=共産推薦=のいずれも無所属の2氏が立候補している。(滝沢文那、加藤美帆)
●政治活動の規制 - 東京都選挙管理委員会 86ページ 「4 選挙期間中の政治活動で何が規制されますか」 ・・・・・・・・・・・・(略)・・・
|
|
昨年2013年7月に解禁されたネット選挙。もともと「インターネットを使っての政治活動(いわゆる後援会活動など)」は以前からできていた。
それに対する「ネット選挙の解禁」とは、おおまかにいうと、「選挙運動期間中にインターネットを使った選挙運動ができること」「基本的に、誰でも、特定候補者の当選のためのインターネット発信ができること」など。 このあたりのこととともに、選挙の候補者や周辺の人たちがどう理解し、どう使えるかは、10月に出した本にも解説している(下記ブログに見出しだけ載せた)。 ・・ということでき、今日のブログは、現在進行形の衆議院選のネット選挙の報道を記録しておく。 (今日は、明日印刷する「新しい風ニュース」の原稿作りをしていてブログが遅くなった・・) ●人気ブログランキング = 今、1位 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点●
● 衆院選 ネットで何ができる? 2014年11月29日 東京新聞 12月2日公示の衆院選では、インターネットを使った選挙運動ができる。国政選挙では昨夏の参院選から導入され、衆院選は初めて。選挙が始まる2日から投票日前日の13日までの選挙期間中に、ネットをどう使えるようになり、何ができないのかをまとめた。 (後藤孝好) Q ネット選挙運動って何かな。 A 候補者や有権者が選挙期間中にホームページ(HP)、ブログを更新したり、交流サイト「フェイスブック」や短文投稿サイト「ツイッター」で発信したりするなど、投票の呼び掛けをできるようになったことだ。インターネットで投票ができるわけではない。投票は従来通り、投票所でしか行えない。 Q 電子メールは使えるの。 A 政党や候補者は、受信に同意している有権者に限って、パソコンや携帯電話の電子メールを送信できる。有権者が電子メールや携帯電話の番号を使うショートメッセージサービス(SMS)を利用することは「悪意のある情報が流される恐れがある」として禁じられている。 Q フェイスブックのメッセージ機能の活用は。 A フェイスブックのほか、ツイッター、無料通信アプリ「LINE(ライン)」などのメッセージ機能は、誰でも利用できる。文章を送るという行為は同じでも、メールはだめだが、メッセージ機能を使うと認められる。分かりにくいから注意が必要だ。 Q ネットで公開されている政党の公約や、候補者のビラは印刷できるの。 A 自分で見るだけなら問題ない。ただ、印刷物を友人に配り歩いたり、大勢の人が見られるように掲示したりすると、公職選挙法違反になる。 Q ネットが得意な高校生に手伝ってもらおうかな。 A 未成年者の選挙運動は公選法で禁止され、ネット上でも認められない。各政党の政策を比較してネット上で紹介するなど、政治活動の範囲なら未成年者でも可能だよ ●衆院選:ネット選挙控えめ 短期決戦で態勢手薄 毎日新聞 2014年12月03日 昨年の参院選に続き、衆院選でも今回からインターネットによる選挙運動が解禁された。与野党は党首や候補者の選挙運動の様子を動画や写真で次々とネットに掲載。衆院解散から公示まで11日しかなかった「短期決戦」で、できるだけ多くの有権者に浸透しようと知恵を絞る。 「いよいよ選挙戦の火蓋(ひぶた)が切られました」。安倍晋三首相は公示日の2日、福島県相馬市で第一声を行うと、さっそく自身のフェイスブック(FB)に書き込んだ。自民党候補への応援メッセージとともに、候補者のホームページ(HP)へのリンクも掲載。賛意や支持を示す「いいね!」はわずか1時間で1500件に上った。 同党は衆院選の特設サイトに、候補者のFBやツイッターを集約して活動を紹介するページを開設。ネット上の書き込みなどから世論の動向を分析する「ソーシャルリスニング」を活用し、有権者の関心に合わせて演説内容を考えるよう各候補にメールで助言している。来春の統一地方選に向けて準備していた「初心者」候補用のネット選挙マニュアルも一部前倒しで使い始めた。 民主党の海江田万里代表は3日午前、福島県いわき市での第一声を紹介した前日に続き、FBで「地方遊説前の時間を利用して、初めて自分のたすきをかけて朝のあいさつをしました」と発信した。同党は自民党同様、政策トピックを各陣営にアドバイスするほか、反響の大きい投稿を例示して候補者全体の力量アップに努めている。 維新の党はツイッターのフォロワー(読者)数が約125万人を誇る橋下徹共同代表や、江田憲司共同代表の発信力を生かす戦術。公明党は無料通信アプリ「LINE」を通じて、支持者を中心に双方向コミュニケーションを図っている。 次世代の党は動画配信に力を入れる。党の新キャラクターが登場する短編アニメを4日に発表予定。若者を中心に情報の拡散を狙う。 参院選でネット選挙を存分に活用し、議席を伸ばした共産党。今回は政策担当の「ゆるキャラ」部員を集めた特設サイト「カクサン部」をリニューアルし、参院選の再現を狙う。 生活の党は小沢一郎代表を前面に出してアピールするほか、ボランティアが撮影した街頭演説の様子などを党のHPに掲載する。社民党は党のHPやFBで、9月に死去した土井たか子名誉党首の動画を掲げ、党勢回復を期す。 ただ、各党には悩みも多い。参院選でネット対策の中心になった当時の衆院議員の多くが今回は自身の選挙にかかりきりになり、「どうしても対策が手薄になる」(自民党関係者)という。民主党の担当者は「参院選時のような態勢は組めない」とこぼす。 参院選で各党が趣向を凝らしたスマートフォン向けアプリの提供も今回は控えめ。参院選で首相をモチーフにしたゲームを始めた自民党は「年末のこの時期にかえって逆効果」と、新作の検討を見送った。【笈田直樹】 ●【栃木】ネット選挙解禁で 各陣営さっそく火花 東京 2014年12月3日 インターネットを使った選挙運動が昨年解禁されてから、初の衆院選となる今回の選挙。県内でも、各陣営は写真や文章を即時に載せられるソーシャルネットワーキングサービス(SNS)サイトを活用し、二日の公示日からネット上でも火花を散らした。 自民前職の一人は二日午後、フェイスブック上で、選挙区内の商店街で有権者と握手を交わしている自身の写真を公開。訪れた商店街の名前も報告し、地域の商店主や買い物客の印象アップを図った。 ある共産新人は、短文投稿サイトのツイッターを積極的に更新。決意表明や公約のポイントを、自身の写真とともに取り上げた。街頭演説にも足を運んでもらおうと、遊説に訪れる場所や時間帯も掲載した。 民主前職の陣営でも、スタッフが出発式会場を駆け巡って写真を撮影し、遊説予定とともにフェイスブック上で紹介。担当者は「若年層に広く訴えかけたいので、ネット対策は重要だと感じている」と意気込む。 各演説会場では、スマートフォンで候補者を撮影し、その場でインターネット上に投稿する支持者の姿も。ある候補者の第一声を聞きに訪れた上三川町の主婦(64)は、写真撮影機能があるタブレット端末を会場に持参。「友人から(候補者を応援するために)ブログに写真を載せたいと言われて」と理由を語り、演説の様子を精力的に撮影していた。 (後藤慎一、大野暢子) ●衆院選:ネット空間、まだ盛り上がらず 琉球新報 2014年12月2日 /(毎日新聞) 今回の衆院選では昨年の参院選に続き「インターネットによる選挙運動」が認められているが、ネット空間は盛り上がりを欠いている。突然の解散で準備不足の陣営も少なくない。とはいえネット社会の傾向で、候補のささいな言動が瞬時に拡散、反響を呼ぶ可能性もあり、専門家は「始まってみないと分からない」と話す。 「衆院はいつクビになるかわからない。常在戦場だ」。首都圏の前職の秘書がため息をついた。来春の統一地方選を前にネット戦略を練り直し、系列の地方議員も含めた後援会名簿の電子化を進めていた。そこへ、突然の解散。「会員向け一斉メール」などの新機軸は夢物語と化した。 相談していたIT会社幹部には、こう忠告された。「ホームページ(HP)を選挙の時しか更新しないようでは、サボっているのが一目瞭然。仮想空間では現実以上の“どぶ板”(こまめな更新)が求められる」 政府のIT政策の総元締め、山口俊一科学技術担当相(衆院前職)すら後手に回っている。公示前日の1日現在で、HPの「活動写真集」の最後の更新は昨年8月。メールマガジン配信は3年前から止まっている。ブログも始めたが、自身の写真を張っただけで投稿ゼロの状態だ。 事務所は「更新が滞り申し訳ない。フェイスブックの利用を検討しています」。だが、山口氏をかたるツイッターが複数出現しており、道のりは険しい。 ネット選挙では、遊説や討論会での不用意な言動が居合わせた人物によってネット上にさらされ、思わぬ反発を招くリスクは消えない。明治学院大の川上和久教授(政治心理学)は「既成メディアは公示後バランスを重視するが、ネットの世界にそんな配慮はない。関心が低いからといって候補や陣営は甘く見ない方がいい」と警告する。【本多健】 ●名入り「たすき」「のぼり」写真つきツイートが続々 違法行為を立候補予定者自らが拡散する異常 www.j-cast 2014/11/28 公示が直前に迫った衆院総選挙は、衆院選としてはインターネットを使った選挙運動が認められる初めての選挙だ。国選選挙としては13年7月の参院選に続いて2度目だが、早くもネット選挙への関心度は「低空飛行」気味だ。 各党の公約や会見でネット選挙について触れることは皆無に近く、解散が急に決まったこともあってネット選挙への対応状況には大きな差はみられない。ネット選挙が誤解されているのか、立候補予定者が違法と疑われる行為を自らツイッターで拡散するというケースも相次いでいる。 75%以上が「ネット上の情報は投票の参考になった」 公職選挙法が2013年4月に改正されたことで、公示後もインターネットを活用した選挙運動ができるようになった。 具体的には、有権者や政党、候補者がフェイスブック、ツイッターをはじめとするソーシャルメディア、動画配信サイトなどを使って特定の候補者への投票呼びかけを行うことができる。これに加えて、フェイスブックやツイッターのメッセージ機能を使って個別に呼びかけることもできる。ただし、「SMTP方式」と呼ばれる通常の電子メールを使えるのは候補者や政党だけで、有権者にはメールは許されていない。さらに、未成年者は引き続き選挙運動ができないため、ツイッターなどで特定候補への投票呼びかけをすると違法になる。 法律が施行されてから時間が経ったこともあって、ネット選挙の認知度はかなり高い。総務省が14年1月に行ったインターネットパネル調査によると、ネット選挙が解禁されたこと自体は83.5%が知っており、「インターネット上の情報は投票に関して参考になったか」という問いには15.8%が「参考になった」、60.7%が「多少は参考になった」と回答。全体の4分の3以上が、解禁にともなってネット上に流れた選挙関連情報を参考にしたことになる。 だが、「ネット選挙で何ができるか」については、ほとんど理解が進んでいない。 「候補者以外の方が『フェイスブックやツイッターを利用して特定候補者への投票を呼びかけること』ができるか」 という問いに対して「できる」と正しく回答した人の割合は、わずか19.1%で、「『インターネットを利用して投票すること』ができるか」という問いに「できない」と正しく答えられた人は、51.9%だった。 共産党はすでにネット番組の放送予定を公表 今回の衆院総選挙は12月2日に公示、14日に投開票される。各党とも準備に時間がなかったからか、ネット戦略に大きな違いはみられない。各党とも(1)ウェブサイトに公約と立候補予定者一覧を載せる(2)遊説の予告や遊説現場の様子を記事仕立てにしてウェブサイトに掲載する(3)フェイスブックやツイッターにサイトの記事や会見動画のURLを貼って拡散する、といった点でほぼ共通しており、13年夏の参院選から大きな変化はない。 そんな中でも、公明党はウェブサイトに「何のための解散か」と題したコーナーを設けてQ&A形式で解散の「大義」について説明するなど、独自の工夫がみられる。動画で一方先を行くのが共産党で、生放送番組「生放送!とことん共産党」の選挙期間の放送予定もすでに公表している。 ツイッターの利用方法にも微妙な違いが見られる。自民、公明の与党はウェブサイトの更新情報や遊説スケジュールが中心だが、民主、次世代、社民、生活などの野党は、立候補予定者などのツイートを党の公式アカウントがリツイート(転送)して、発信する情報の幅に広がりが出るように工夫している。 名前入りのたすきを付けた写真とともに「どうか国会に送ってください」 ただ、こうした活用法が逆に足をひっぱりかねない事例も確認されている。例えば野党の首都圏の立候補予定者は11月25日朝、本人の名前入りの「たすき」と「のぼり」が写った写真とともに、 「さぁー!今日も頑張ります!!安倍暴走政治に正面対決!」 とツイート。九州地区の野党立候補予定者も11月26日、名前入りのたすきを付けた写真とともに 「どうか国会に送ってください」 などとツイートした。 公示前に行う「政治活動」で、候補者名や政党名を入れた「のぼり」、プラカード、たすき、腕章などを使うと公職選挙法に違反するとされる。当然、これらの行為はネット選挙が解禁されてもされなくても違法だ。だが、公職選挙法があまりにも理解されていないからか、ネット選挙解禁にともなって、違法だと疑われる行為を立候補予定者自らが拡散するという奇妙な状況が起きている。 |
|
昨日から、名古屋で「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」を開催中。
テーマは「勝つ選挙をイメージする~政治活動は本番!選挙運動への準備」。 10月に『最新版 市民派議員になるための本』を刊行したので、選挙の基本のノウハウはこの内容に沿ってすすめ、さらに、参加者に提出したもらった課題を元に、それぞれの個別の選挙のすすめかたをアドバイス。 昨夜の最終パートでは、「リーフレット」や「公選ハガキ」、配布しているニュースなどを参加者ごとに掲示して、「その情報をもとにして」どの人に託すかの「模擬投票」も実施。 今回は、連続講座の4回目で、次回1月10日11日の第5回は最終回となる。 年間の連続講座が終了すると、統一選まで4か月あるので、「遅れてきた人のための市民型選挙」の講座を企画する予定。 ●人気ブログランキング = 今、2位 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点第4回「勝てる選挙~市民派議員になるための選挙講座2014」 「勝つ選挙をイメージする~政治活動は本番!選挙運動への準備」 日時:2014年 11月22日(土)~23日(日) 【内容およびスケジュール】 11月22日(土) 13:00~ 開会 参加者プレゼンテーション(ひとり1分×5人) テーマ:『最新版 市民派議員になるための本』を読んで・・・ 《セッションB》 「勝つ選挙をイメージする~選挙運動への準備」 1)公選法を熟知して、選挙違反をしないきれいな選挙を 2)いよいよ告示日~選挙運動(投票日まで)の流れを理解する 3)政治活動のスケジュール表をつくる/カレンダーに記入/レクチャー 【課題-3】 選挙本番までの工程表 4)当選するために必要な要素~現状と目標をチャートに書き込む ◇レーダーチャートを活用して当選する 【課題】 8軸レーダーチャートの記入 《セッションC》 「書きことばのメッセージを届ける~基本は政策・リーフレット」 1)リーフレットの最終検討 【課題】「リーフレットをつくる」 2)ニュースを作って、リーフレットとセットにする 【課題-7】 前回から現時点までのニュース(配布物) 3)リーフレットとニュースを届ける → 印刷は、どこで何枚つくるのか? → 使い方の制限は→あなたは、いつ、どこで、だれに、どのように配るのか ◇ワークショップ:リーフレットのくばり方 4)公選ハガキのつくりかた ◇公選ハガキのポイントと留意点 【課題】「公選ハガキをつくる」 5)公選ハガキの使い方のじっさい あなたは公選ハガキを何枚つくるのか/拡げ方のイメージ 6)webページ、ブログの使い方のじっさい ○インターネットの利用の範囲と限度 7)勝つ選挙をイメージする~どこに重点を置くのか ◇模擬投票 ~ リーフ、ハガキ、ニュースを元に投票 ◇個別の選挙の状況に対応したアドバイス テーマ: 「わたしのやりたい市民型選挙」 11月23日(日) 《セッションD》 テーマ:話し言葉でメッセージを届ける ~ 選挙運動・政治活動 1)話し言葉の基本とコツ/街頭演説のノウハウ、スキル ○街頭演説は何のためにするのか/ノウハウ、スキル/選挙運動・政治活動 ○「連呼」とはなにか/政策連呼のじっさい 2)街頭演説のじっさい 【課題】 1.告示日の街頭演説(3分) 2.スタンスと具体的な政策を入れた内容の演説 3)政治活動、選挙運動でのマイクの使い方、車のまわし方 ○マイク、拡声器の使い方の注意事項 ○ドライバーの注意事項、車を止める場所とタイミング ○選挙カーはベストで使う/メンテナンスは重要 《第4回のまとめ》 1)候補者の現状認識および講師の評価 2)第4回の選挙講座に参加して~選挙にむけての決意 3)第5回の内容予告と課題の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 午後 【オプション】わたしが選挙でかかえる問題 |
|
今日16日は、今年最注目の自治体選挙である「沖縄県知事選挙」の投票日。
極めた特殊な組み合わせや支援体制の中で、県民の皆さんの気持ちは固まっていたように見受ける。すでに、"ダブルスコア"との予測もある。・・が、油断は禁物。 (関連)11月10日ブログ ⇒ ◆沖縄県知事選/翁長氏が先行、追う現職・仲井真氏/「辺野古推進「不支持」7割 政府不信、鮮明に (10月30日 ⇒ ◆知事選4氏が立候補 辺野古争点に論戦/自公にすきま風 「辺野古」巡り 衆院選協力に影も)。 とりあえずは、選管が出している「各候補の選挙公報」にリンクし、もし選管が後日データをインターネットから落としてしまっても良いように、ブログに記録もしておく。あと、選管の開票速報のページはまだ動いていないので、場所だけ確認しておいて報道のいくつかをブログに記録しておく。 ●人気ブログランキング = 今、2位 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点
●沖縄県知事選、16日投開票 NETIB-NEWS(ネットアイビーニュース) 2014年11月14日15:31  注目の沖縄県知事選挙が16日、投開票を迎える。 注目の沖縄県知事選挙が16日、投開票を迎える。4人の候補者が争うことになった選挙戦は、事実上現職仲井眞弘多氏と前那覇市長、翁長雄志氏の一騎打ちとなる展開。報道各社の選挙情勢調査では、オール沖縄を旗印に掲げた翁長氏が優勢のまま、最終日に突入しそうな状況だ。 争点はひとつ。米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古への移設を認めるか否か。今年1月の名護市長選に続き、移設反対派の翁長氏が勝利を収めれば、安倍政権の進める辺野古移設に影響が出るのは必至。確実となった総選挙で自民党への逆風の要素になることも予想される。 知事選立候補者は次のとおり。 ■立候補者(届け出順。敬称略。いずれも無所属) 下地幹郎(53) 新 前政党そうぞう代表 喜納昌吉(66)新 前民主党沖縄県総支部連合会代表 翁長雄志(63) 新(沖縄連合推薦)前那覇市長 仲井眞弘多(75)現 現職沖縄県知事(2期) ●沖縄知事選焦点:米軍基地問題、異例の注目度 沖縄タイムス 2014年11月16日 06:55 きょう投開票される沖縄県知事選は「基地問題」への注目度が近年の県内主要選挙と比較しても異例の高さとなり、4候補ともに米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設への対応を政策の中心に据えて舌戦を展開した。普天間問題の当事者である名護市でのことし1月の市長選が辺野古賛否に対する市民投票の意味合いを持ったのと同様に、知事選の結果は県民による辺野古移設の審判となる。 普天間問題が最大争点であることは政府と与党自民党の対応を見ても明らかだ。菅義偉官房長官はことし9月に普天間問題について「過去の問題だと思っている」と発言したものの、選挙戦では菅氏本人を含め閣僚や党幹部が連日沖縄入りし、「普天間問題の解決のメドを付ける」とする現職を応援した。政府にとって、辺野古で進める移設作業を左右する選挙と位置付けていることが浮き彫りとなった。 今回の知事選では辺野古移設をめぐる保守分裂や、保守・革新の枠組みを超えた勢力の誕生など県内政局の変化も特徴だ。同時に、沖縄タイムスと朝日新聞社、琉球朝日放送(QAB)が実施した世論調査では政党支持層は3割にとどまり、無党派層が7割となり、前回の10年知事選での6割から増加したのも特筆すべき事項だ。 背景には、2009年の政権交代で普天間について「最低でも県外」とした民主党政権の辺野古回帰や、一時は県外を掲げた自民党県連の12年末の辺野古容認などによる政治不信があるとみられる。 調査では無党派層が重視する政策も基地問題が約半数を占めた。有権者の“政治離れ”に歯止めをかける意味でも、各候補者には当選後の公約の堅持、政府には選挙で示された結果を受け止めた普天間問題への対応が迫られる。 当然、基地問題だけでなく各候補者の経済、子育て、福祉など生活につながる政策への期待も有権者の一票に込められる。16日の投開票で県政のかじ取りを託される候補者は政策実現に向けた努力も求められる。(選挙取材班・銘苅一哲) ●<社説>きょう知事選 後世に恥じぬ選択を 自己決定権 内外に示そう 琉球新報 2014年11月16日 第12回沖縄県知事選挙がきょう16日、投開票される。12回目だが、単なる繰り返しでない特別な意味があることは周知の通りだ。県内だけでなく全国的、国際的にも高い関心を集めている。 それだけではない。この1年の動きを考えれば、この選挙では、沖縄の土地や海、空の使い道について、われわれに決定権、すなわち自己決定権があるか、適切な判断ができるか否かが問われている。1968年の主席公選にも匹敵する歴史に刻まれる選挙といえる。国際社会にも、沖縄の先人にも後世にも恥じない選択ができるか。考え抜いて1票を投じたい。 明確な争点 今選挙は無所属新人で元郵政民営化担当相の下地幹郎氏(53)、無所属新人で元参院議員の喜納昌吉氏(66)、無所属新人で前那覇市長の翁長雄志氏(64)、3選を目指す現職の仲井真弘多氏(75)=自民、次世代の党推薦=の4人の争いだ。 特筆すべきは、県民世論を二分する課題について、各候補の主張がはっきり分かれていることだ。近年の知事選は各候補の主張が似た言い回しになり、争点が見えにくくなることが多かった。特に基地問題はそうだ。今回は違う。 米軍普天間飛行場の移設については下地氏が「県民投票の結果に従う」と打ち出し、喜納氏は埋め立て承認の取り消しと嘉手納基地暫定統合を訴える。翁長氏は県内移設断念を掲げて承認取り消しを示唆、仲井真氏は「危険除去が最優先」と移設推進の姿勢を示す。 東村高江の米軍ヘリパッド建設についても下地氏は容認、喜納、翁長の両氏は反対、仲井真氏は「どちらとも言えない」だ。垂直離着陸輸送機MV22オス プレイについては喜納、翁長、仲井真の3氏が配備撤回を求め、下地氏は配備の可否を明らかにせず、訓練削減の方向性は他と一致する。 カジノをめぐっても違いは歴然としている。下地氏は「長所・短所の議論を深めて判断する」とし、喜納氏は「入場者の富裕層限定」を条件に賛成する。翁長氏はギャンブル依存などの悪影響を懸念し反対、仲井真氏は「県民合意」を条件に賛成する。 いずれも沖縄の将来を大きく左右する問題だ。各氏の主張の是非をしっかり吟味し、選択したい。 子育て・教育は各氏が力点を置く。主張は似通うが、若干の違いはある。例えば子ども医療費の無料化や制度見直し、教育費の減免などだ。どの主張に妥当性があるか、財源も含めた実現可能性があるか、見極める必要があろう。 争点の重み 知事選の投票率は上昇・低下を繰り返しつつ、長期的には緩やかに低下してきた。 だが米軍統治下にあった47年前まで、われわれには住民代表を選ぶ権利すらなかった。沖縄の住民が主体的に行政権を行使し、意思を表明できるこの権利は、先人が血のにじむ思いで勝ち取った権利であることを忘れてはならない。 琉球新報社と沖縄テレビ放送が8、9の両日行った世論調査では選挙に「大いに関心」「ある程度関心」と答えた人は91・4%に上った。特に若年層で関心度は急速に高まっている。この選挙を投票率反転上昇の契機としたい。 近年、投票率が下降したのは、主権者であることを実感できないのが原因だろう。「政治はどうせ改善しない」「誰に投票しても同じ」という諦めが投票所から足を遠のかせているのだ。その意味で、政治家が公約を軽々と破ることの悪影響は甚大だ。 だが候補者が公約を示し、有権者が投票で公約を取捨選択することは民主主義の根本である。その重みをあらためてかみしめたい。 今選挙が内外の関心を集めるということは、沖縄の意思表示の国際的な影響力を物語っている。実は主権者たるに十分な力を持っているのだ。沖縄には揺るがぬ自己決定権があり、適切な判断ができるということを、内外に示そう。 |
|
沖縄県知事選は、10月30日に始まった(関連エントリー ⇒ ◆知事選4氏が立候補 辺野古争点に論戦/自公にすきま風 「辺野古」巡り 衆院選協力に影も)。
時期が中盤ということで、報道各社の世論調査結果が出されている。 その見出しを並べるだけでも、状況は明らか。 《「辺野古推進「不支持」7割 政府不信、鮮明に》(共同通信)、《翁長氏が先行…追う現職・仲井真氏》(読売)、《翁長氏優位 仲井真氏追う 中盤情勢》(沖縄タイムス)、《翁長氏が優位》(朝日)、《翁長氏リード、仲井真氏追う》(日経)、《あと1週間、保守分裂 中央とのねじれも》(TBS) 安倍政権は、今年、滋賀県知事選で敗れ、福島は保守系候補を降ろして民主・野党系候補に相乗りして"負け逃れ"。 今年一番注目の沖縄知事選は、先の通りの情勢。 国会で、圧倒的多数をとったけれど、国民レベル、民意レベルでは、決して多数ではないことの証の一つ、か。 しかも、16日の知事選の投票と併せて行われる那覇市長選は昨日告示。 構図は、知事選とぴったり連携した候補者。 沖縄タイムスの社説が沖縄の歴史と今回の選挙を端的にまとめていた。 ★《復帰後、那覇市政の舵(かじ)を取ってきたのは、革新系の平良良松氏、続いて同じく革新系の親泊康晴氏、その後、保守系の翁長雄志氏だった。それぞれが4期と長きにわたって県都の顔となった。》 さらにまとめると、 ★《前副市長の城間幹子氏・・支持するのは市議会保守系の新風会と共産、社民、社大などの各党。翁長氏の後継》 ★《前副知事の与世田兼稔氏・・推薦するのは自民、公明の両党。仲井真弘多知事側が擁立》 投票日が一緒、今後の一週間の運動は、いっそう 知事選と市長選の候補の連動が組まれるのだろうから、有権者の動向は想像に難くない。 かつての政権交代もローカルの足元から崩れていったから、その流れと見たい。 なお、今日は、桑名市の知人の選挙に出かける。 その前に、市役所に情報公開請求書を出していく予定。 先週の6日に一案件について情報公開請求したけれど、今日は5件まとめて請求する。もちろん、分野は、それぞれ全く別のこと。 ところで、私のブログは、土日のアクセスはちょっと少なくなる傾向があるものの、ここのところ安定的に向上していると認識できる。 gooブログが通知してきた記録から。 【過去一週間の「閲覧」と「訪問」の記録の表】 左が「閲覧」、右が「訪問」  【過去一週間の「閲覧」と「訪問」の記録を図】 上が「閲覧」、下が「訪問」。 週間の最多の『5日』にカーソルを置くと数字も出てくる。  ●人気ブログランキング = 今、2位 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点
|
|
昨日と今日は、山県市の議会運営委員会の視察・研修で出張。私たちの議会運営委員会は、(自治体合併して11年)今までは外部への視察・研修は行っていなかったけれど、今年は研修することになった。内容についての起案を私が任されたので、少し考えてみた。
議会改革に関しては、遅まきながら、山県市議会は2年半前から議会改革特別委員会を設置して、いろいろと検討を進めている。初年度は多治見市議会、鳥羽市議会などへも研修に出かけた。今年は、日経グローカルの直近版で、改革度4位といわれる上越市議会、同じく改革度3位といわれる高山市議会にも出かけた。それぞれ、意義深かった。 ・・ともかく、議会運営委員会の改革には何が必要なのか・・思案し、知人とも話したりして、「議会運営委員会の改革には議会事務局改革も重要なポイントの一つではないか」との観点に至った。実際、議会改革の進んでいるところは、議会事務局もしっかりしているとの印象は強く受けている。 そこで、 議会事務局研究会 のことを思いついた。 ちょうど、以前、自治ネットで三重県議会議長に来ていただいて公開講座を開いたとき、終わった後、ロビーで少しだけ話したことがあった高沖氏はその会の共同代表。先の知人に仲介を頼んで、お話しすることができた。 ★ 公開講座/2010年2月13日(土)/テーマ・「三重県議会の議会改革」/三重県議会議長 三谷哲央氏 - 無党派市民派・自治体議員と市民のネットワーク (自治ネット) ★ 堺市議会のデータ/高沖秀宣氏プロフィール 研修の受け入れを内諾頂いたので、当然ながら、あとはこちらの議会事務局に正式に依頼・調整を進めてもらった。 もちろん、改革度1位として注目される四日市市議会、そして、日本の議会改革のリード役として走ってきた三重県議会(の担い手の議会事務局)、この2か所も視察・研修先として決まった。 ・・ということで、昨日は市役所7時発で、(午前中)四日市市議会、(午後)三重県議会、今日(午前中)高沖氏(三重県地方自治研究センター)でみっちりと研修。 研修先のそれぞれの関連データの一部を以下のブログにしておく。 研修の内容のことはまた改めて・・・ なお、昨日、三重県議会の説明の後、最後に、1階にある議会図書室も見せていただいた。以前よく調べに通っていた岐阜県議会の図書室とは違い、明るくて、しかもたくさんの本があって驚いた。・・職員の方から「寺町さんですか」と声をかけられて「はい」と答えたら、「注文していた本が、ちょうど今日届きました」とのこと。 つれあいと書いた本、『最新版 市民派議員になるための本』がここにも置いていただけるのかと、嬉しかった。 (★ アマゾン⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』 ★ ブックサービス通販⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』) ●人気ブログランキング = 今、2位 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←← ★パソコンは こちらをクリックしてください →→  ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点
|
| « 前ページ | 次ページ » |