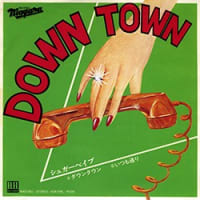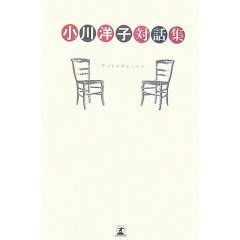
幻冬舎から発行された「小川洋子対話集」に佐野元春との対話が収録されている。二人の対談といえば、2005年1月21日の朝日新聞夕刊(Culture & Entertainment欄「ARTIST MEETS ARTIST」)に掲載されたことがあった。今回の対談はその時と同じ「言葉を探して」という表題だったが内容は異なっている。語りおろしだそうだ。
アルバム『VISITORS』(1984年)の話が出てくる。小川洋子と佐野元春の対話を読んでいて、僕はいつしかその会話に加わっていた。
はじめてアルバムの中の曲を聴いたのはラジオからだった。先行シングルの「Tonight」だ。曲を聴いてニューヨークの風景が目の前に広がった。僕はいつ気がついたのだろう? この曲の主題が"No more pain tonight"だということに。賢明なリスナーならこの曲を聴いて変化に気が付いたはずだ。
アルバム『VISITORS』リリース時に、Motoharu Radio Showで、一ヶ月に渡って4人の音楽評論家を招き、『VISITORS』をそれぞれの視点から批評してもらうという試みが行われた。3週目に出演した萩原健太のクリティクスが強く印象に残っている。それは、佐野元春は一人称で歌うことが少なかったのに、いきなり"オレを壊してほしい"(「Wild On The Street」)って出てきて驚いた、と指摘したからだ。
僕はそれまで佐野元春のソングライティングに関してまともに考えた事などなかった。確かに検証してみれば、一人称が出てくる楽曲を簡単に思い出すことができない。「Please Don't Tell Me A Lie」や「君をさがしている(朝が来るまで)」くらいだろうか。そんなふうに、佐野元春のソングライティングを分析した萩原健太に、僕は一目置いた。あとから聞いた話では、この時の放送が初ラジオ出演だったらしい。
『VISITORS』はヒップホップをいち早く導入したアルバムだとか、今聴けばあれはファンク・ロックだとか、サウンド面で語られることが多いけれど、言葉に特化したアルバムだと僕は思う。
小川洋子は2005年の「THE SUN TOUR」神戸国際会館こくさいホールの公演を見に行ったという。その日は僕も神戸にライヴを聴きに行っていた。震災から10年目ということで、僕は友人とライヴの前に神戸の街を歩いた。そのことはブログに書いている。こことこことここだ。
そんな午後の時間があったからなのか、僕はいつもと違う気持ちになってライヴを見ていた。「あの日の朝に亡くなった人の中に佐野元春のファンもいたのだろうな」と考えて神妙な気持ちになっていた。彼らはこの会場のどこかにいるのかもしれないと思って会場を見渡したりした。
神戸国際会館こくさいホールで「太陽」を聴いた時のことを、「佐野さんが私の体を通して、誰かここに来ていない人に向かって歌われているような、不思議な感覚に陥った」と小川洋子は話している。それまで暗かったステージの背景が開いて、白い光が差し込んだ時のことだったという。さすがに小説家だと僕は思った。そこの部分はもう彼女の語り口で物語になっているような気がしたから。
この対話は昨年『THE SINGLES』がリリースされる直前に行われたようだ。シングルの「Down Town Boy」に関する話題があった。そのレコーディングの日は大雨でスタジオは湿気ていたという。楽器に湿気は大敵でギターもドラムも音が鳴らなかったのだそうだ。レコーディングの時間はその日だけしかなく、「音に妥協してリリースした」と佐野元春はずっと思っていた。だからアルバムではリテイクし、新しいアレンジで仕上げた。しばらくしてファンから手紙が来て「『Down Town Boy』はシングル・ヴァージョンのほうが演奏も歌も優れている」と指摘されたことがあったという。そこで聴き直してみると、確かに気持ちの入り方といったものはシングル・ヴァージョンのほうが数段上だった。
小川洋子はその話を聞いて「そこで雨が降ったことはよきことだったんですね」と言った。佐野元春はあまりにも若かったので気づかなかったと言ってるのだが、「雨」に注目するあたりは小説家ならではの視点だな、と僕は感じた。それがとても興味深かった。