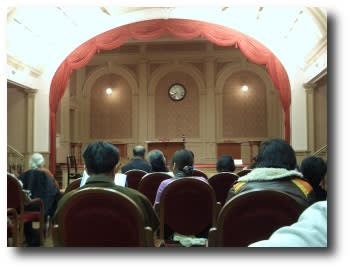規模の大小はありますが、オーケストラによる管弦楽作品をCD等で続けて聴いていると、ピアノソナタなどの独奏曲や室内楽などを聴きたくなります。反対に、室内楽や歌曲ばかりを続けて聴いていると、大編成のシンフォニーやオペラを聴いてみたくなります。感覚の楽しみはかなりわがままで、昔の王侯貴族に仕えたお抱え楽人たちも、ずいぶん苦労したことでしょう。幸いに、現代ではCD/DVDなどというものがあり、棚中よりあれこれ選び出しながら、気ままに音楽を楽しむことができます。
では、実演ではどうか?
昭和48(1973)年に初版が刊行された、大木正興著『室内楽のたのしみ』(音楽之友社)によれば、地方の音楽鑑賞組織や文化活動団体によって、著明な演奏家を招いて室内楽の演奏会がしばしば行われるものの、それは経費のかかるオーケストラの演奏会のかわりに安上がりの代用品として行われるだけにすぎない、という厳しい指摘がありました。もちろん、長年室内楽の振興を願って活動した著者の意図するところは、代用品としてではなく、室内楽の独自の魅力と価値を認めてほしい、ということなのですが、では本書が書かれてから36年後、平成21(2009)年の今日の状況はどうなのだろうか。
幸いなことに当地山形には、村川千秋氏が中心となって結成したプロ・オーケストラである山形交響楽団があり、若い音楽監督を迎え、意欲的に活動しております。また、山響団員を中心として結成された常設のカルテットである山形弦楽四重奏団が、ハイドンの弦楽四重奏曲全曲演奏という目標をかかげ、年四回のペースで定期演奏会を行うなどの活動を続けています。文翔館議場ホールという文化財の建物の中で行われる演奏会に集まる聴衆は、人口20万人規模の地方都市において、コンスタントに80人程度を集めており、単純に人口比で言えば、100万都市なら400人、1000万都市なら4000人規模の聴衆に相当する比率となっています。
そのほかにも、定期的ではありませんが、管楽器を含むさまざまな形の室内楽アンサンブルが演奏会を開くなど、室内楽の演奏会が一定のレベルで成り立っているようです。
私を含め、聴衆はオーケストラ音楽の代用品として室内楽演奏会に足を運んでいるわけではないでしょう。それなら山響の演奏会に行けばよいのですから。実際は、オーケストラの演奏会を楽しみつつ、室内楽演奏会をも楽しんでいるのだと思います。地元にオーケストラがあってこそ、室内楽も定着することができる。その見本のような都市の姿です。その意味では、人口規模は小さいですが、実は魅力的な「音楽都市・山形」なのかもしれません。
では、実演ではどうか?
昭和48(1973)年に初版が刊行された、大木正興著『室内楽のたのしみ』(音楽之友社)によれば、地方の音楽鑑賞組織や文化活動団体によって、著明な演奏家を招いて室内楽の演奏会がしばしば行われるものの、それは経費のかかるオーケストラの演奏会のかわりに安上がりの代用品として行われるだけにすぎない、という厳しい指摘がありました。もちろん、長年室内楽の振興を願って活動した著者の意図するところは、代用品としてではなく、室内楽の独自の魅力と価値を認めてほしい、ということなのですが、では本書が書かれてから36年後、平成21(2009)年の今日の状況はどうなのだろうか。
幸いなことに当地山形には、村川千秋氏が中心となって結成したプロ・オーケストラである山形交響楽団があり、若い音楽監督を迎え、意欲的に活動しております。また、山響団員を中心として結成された常設のカルテットである山形弦楽四重奏団が、ハイドンの弦楽四重奏曲全曲演奏という目標をかかげ、年四回のペースで定期演奏会を行うなどの活動を続けています。文翔館議場ホールという文化財の建物の中で行われる演奏会に集まる聴衆は、人口20万人規模の地方都市において、コンスタントに80人程度を集めており、単純に人口比で言えば、100万都市なら400人、1000万都市なら4000人規模の聴衆に相当する比率となっています。
そのほかにも、定期的ではありませんが、管楽器を含むさまざまな形の室内楽アンサンブルが演奏会を開くなど、室内楽の演奏会が一定のレベルで成り立っているようです。
私を含め、聴衆はオーケストラ音楽の代用品として室内楽演奏会に足を運んでいるわけではないでしょう。それなら山響の演奏会に行けばよいのですから。実際は、オーケストラの演奏会を楽しみつつ、室内楽演奏会をも楽しんでいるのだと思います。地元にオーケストラがあってこそ、室内楽も定着することができる。その見本のような都市の姿です。その意味では、人口規模は小さいですが、実は魅力的な「音楽都市・山形」なのかもしれません。