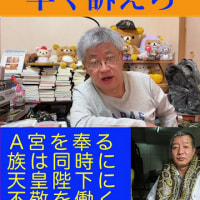下は、ごくごく若い頃、書いた一文にござるが、その文章の拙いことといったら、恥ずかしくて穴があったら入りたいと思う一面、「平家物語」とは、一人の知識人が書き記した文書ではなく、地方地方の職人、名主また語り部どもが総動員されて、成り立った一書の物語であるとの結論は、取り下げるつもりは毛頭ないのであったのであったのだった。
@@@@@@@@@@@@@@
文体は精神のリズムであると申していたのが、小説の神様としてあがめられた志賀直哉その人でしたが、この説は、とてもよく分かります。知識とかボキャブラリーの質量から推し量ってみる傾向が強い今日この頃の国語教育の現場模様ですが、知識と文体は別腹、概念違いの愚の骨頂と申せましょう。よって田舎者には田舎者なりのリズムがあり、その心の鼓動に身を打ち負かせておくなれば、それが文体として形成されてくるに違いありません。そのよき例文を下に記しておきました。
私は、鎌倉後期あたりに、自分の文体の底流と奥義を求めて、この暑さの中、しきりにあえいでいるところなり。私の知る限りでは「平家物語」と「梁塵秘抄」をもって文体の手本となさしめようと心がけて以来久しいのですが、なんともはぁ、とてもじゃないが見果てぬ夢のまた夢。いまや文体どころの話ではなく、墓場行きが目の前となりました。トホホ・・・・。
平家物語 巻十一 第百二句
与一そのころ十八九なり。赤地、浅葱(あさぎ)の錦をもって、はた袖いろへたる直垂(ひたたれ)に、萌黄(もえぎ)にほひの鎧(よろい)着て、足白(あしじろ)の太刀(たち)を帯(は)き、中黒の矢の、その日のいくさに射(い)残したるに、薄切斑(うすぎりふ)に鷹の羽はぎまぜたる、ぬための鏑(かぶら)さし添えたり・・・兜(かぶと)をぬいで高紐(たかひだ)にかけ、御前(義経)にかしこまる。判官(義経)、「いかに与一、傾城(けいせい)のたてたる扇の真ん中射て、人にも見物させよ」とのたまへ・・・なぎさよりうちのぞんで見れば遠かりけり・・・をりふし風吹いて、船、ゆりすえ、ゆりあげ、扇、座敷にもさだまらずひらめきたり。沖には平家、一面に船を並べて見物す。与一・・・しばらく天に仰ぎ祈念申しけるは、「南無帰命頂礼(なむきみやうちょうらい)、御方(おかた)を守らせおはします正八幡大菩薩、別してわが国の神明、日光権現、宇都宮、那須の温泉大明神、願わくは、あの扇のまん中、射させて賜せたまえ・・・」と心のうちに祈念して、目をひらき見たりければ、風もすこし静まり、扇も射よげにぞなつたりける・・・十三束の鏑(かぶら)取ってつがひ、しばしたもちて放つ。弓はつよし、浦にひびくほど鳴りわたりて、扇のかなめより上一寸ばかりおいて、ひやうふつと射切つたれば、扇こらへず、三つに裂け、空へあがり、風にひともみもまれて、海へざつとぞ散りたりける・・・沖には平家船ばたをたたいて感じたり。陸には源氏箙(えびら)をたたいてどよめきたり。
与一の場合、平家の扇を射てんとて、義経から指名された後、馬はおろか装束一式を、源次郎党らから借り受け、あわてて、その場で身づくろいをしたに違いありません。沖はるかに小船にのって義経方を挑発してくる、平家の傾城の美女がささげる扇を前にして、それ相当の成り立ちをせねば、源氏の恥にござります。鎌倉殿に、申し訳がたちますまい。馬子にも衣装とは、そもそも那須与一の物語より発生したとかしないとか。浴衣に毛の生えた程度の貧しい装束は、その場に脱ぎ捨て、陣屋の裏のほうで、急いで着替えたのでござります。与一も数え19の春のこと。人生の晴れ舞台がまっておったのでござります。与一が、屋島くんだりまで、くっついてきたのも弓の腕だけは確かだったのです。
なにしろ「ナスノガ原」は広大無比。関東中を探しても、当時、狩場としてこれ以上有名なところもござりません。イノシシ、鹿、熊、鷹、雉など、食ってうまい、すべての獣が、遊びほうけておったとは、昔より土地に伝わるパラダイス伝説にござ候。これら勇ましい獣を相手に、学校にも行かず、毎日弓の練習に明け暮れたわけですから、弓の腕は、めきめき上達する一方にござります。おそらく合戦に参加したのも、領主様のご寵愛。馬でも引けというわけでしょう。訳も分から屋島まで源氏の一党に、くっついてはきたももの、そろそろなすのが原におわせられます田舎のかあちゃんやばあちゃんが恋しくて恋しくて、泣いていたのではないでしょうか。それにしても、見事なかぶら矢でしたな。与一はこうして、今につたわる郷土の英雄として奉られたにちがいありません。
私は、平家物語の上の箇所についても往時の「知識人」が書いたとは思いません。一般に「平家物語」は、登場人物たちの装束を詳しく述べたて、雰囲気を作り出す。普通名詞が語呂並べ。おそらく鎧や装束に詳しい職人郎党などが、さらに物語の原型に、言葉をさしはさみ、さらに物語を膨らませているのです。同じことは与一が祈る、故郷に祭られた神々にも及びます。日光権現、宇都宮、那須の温泉大明神とある。これは下野の住人一党らの言葉のはしはし。田舎者であればこその証拠です。いわば知識人というよりは、いっそ落語家か、漫才師らの語り口と申せましょう。
それもあちゃこちゃに住みまたは放浪して各地方の田舎の習俗とうとうをよく知っているものどもの口吻こそ、さらにさらにと、書き記されて物語を膨らませているように思われるしだいです。一見して判ぜられるのは、近代人の大特徴とされる、どう思った、こう感じたとうとうの「心理」というものが一切書かれていないことです。あくまでも見たとおりが、そのまま叙述されている。心理の代わりに、語呂並べが置き換えられている。そこに人間の雄渾な姿が、リアルに浮かんでくるのでございます。おそらく近代人の私の邪推からすれば、那須といえば、下野も田舎も田舎。
足軽もどきで源平合戦に招集されて屋島まで、首に縄つけられほうほうのていで、くっついてきた舎弟格です。部下もいない最低の足軽もどきの与一が自前の馬に乗っていたとは思えないのです。鎧かぶともなかりせば、浴衣に毛のはえたほどの装束だったのではないでしょうか。たまたま、与一を引き連れてきた、領主なりが那須の原で弓矢での狩の名人として、それなりに名高かった与一に義経の御前に出ることを命じた。平家の挑発的扇打ちに名乗りを上げた将兵は数名いた。その中で義経が与一を指名したのは、あまりに貧しげな身なりに興味をもって、与一の意外性に賭けたとも思われるのでござります。
<2005年 記>