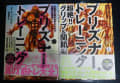ピアノ聴いてきました。猛暑でもホールは涼しいし、潤いのあるピアノの音は癒やしてくれるし、居心地は最高です。暑いので何を着て行こうかと迷いましたが、演奏者本人が大きな花柄みたいな模様の派手な上着で出てきたので、少なくともこの人の時はカジュアルでいいんだと思います。
曲目は、
バッハ 主よ 人の望みの喜びよ
ショパン 幻想即興曲 Op. 66
同 バラード第3番 Op. 47
同 エチュード Op. 10-12 革命
チャイコフスキー(プレトニョフ編曲) くるみ割り人形組曲
モーツァルト きらきら星変奏曲
リスト ピアノソナタ ロ短調
同 ラ・カンパネラ
アンコール3曲 ドビュッシー 月の光 他
「くるみ割り人形組曲」は編曲したプレトニョフさんの演奏を昔FMでエアチェックして、好んで何回も聴いているので、今回は生演奏で聴けて感激しました。冬の曲なので一時暑さを忘れるのもいいですね。
楽しませてもらった記念にCD買ってサインしてもらいました。涼しい顔して超絶技巧の曲を次々に演奏する技量と、観客を楽しませてくれるサービス精神を兼ね備えたエンターテイナーなので、日頃クラシック聴かない人にも足を運んで頂きたいです。
東宝シネマズで「国宝」を鑑賞。評論が仕事ではありませんので個人的な感想を簡単に。
今の邦画が正面から文字通りの芸術至上主義を描くとはかなり驚きで、まず制作した度胸を買います。歌舞伎の再現度については日頃興味がないのでよくわかりませんが、少なくとも動きに弛んだ所はありませんし、名優の4代目中村鴈治郎が全面指導して納得行くまで追い込んだそうなので、称賛すべき仕上がりなのでしょう。一種のシンクロダンスである「二人藤娘」などは素人が見てもあらが見えやすいはずなので、上出来と言っていいと思います。主役二人の熱量だけでもたいしたもの。
脇役もしっかり仕事をしている印象で、多くの人がコメントしていますが人間国宝役の田中泯さんの存在感は出色。舞踊は専門ですから雰囲気があるのは当然としても、頂上に立ち続ける人ならではの重圧を内に秘めて若い人に向き合う姿勢や、引退後に安アパートの一室に横になって、「ここには何もきれいなものがないでしょう?」と、開放されたように言葉を継ぐ様子など、傑出した重量感があります。この配役無しでは映画が軽くなってしまいますね。
あとは細かいところまで演出がしっかりしていること。歌舞伎の舞台はもちろん、重症の糖尿病で左脚を切断した俊介が、義足を付けてまで臨んだ最後の「曽根崎心中」で、縁側から下ろした足を徳兵衛役の喜久雄が掻き抱き、カメラがアップになると、俊介の残った右足も化粧で隠しようがないほど色が悪く、重篤な循環不全に加えてびっしりと爪白癬が曝け出される場面。遠くない俊介の死を暗示したシーンであり、汚らしい爪白癬までしっかり再現したからこその説得力だと思います。美術などの世界で神は細部に宿る、と言いますが、細かいところまで作り込んだからこそ、重厚なストーリーが生きるわけです。全方面に手を抜かず作り上げた大作であり、好き嫌いは別としても日本映画の歴史に残る一作と感じました。
ミッドランドスクエアシネマの「午前10時の映画祭」ドクトル・ジバゴに行って来ました。テレビで見たことはありますが、スクリーンで見るのは初めて。全編通して見るのも初めて。ミッドランドのスクリーン7はあまり音響に力を入れていないのか、そもそもデジタル化に金を掛けてないのか、音が今ひとつ。デジタルリマスターで見事に蘇った映画もあるのですから、これだけの名画については何とかならないかと思います。もっとも、観客はちらほらといった感じで、採算を考えると贅沢は言えないのでしょうね。
激動の時代背景、変化を利用してのし上がろうとする人たちと、翻弄されながらも誠実に生きようとする人々。壮大なドラマは何度見ても見応え充分です。役者も全部いいのですが、やはりラーラ役のジュリー・クリスティーが素晴らしい。もちろんスラブ人らしいメイクをしているのですが、憂いを帯びた表情でアイロン掛けてるだけで、内に秘めた情熱を表現できる人は稀だと思います。有名な「ラーラのテーマ」は彼女のためにあるような曲だと感じます。ハリー・ポッター「アズカバンの囚人」のマダム・ロスメルタ役で出ていたと見て少しびっくり。歳が離れているがロンの憧れの人、という設定らしいので、なるほどこのレジェンドを出演させるとは粋で贅沢な配役だと思いました。
なぜ山に登るのか、と問われて、「そこに山があるからだ」と答えた登山家がいるそうです。なぜ研究するのか、なぜ知識を求めるのか、と科学者が問われれば、そこに知らないものがあるからだ、と答えるのでしょう。オッペンハイマーと同時代の核物理学者、ハイゼンベルクは「科学者は知識の奴隷である」と語ったことがあるそうです。オッペンハイマーという人物はまさしく知識の奴隷であって、どんなことであれ触れる物を知らずにおかない、という強い衝動を持っていました。当時のアメリカでは誰も関心を持たなかった量子力学の世界に飛び込み、ヨーロッパの高名な科学者を訪ね歩き、オランダで講義を頼まれれば6週間でオランダ語を詰め込んでオランダ語で講義を始めて聴衆を驚かせ、ふと出会ったインド哲学を理解するためにサンスクリット語を読解する。そこにはコスパとかタイパとかいう観念はなくて、とにかく知らずにおれないのです。
同じ流れで当時勃興した労働運動に首を突っ込み、共産主義者と交流する。党員の女性とも無防備に交流するから、プロパガンダの理解者だと誤解され、警戒心なしに男女の関係に陥る。ある意味無邪気な知識欲の塊である彼の行動を、周囲はアカだとか女たらし(映画ではwomanizerと称している。ホリエモン名誉棄損裁判で論点となった、女性化という意味は少なくとも辞書にない。理科系には常識のcatalizerも直訳すれば猫化装置になるのだが、実際は触媒のことである。言葉は慣用の要素が多いので、理屈通り直訳しても大外しすることがある。)と批判する。これが後に失脚の原因となります。これと対極に描かれているのが、核物理については何一つ功績がないのに、マンハッタン計画を踏み台にして政治家としてのし上がろうとしたストローズです。
会議でプランに反対され、笑い物にされた意趣返しに、オッペンハイマーに包囲網を敷き、社会的に葬ろうと狂奔する晩年のストローズの足掻き方は、あの天衣無縫のチャーリーを演じた人と同一人物とは思えないロバート・ダウニーJr.の見事な演技。役者は本当に何にでも化けますね。他にもマンハッタン計画の軍側の責任者であるグローブス将軍を演じたマット・デイモン、デンマーク出身の卓越した理論物理学者ニールス・ボーアを演じた演劇の至宝ケネス・ブラナー、トルーマン大統領役のゲイリー・オールドマン(アズカバンの囚人でシリウス・ブラック役)など、実力者が脇役を固めていて存在感が凄い。この重量級の脇役なくしては、話そのものが軽くなってしまいます。物語は対立に次ぐ対立で進行しますが、対立の双方に理があるから当事者は苦悩せざるを得ないので、これは子供が見る勧善懲悪のストーリーではありません。大変見応えのある、疲れる映画です。
この長編を見て、私が想起したのは「アラビアのロレンス」です。当時のイギリスによるアラブ支配の転換点を作り出した奇才で、本人は政策的な意図と言うよりはアラビアへの憧憬とも言える興味から現地工作の先兵となって働き、その奇跡的なアカバ攻略の後で、利権を確保したイギリス政府は邪魔者となったロレンスを現場から排除します。その余りに冷たい処置に同僚の軍人は鼻白みますが、事実かどうかはさておき、映画ではイギリスの策に乗ってサウジアラビアを手に入れたファイサルが、直前のロレンスとの対面で「我が友」と激賞したその舌の根も乾かぬうちに、「余は国王であり、そなたらは軍人に過ぎぬ」とロレンス切り捨てにお墨付きを与えます。余人をもって代えがたい働きをしたロレンスも、今回のオッペンハイマーも、政治の大きな流れの中ではチェスの駒として扱われたに過ぎなかったわけです。まあ、トルーマンがオッペンハイマーを優遇したところで、原爆投下を止められなかったという彼の苦悩が軽くなるものでもなかったでしょうが。ローレンスとオッペンハイマーはどちらも権力に利用されて、ほかの人にはとても及ばなかった人類史の転換を演出した人物であり、実はその意図はなくて、自分が招いた結果については苦悩と後悔を抱いて残りの人生を歩んだという大きな共通部分を持っています。
確かにイギリスのアラビア政策は今の中東の不幸を作り出した根本原因ですし、原爆が広島と長崎に人類史上初の災禍をもたらしたのは事実です。しかし今のガザ地区の惨禍が元々はイギリスが蒔いた種であり、決してロレンスを免罪できないにしても、彼個人の物語は魅力的で、「アラビアのロレンス」は名画と評価されています。同じ基準を用いるなら、「オッペンハイマー」が同等に評価されることは不思議がないと感じています。
ストーリーに大きな影響はないのですが、フレディー・マーキュリー役を熱演したラミ・マレックが物理学者の一人として出演していたり、パーティーでボンゴ叩いてるのが(名前は出ませんが)リチャード・ファインマンだろうなというお楽しみも用意されているので、お好きな人はディスクや配信で見倒して下さい。
久しぶりに映画を見てきました。伏見のミリオン座です。2019年に伏見駅の北側に移転したのを知らずに、最初は御園座の方に行ってしまい少し焦りました。
直木賞作家、水上勉の随筆を原作とした「土を喰らう十二ヶ月」です。水上勉はお寺で修行した経験があり、お寺の典座さんから料理を学んでいます。畑や山野から取れる材料を、精進の精神で慈しんで頂く、今で言う「丁寧な暮らし」を毎日綴り、「美味しんぼ」の雁屋哲さんから「日本で唯一読む価値のある食の本」などと評価されています。
この映画が面白いのは、水上勉をモデルにした、丁寧な暮らしをする主人公を、沢田研二さんが演じていることです。他の配役なら、単に違和感がないだけで地味な映画で終わってしまったのかも知れないですが、彼の熟年になっても全身に漂う色気が、映画全体を華やいだ雰囲気にしていることは間違いありません。
沢田さんがこの役に全身全霊で打ち込んだのは間違いなくて、昭和前半の田舎家で畑仕事や採集、料理に時間と手間を掛け、それこそ朝起きてから夜寝るまで、天地に感謝を絶やすことなく生きている男の姿勢が、手抜きのない所作を通じてしっかり伝わってきます。「ジュリーが大根切ってる!」みたいな違和感は一切なく、演技がしっかりしているからこそ、スーパースターとしての色気が生きてくるものと思います。大した熱演です。
松たか子さんや火野正平さんもいい役をしているのですが、後半で少しだけ登場する檀ふみさんが、連想ゲーム時代のファンである私には嬉しいサプライズでした。「去年82歳の母をなくした」娘という設定は、実年齢にはちょっと合ってないと感じましたが、これはお父さん繋がりで起用されたな、と気付いた人が多いのじゃないでしょうか。
檀一雄は太宰治や坂口安吾などと同じ「無頼派」の作家と言われていて、丁寧な暮らしの水上勉とは生き方がまるで違うのですが、食事や料理への拘りは非常に強く、料理の本も出しています。親しいとまでは言えないですが、水上勉はこの7歳年上の小説家と交流があったらしく、「檀さんはあの小説の通りの人だなあ」と称したらしいです。「あの小説」というのは「火宅の人」ですね。交流があったとなれば、檀ふみさんは実際の水上勉に会ったことがあるのだと思います。映画に重厚さを加える、欠かせない脇役です。
題名に惹かれて入手。前置きが長くて、スパルタの兵士のトレーニングとかローマの軍団の話を引用しています。21世紀の先進国において、「強くならなければ潰される」というプレッシャーが最も作用するのは監獄の中で、20年収監されていた著者が設備も道具もなしに体を有効に鍛え上げるために、交流のあった囚人や看守に学び、本を読み漁って実践したノウハウをまとめたものだそうです。
著者のポール・ウェイドは近代的なトレーニングに否定的な人で、バーベルやノーチラスマシンを「おもちゃ」、ジムでパンプアップしたビルダーの体も「筋肉付けて髪の手入れすら不自由になった」と見下します。この辺は各人のゴールの設定の違いであって、ヴィジュアルな誇張された筋肉やベンチプレスの数字を追い求める人もいるし、囚人として襲われないように「動ける筋肉」を必要としている人もいるので、必ずしもウェイドに全面賛成しなくても本書は役に立ちます。
具体的なトレーニング編の腕立て伏せの進め方、強度の高め方を見れば、このトレーニングが合理的なものであることは十分に理解できます。道具を使わずに、どれだけ筋肉や靭帯、関節などの自然な協調を保ったまま強度を上げられるのか、故障やステロイドの副作用に苦しまずにゴールを達成できるのか、やはり十分な考察と経験がなくては書けない本だと思いました。まだ全部は読んでないので先が楽しみです。訳文も曖昧さがなくて読みやすく、いい仕事だと評価できます。
極楽息子(小)の夏休みの宿題用に買い入れた資料です。主計士官の立場から書いた戦記なので、直接の戦闘と言うよりは全体的な戦況とか補給の状況、食料調達の苦心などにページが割かれています。「ウ号作戦」つまりインパール作戦が当初から補給無視の無謀な作戦であったことは、作者にとっては見習士官として赴任して、作戦概要を初めて聞かされた時から明白でした。インパールを占領するという現実的な目標があったと言うよりは、陽動作戦として英軍を引き付けておいて、最重要戦場である太平洋での戦略を有利にする意味があったという記述もありますが、さすがにそれでは説明できません。わざわざ無謀な作戦で多数の死傷者を出すほどの理由にならないからです。
いざコヒマまで乗り込んでみると、数機の山砲しかない第31師団に対して、英軍は多数の重火器を擁しており、「一日にこちらが40発ほど砲撃するのに対して、敵軍は4万発を放ち、しかも狙いが正確になってくる」と比較にならない火力であり、その上多数の爆撃機と戦車を投入してきます。中国戦線で功を奏した(と言っても犠牲の多さを無視してだが)肉弾戦の突撃に対しても、多数の機関銃で簡単に制圧される。日本の計画は敵に筒抜けであり、飛行機の援護がないことも補給線が脆弱であることも知られていて、後方のビルマ縦貫鉄道付近に空挺部隊を送り込まれ、完全に補給線を断ち切られます。
多くの文献や報道が示す通り、インパール作戦は実行に移されたことが致命的な誤りでした。旧陸軍の意思決定に構造的な欠陥があったということは、きちんと検証されるべきだと思います。
シュポルスキーの原子物理学は、文系の妹が教養で科学の講義を取っていて、参考図書として示されたので買ったそうですが、文系の講義でよくこんな本推薦するなあと呆れる難度。物理学科行かなきゃ宝の持ち腐れと言うものです。
砂川重信先生の理論電磁気学は、高校の時に先生の参考書を使っていたので買ってみましたが、やはり高校生向けの本と物理専攻向けの本は別物で、読むのに苦労しました。当時は高校の理科系用に「親切な物理」がベストセラーになっていましたが、私は砂川本のすっきりした記載を気に入っていました。
フェルミは名前につられて買ってみただけ。他の熱力学の本と内容は変わらないと思います。
流体力学は理学部でほんの少し噛っただけなので、レイノルズ数という用語を覚えただけ。とてもこの本の全容は理解できていません。
生物科学科だったはずなのに、今回の発掘本は物理や化学が多いですね。生物関係は実家に放置せず今の家に持って来たからでしょう。