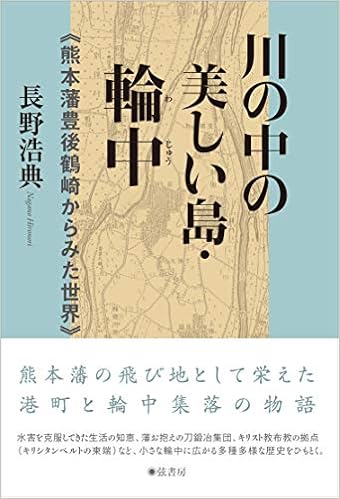寛永拾五年肥前国於有馬原城働之御帳・2
一、松山次郎大夫
一、二月廿七日有馬原之城二ノ丸にて鑓を合突たをし申候 鑓手負申候ニ付二丸より引取申候
証人合申候
一、小崎与次兵衛
一、二月廿七日有馬原之城本丸犬走へ上り貴利志丹と鑓にて突合申候所を内より鑓にて突落され又犬走ニ上り申候
所を石にて打落され申候 御下知にて引取御本陳へ參申候
証人合申候
一、岡部庄之助
一、二月廿七日有馬原之城本丸石垣ニ著鑓にてからち合私鑓を切をられ石にて打落され其後又石垣際へ著申候 其所
石を打申ニ付而なたれ候へとも残り居申御下知にて引取御本陳へ參申候
証人合申候
一、猿木何右衛門
一、二月廿七日有馬原之城本丸犬走へ上り塀ぐいに取付塀裏にて鑓にて突合申候 内より鑓にて突落され石にても打
おとされ申候 御下知にて引取御本陳へ參申候
証人合申候
一、矢野勘左衛門
一、二月廿七日有馬原之城本丸石垣半分程上り内より鑓突出し申所を私も鑓にてつき申候ヘハ私鑓を切おり申候 其
後何も同前ニ乗込申候
証人合申候
一、柳瀬茂左衛門
一、二月廿七日有馬原之城本丸石垣犬走ノ上にて塀の破より敵鑓を突出し申所私も鑓にてからち合手負申ニ付引取
申候
証人合申候
一、下村五兵衛
一、二月廿七日有馬原之城本丸犬走へ両度上り両度なから鑓にてからち合申候 御下知にて引取申候
証人合申候
一、広瀬 杢
一、二月廿七日有馬本丸石垣へ著犬走へ上り申所を内ゟ鑓にて右之肩先を突石垣下へ突落され申候 御下知にて引取
申候
証人合申候
一、樹下右衛門
一、二月廿七日有馬本丸石垣ニ著犬走へ上り塀ニ著申候而鑓にて突落され申候 又上り申候所を突落され手負申候ニ
付而小屋へ引取申候
証人合申候
一、町 熊之助
一、二月廿七日有馬本丸石垣へ上り塀裏ニ著申候所を矢さまより鑓にて私胸を突申候 其鑓を私取候 其後石手負候
夫より本丸へ乗込申候
一、廿八日本丸柵之内へはいり鑓をなけつきニ仕又しゆりけんうち申候者弐人突留申候 其後手負申候而痛申ニ付引
取申候
証人合申候
一、鎌田源大夫
一、二月廿七日有馬本丸石垣へ少上り鑓を合私鑓を切おられ申候 石にてもいたれ申候 夫より本丸乗込申候
一、廿八日本丸にて鑓をなけつきニ仕又しゆりけんうち申候もの両人突留申候
証人合申候
一、竹内次郎大夫
一、二月廿七日有馬本丸犬走に上り塀の破御座候所にて鑓ニ而からち合申候 其後石垣之原へ上り鑓を城内へ突入申
候所ニ鑓之しほくひを敵とらへ申ニ付引合引かち申候 夫より本丸へ乗込申手負候而退申候
証人合申候
一、福田次郎右衛門
一、二月廿七日有馬本丸水手須戸口際へ上り申刻鉄炮にてほかミの下を打ぬき申候得とも其手にかまい不申石垣ニ
著申候を又右之肩先に鉄炮中り申すニ付引取申候
証人合申候