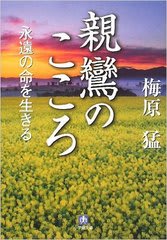開高健 「巷の美食家」読了
以前に読んだ、「食の王様」と同じく、師の過去の文章をいくつか抜き出して編集したものだ。多分、つぎはぎの文章の印象がよくなかったので続編のようなこの本は買わないでいたのだと思う。ネットの古本で1円の値がついていなければ多分買わなかっただろう。
やはり原本でつながりをもって書かれているから一つ一つのエッセイが生き生きしてくるのだ。まして書かれた年代もまちまちで系統立てられていないようなので師の文章をよく知らない人にとっては筆致のちがいに戸惑うのではないだろうか。
谷沢永一や向井敏が監修しても物足りなさを感じるのだ、名もない一介の編集者がつまみ食いをしてもいいものができるはずがない。
しかし、ムムッとなってしまう部分がないわけではない。
山菜について書かれた部分だ。
~~物には、〝五味″などというコトバではいいつくせない、おびただしい味、その輝きと翳りがあるが、もし〝気品″ということになれば、それは〝ホロにがさ″ではないだろうか。これこそ〝気品ある″味といえないだろうか。ことに山菜のホロにがさである。それには〝峻烈″もあり、〝幽邃″もこめられているが、これはど舌と精神をひきしめ、洗い、浄化してくれる味はないのではないだろうか。~~
これは奥只見の銀山湖での経験として書かれたものだ。
どの本が原典かは思い出せないが多分、遠い昔に読んだことがあるはずだ、若い頃には山菜の〝ホロにがさ″なんてまったく何の美味しさも感じなかったはずで、この文章も記憶のなかを通り過ぎていったのだろうと思うが、今となってはなんともいとおし味だ。
歳を経なければわからない味。そんな味を思い描くことの1冊ではあった。
以前に読んだ、「食の王様」と同じく、師の過去の文章をいくつか抜き出して編集したものだ。多分、つぎはぎの文章の印象がよくなかったので続編のようなこの本は買わないでいたのだと思う。ネットの古本で1円の値がついていなければ多分買わなかっただろう。
やはり原本でつながりをもって書かれているから一つ一つのエッセイが生き生きしてくるのだ。まして書かれた年代もまちまちで系統立てられていないようなので師の文章をよく知らない人にとっては筆致のちがいに戸惑うのではないだろうか。
谷沢永一や向井敏が監修しても物足りなさを感じるのだ、名もない一介の編集者がつまみ食いをしてもいいものができるはずがない。
しかし、ムムッとなってしまう部分がないわけではない。
山菜について書かれた部分だ。
~~物には、〝五味″などというコトバではいいつくせない、おびただしい味、その輝きと翳りがあるが、もし〝気品″ということになれば、それは〝ホロにがさ″ではないだろうか。これこそ〝気品ある″味といえないだろうか。ことに山菜のホロにがさである。それには〝峻烈″もあり、〝幽邃″もこめられているが、これはど舌と精神をひきしめ、洗い、浄化してくれる味はないのではないだろうか。~~
これは奥只見の銀山湖での経験として書かれたものだ。
どの本が原典かは思い出せないが多分、遠い昔に読んだことがあるはずだ、若い頃には山菜の〝ホロにがさ″なんてまったく何の美味しさも感じなかったはずで、この文章も記憶のなかを通り過ぎていったのだろうと思うが、今となってはなんともいとおし味だ。
歳を経なければわからない味。そんな味を思い描くことの1冊ではあった。