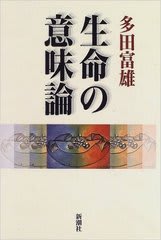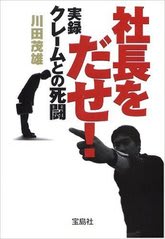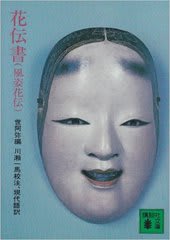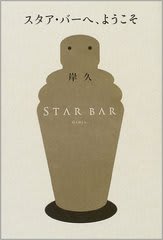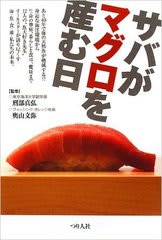速水 侑 「図説 あらすじでわかる!日本の仏」読了
虚空蔵菩薩は一度見たこと、聞いたことは絶対に忘れないそうだ。
仏像を鑑賞する機会があるとき、少しでも知識があればもっとその意味を深くかみしめながら観ることができるのではないかといくつかの本を読んできたが、これがまったく記憶の中に落ち着かない。
情けないことだが、これは学生時代から今までずっとそうだった。英単語から歴史上の人物、数学の問題パターンまで、まったく覚えられない。なんとか大学には入れたが、僕は人の3倍くらいはこれらのことを覚えようと努力したのではないだろうか。人並みの記憶力があればもっと偏差値の高い大学も夢ではなかったかもしれないと今でも悔やまれる。今でも人の名前がなかなか覚えられない。これは仕事の上ではまったく不利に働く。
「念ずると助けてくれる。」これが日本の仏様の基本だ。とにかくたくさんの仏様がそれぞれのご利益を持っていろいろなお寺に鎮座されている。釈迦が説く人生とは、苦しいことそのものだということだ。実際そのとおりでだからなんとか救ってほしいという願いが偶像になって現れたのがこれらの仏様なのだが、読み進めるうちに、こんなに助けてもらうだけでいいのだろうか?なんていう思いが沸いてくる。念ずるだけで助けてくれるというのはあまりにも安直で、それ以上何の努力もしなくなってしまうのではないだろうか?
キリスト教にせよ、イスラム教にせよ、偶像崇拝を禁じている。目の前に助けくれる対象があればそれに頼り切ってなにもしなくなる。だからそれを禁じているという面もあるだろう。
両方とも一神教だから仏教みたいにいろいろなキャラクターが出てこないので、偶像があってもあまり面白くないといえば面白くないので、じゃあ、最初からやめておこうなんていう考えもあったりもするのだろうが・・。
仏教が東の端までたどり着いて花が咲きいろいろな仏像が生まれ、その延長上にアニメやキャラクターの文化があるのではないかといつも思っている。四天王なんてそのまんまガンダムみたいだし、ウルトラ兄弟はどことなく如来様みたいに見える。今は二次元というらしいが、そういうものに耽溺しすぎるということは人間として生きてゆく気力のようなものをどんどんそぎ落としてしまうようなどこか危険なところをはらんでいるような気がする。
まさに玩物喪志だ。
いまや外国人からもクールジャパンといってもてはやされ、それらがスマホと癒合して人の心を侵しつつある。もうすぐ現実の世界と空想の世界の重要性が逆転する。
ちょっと前からポケットに入る怪獣を捕獲するゲームが社会問題になりつつあるが、現実の世界を空想の世界とすり替える大きなたくらみのひとつのような気がする。これも人間という有機物で構成された炭素体ユニットを必要としなくなった遺伝子のなせる業だったりしないのだろうかと杞憂な思いを抱くのはぼくだけだろうか。
今の勤務先の近くには有名な虚空蔵菩薩を祀っているお寺があるそうだ。
もう少し涼しくなったら、とりあえずご利益をもらいに行ってみようと思っている。
虚空蔵菩薩は一度見たこと、聞いたことは絶対に忘れないそうだ。
仏像を鑑賞する機会があるとき、少しでも知識があればもっとその意味を深くかみしめながら観ることができるのではないかといくつかの本を読んできたが、これがまったく記憶の中に落ち着かない。
情けないことだが、これは学生時代から今までずっとそうだった。英単語から歴史上の人物、数学の問題パターンまで、まったく覚えられない。なんとか大学には入れたが、僕は人の3倍くらいはこれらのことを覚えようと努力したのではないだろうか。人並みの記憶力があればもっと偏差値の高い大学も夢ではなかったかもしれないと今でも悔やまれる。今でも人の名前がなかなか覚えられない。これは仕事の上ではまったく不利に働く。
「念ずると助けてくれる。」これが日本の仏様の基本だ。とにかくたくさんの仏様がそれぞれのご利益を持っていろいろなお寺に鎮座されている。釈迦が説く人生とは、苦しいことそのものだということだ。実際そのとおりでだからなんとか救ってほしいという願いが偶像になって現れたのがこれらの仏様なのだが、読み進めるうちに、こんなに助けてもらうだけでいいのだろうか?なんていう思いが沸いてくる。念ずるだけで助けてくれるというのはあまりにも安直で、それ以上何の努力もしなくなってしまうのではないだろうか?
キリスト教にせよ、イスラム教にせよ、偶像崇拝を禁じている。目の前に助けくれる対象があればそれに頼り切ってなにもしなくなる。だからそれを禁じているという面もあるだろう。
両方とも一神教だから仏教みたいにいろいろなキャラクターが出てこないので、偶像があってもあまり面白くないといえば面白くないので、じゃあ、最初からやめておこうなんていう考えもあったりもするのだろうが・・。
仏教が東の端までたどり着いて花が咲きいろいろな仏像が生まれ、その延長上にアニメやキャラクターの文化があるのではないかといつも思っている。四天王なんてそのまんまガンダムみたいだし、ウルトラ兄弟はどことなく如来様みたいに見える。今は二次元というらしいが、そういうものに耽溺しすぎるということは人間として生きてゆく気力のようなものをどんどんそぎ落としてしまうようなどこか危険なところをはらんでいるような気がする。
まさに玩物喪志だ。
いまや外国人からもクールジャパンといってもてはやされ、それらがスマホと癒合して人の心を侵しつつある。もうすぐ現実の世界と空想の世界の重要性が逆転する。
ちょっと前からポケットに入る怪獣を捕獲するゲームが社会問題になりつつあるが、現実の世界を空想の世界とすり替える大きなたくらみのひとつのような気がする。これも人間という有機物で構成された炭素体ユニットを必要としなくなった遺伝子のなせる業だったりしないのだろうかと杞憂な思いを抱くのはぼくだけだろうか。
今の勤務先の近くには有名な虚空蔵菩薩を祀っているお寺があるそうだ。
もう少し涼しくなったら、とりあえずご利益をもらいに行ってみようと思っている。