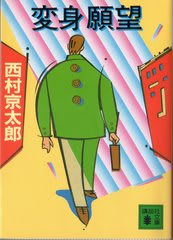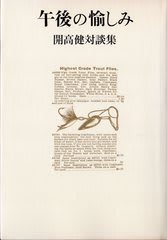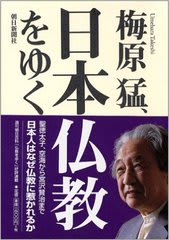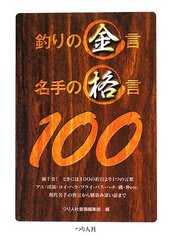西村京太郎 「変身願望」読了
まず自分で選んで読む本ではないのだが、会社の事務所で、Eテレの「100分で名著」が面白いという話から、あの番組で取り上げられていたカフカの「変身」はこうやって読むのだというのがわかったという話になり、その子が、家に「変身願望」って本がありますよと言ってくれので一度読んでみようと借りてみた。
西村京太郎というと、十津川警部が時刻表とにらめっこして事件を解決するという土曜ワイド劇場しか知らないのでどんな物語だろうと読んでみたら、なかなか、人間のエゴとそのなれの果てをたっぷりのアイロニーを込めて書かれた短編集だった。
昭和40年代の後半から50年代の前半に書かれたものだが、受験生時代、深夜ラジオが始まる前の時間帯のラジオドラマのシナリオのような感じの物語であった。
会社に初めて導入されたNECのパソコンにリセットボタンというのがあった。押すとウインドウズが再起動するというもので、これを見ながら人生のリセットボタンってないのだろうか?なんていつも考えていたが、たとえ変身できたとしても結局は今の生き方が一番いいと思うに違いない。奥さんも、それは長澤まさみが家にいて、「今日の晩御飯はおでんやで~。」って言ってくれるとうれしいがやっぱり和歌山弁をしゃべる長澤まさみはちょっと気持ち悪く、今の奥さんがちょうどいいとしておいた方が無難なわけで、この本はこんな感じの内容であった。
まず自分で選んで読む本ではないのだが、会社の事務所で、Eテレの「100分で名著」が面白いという話から、あの番組で取り上げられていたカフカの「変身」はこうやって読むのだというのがわかったという話になり、その子が、家に「変身願望」って本がありますよと言ってくれので一度読んでみようと借りてみた。
西村京太郎というと、十津川警部が時刻表とにらめっこして事件を解決するという土曜ワイド劇場しか知らないのでどんな物語だろうと読んでみたら、なかなか、人間のエゴとそのなれの果てをたっぷりのアイロニーを込めて書かれた短編集だった。
昭和40年代の後半から50年代の前半に書かれたものだが、受験生時代、深夜ラジオが始まる前の時間帯のラジオドラマのシナリオのような感じの物語であった。
会社に初めて導入されたNECのパソコンにリセットボタンというのがあった。押すとウインドウズが再起動するというもので、これを見ながら人生のリセットボタンってないのだろうか?なんていつも考えていたが、たとえ変身できたとしても結局は今の生き方が一番いいと思うに違いない。奥さんも、それは長澤まさみが家にいて、「今日の晩御飯はおでんやで~。」って言ってくれるとうれしいがやっぱり和歌山弁をしゃべる長澤まさみはちょっと気持ち悪く、今の奥さんがちょうどいいとしておいた方が無難なわけで、この本はこんな感じの内容であった。