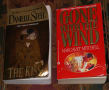「平の将門」の次に電車で読んでいる「梅里先生行状記」です。梅里先生とは「大日本史」の編纂で知られる水戸光圀のこと。1941年という時勢を反映して、単調な皇国史観を奉じる光圀と藩士たちの物語で、同じ勤皇の士でも、戦後の「私本太平記」に描かれる楠木正成のような深みのある人物像ではありません。吉川さんが本心ではどちらを描きたかったのか、一目瞭然です。
1935年から39年の「宮本武蔵」ではまだ青年期の武蔵が一乗寺の決闘に臨むに当たり、神仏の加護を受けようという弱い心を振り捨てて死地に赴く場面がありましたが、1941年にはそんな記述すら許されなかったのでしょう。ただただ神とその末裔たる皇室を畏れ敬う人物像ばかりで辟易とします。湊川で楠木正成の忠魂碑を建てる件は、ほとんど現代の「自己啓発セミナー」の乗りで、戦時の読者が昂揚した気分で読めば、それこそ涙を流して感動したでしょう。
また廃仏毀釈の影響か、吉川作品で重要な脇役を演ずることの多い僧侶がほとんど活躍しません。この世を支配する他の原理を排除して、ただただ国の根本は天皇、という無批判な称揚ぶりは戦時の人気作家としては至極当然の姿勢でありますが、いかにも人間臭い「新平家」の後白河法皇や「私本太平記」の後醍醐天皇像を見てから読むと寒気がするほどで、当時の吉川さんは実に気の毒に思います。
柳沢吉保を狙う水戸藩浪士の無計画ぶりも、国家百年の大事をなす者としてはリアリティがなく、短兵急な行動ばかりで漫画的です。「怪傑黒頭巾」ならこれでもいいのですが、吉川さんの重々しい文章でこんなストーリーを書かれると、笑って済ますこともできず困惑するしかありません。