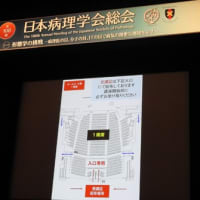吉川英治全集を「宮本武蔵」から「新平家物語」「私本太平記」と読み継いで今度は「平の将門」読了です。ここまで大長編ばかりだったので、1冊しかない今回は印象が薄いですね。本の分量のみならず、主人公の将門がどうも物足りない感じです。吉川さんも、書いていてつまらなくなったんじゃないでしょうか。
「宮本武蔵」なら何より武蔵と小次郎、そして武蔵と又八、あるいは武蔵と本位田のおばば。そして武蔵と石州斎。「新平家物語」なら清盛と後白河法皇、清盛と麻鳥、清盛と文覚、義経と頼朝。「私本太平記」なら尊氏と後醍醐天皇、尊氏と楠木正成、尊氏と佐々木導誉、尊氏と直義。いずれも主役を食いかねない彫りの深い脇役が生き生きと主役に対比して描かれていて、それが主役のキャラクターをより一層印象付けています。「宮本武蔵」以外の吉川さんの主役は清濁併せ呑むような「大どかな人物」であることが多く、単独で描かれてもキャラクターがはっきりしにくいため、余計にライバルが重要になります。「平の将門」ではどうもそこが弱くて、吉川さんも長編にしようがなかったのではないでしょうか。
強欲なだけの伯父ではさして面白くない相手ですし、策謀家の貞盛も魅力に欠ける人物です。単純な善悪の対決ではなく、いずれにも理があり大きな正義がある者同士が引くことならず泥沼の対立に陥る、というのが吉川文学のパターンであり、読者はそこに時代劇を超えた普遍的な面白さを感じているのだと思います。
将門の反乱は「俵藤太のムカデ退治」で知られる押領使、藤原秀郷により鎮圧されますが、この興味深い人物の扱いが余りにあっさりしているのは肩透かしを食らった感じです。また死後に怨霊として恐れられたことについても伏線がなく、吉川さんならもう少し何とかしてくれないかなあ、というもどかしさすら覚えます。崇徳上皇の例もあるように、強い怨霊となったのは恨みを抱いて死んだからでしょう。この本のあっさりした場当たり的な野人である将門が死んだところで、怨霊になる気配もありません。
ここは史実と異なっても、関八州を支配してようやく大義を持ち始めた将門が、朝廷の懐柔と卑劣な策謀により陥れられて、世を呪い人を呪いながら憤死したことにして欲しいものです。これを書かれたころの吉川さんは「新平家」の方に注力していたので、「将門」の方は短くまとめたかったのかな、とも思われる出来でした。