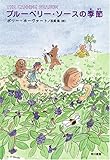極楽息子(大)はルパンを愛読しているようです。この南洋一郎翻訳のシリーズは私も持っていてよく読みました。南さんは戦前に「少年倶楽部」に連載した冒険小説がベストセラーになった作家であり、一連のルパン物も翻訳と言うよりは改作により人気を博したようです。
他の訳者による(原文の逐語訳に近いと思われる)訳でルパンを読んでみると、当時の小説のスタイルと思われる詳しい情景描写やエスプリの効いた長々しい会話などが、少年少女を対象に考えた場合はかなり読みにくかろうと思わせるのは確かで、子供向け冒険小説の乗りのいい筆致でルパンを再創造した南さんは、改作による批判を受けるものの、日本に多くのファンを得ることに成功しました。
世界的な知名度があると思われているルパンシリーズは、意外にも本国フランスと日本以外ではあまり知られていません。これはドイルやクリスティーの作品が世界でロングセラーとなり、何度も映画やテレビシリーズになっているのに、ルパンの映像化が極端に少ないのを見ても納得できます。日本ではルパンへのオマージュが「ルパン三世」を生み出したほどの国民的な知名度があるのは、南さんの功績が大きいと考えていいでしょう。

こっちは学校の図書館から借りて来たそうです。英語を始めたばかりでいきなり英語の詩集とは大胆ですな。まあ、語学に限らず学問では大胆、身の程知らず、猪突猛進は大いに結構です。失敗を恐れるのは家族を養う重圧が掛かってからでよろしい。