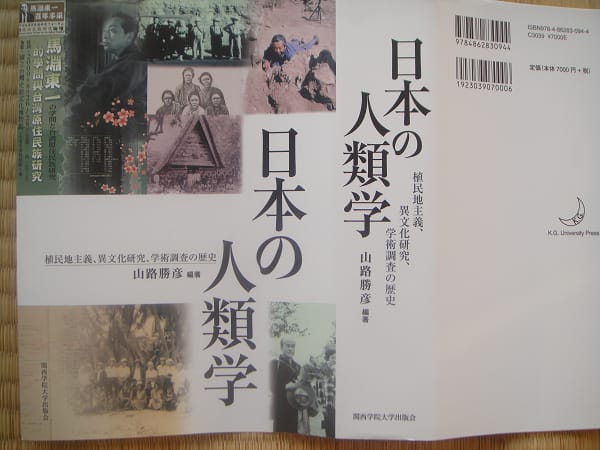久しぶりに下関の大韓キリスト教会に出席した。信徒は多少変わっても中心メンバーは変わりなく、懐かしく全員から心から歓迎されたと感じた。わが夫婦は引越しなどで数多く教会は変えても信仰は変えてはいない。最近私の心に生涯で初めての教会離れ志向が起きている。神の名を借りて勝手に物事を決めたり、閉塞的な空間を作ったりすることが最近になって気になっている。そんな私を家内が心配しているような気がする。昨日急に韓国教会へ向かった。久しぶりに礼拝に参加して久しぶりに新鮮な、意味深い説教を聞いてほっとした。全員が握手したり、声をかけてくれたりいろいろ話しかけたり心温まる時間があり、何より感謝すべきである。日本の教会より時間がゆっくり流れているようにも感じられた。
説教は僕が主人に「忠誠」をつくすたとえから、与えられたものをどのように生かすかということであったが 主従関係においても、そこにはお互いの信頼関係の「忠誠」が必要であり、「充実」したしごとであるべきことを考えさせるものであった。説教はそこまで到っていないが、私には深める時間が与られた感じである。私は日常生活においても、人は互いに信頼する忠誠が必要であり、仕事(業)には充実したものを求める職業観と人への義理など、今一度考え、今日からの生活の中でそのことを心に留めて努力していきたい。忘れて聖書を置いてきてしまった。牧師や長老から電話してくれて温情が伝わってきた。
下関教会
住所 : 〒750-0043 下関市東神田町5-6 083-222-0097 FAX : 083-222-0097
礼拝案内 日曜日 午前 11
牧師 : 鄭在植
説教は僕が主人に「忠誠」をつくすたとえから、与えられたものをどのように生かすかということであったが 主従関係においても、そこにはお互いの信頼関係の「忠誠」が必要であり、「充実」したしごとであるべきことを考えさせるものであった。説教はそこまで到っていないが、私には深める時間が与られた感じである。私は日常生活においても、人は互いに信頼する忠誠が必要であり、仕事(業)には充実したものを求める職業観と人への義理など、今一度考え、今日からの生活の中でそのことを心に留めて努力していきたい。忘れて聖書を置いてきてしまった。牧師や長老から電話してくれて温情が伝わってきた。
下関教会
住所 : 〒750-0043 下関市東神田町5-6 083-222-0097 FAX : 083-222-0097
礼拝案内 日曜日 午前 11
牧師 : 鄭在植