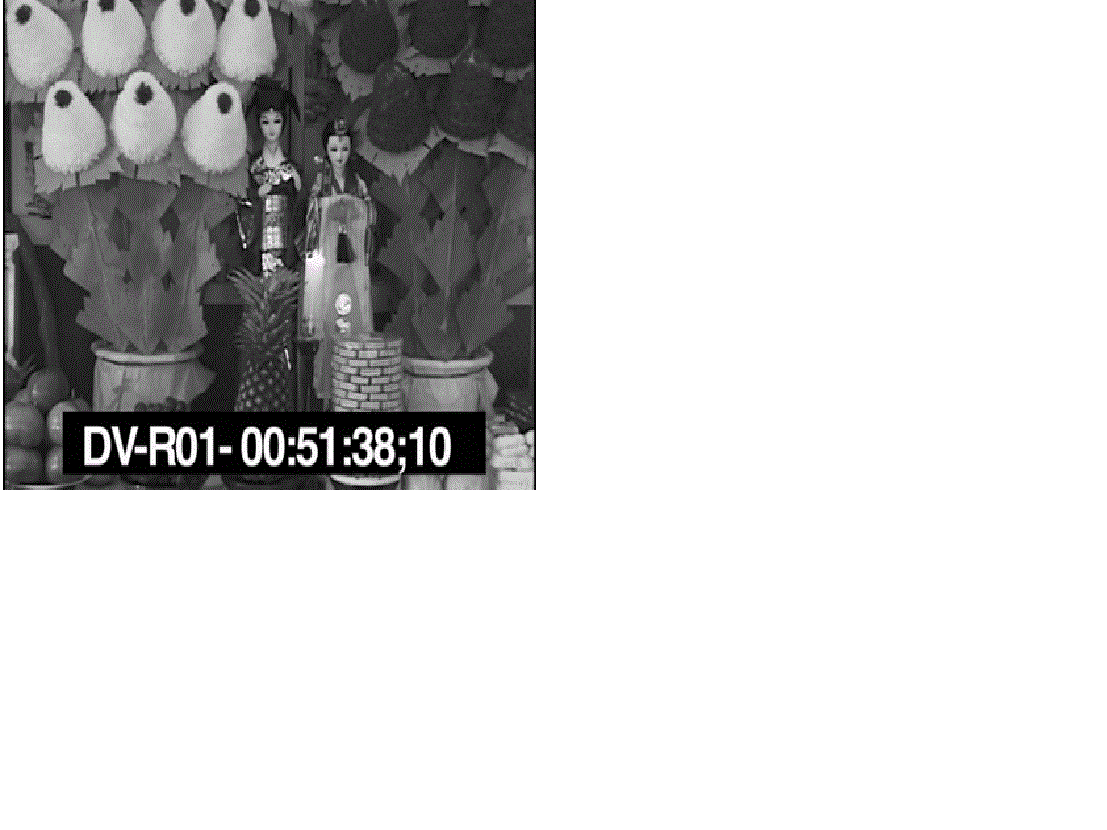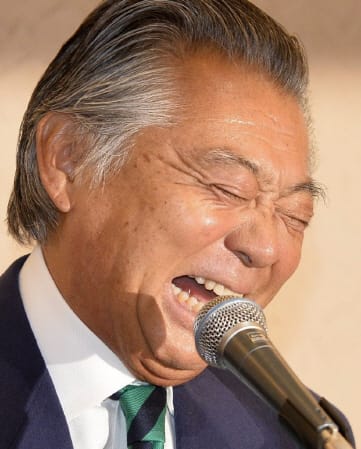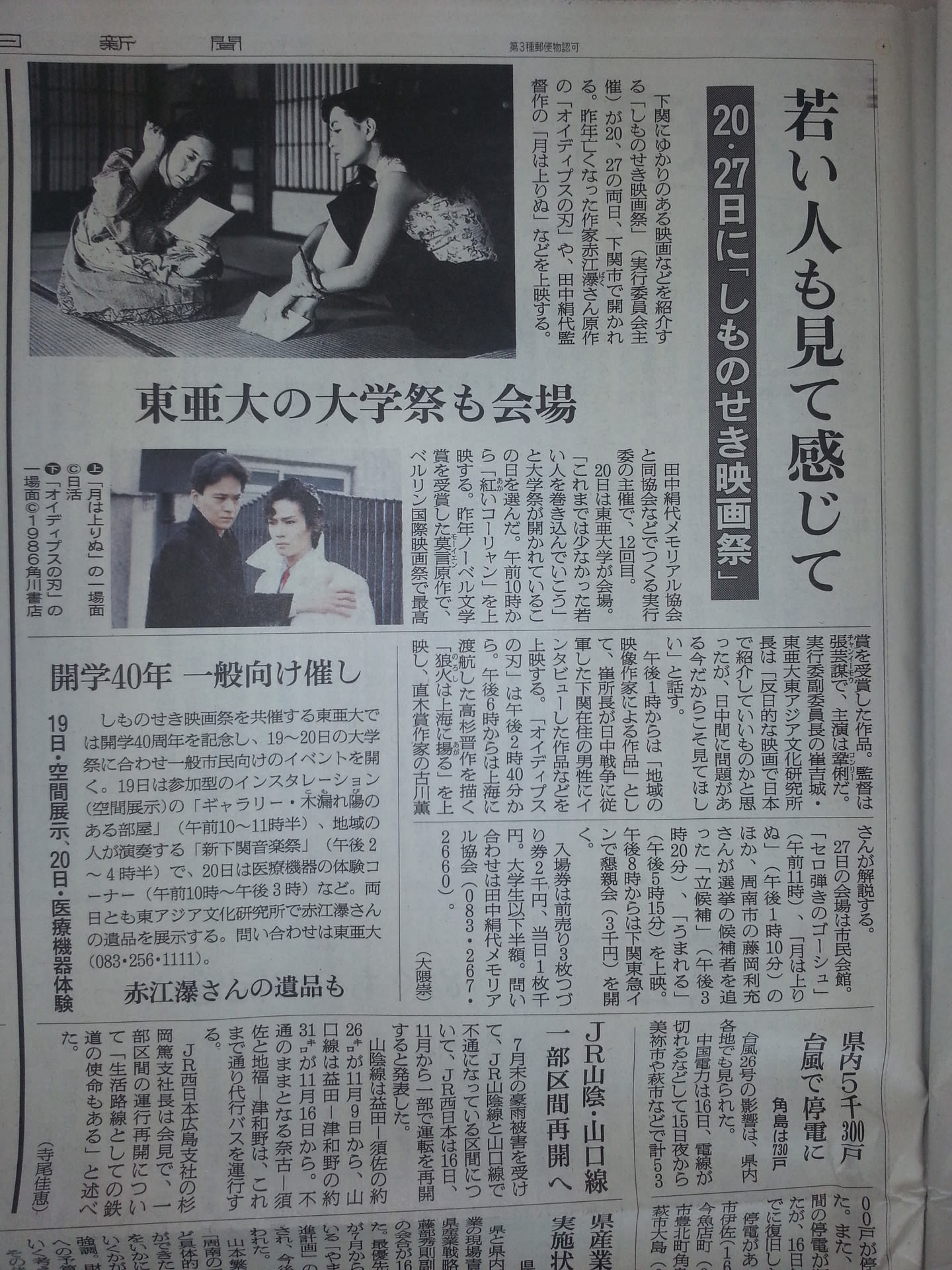北京天安門事件が特にテレビなどで報道されている。しかし中国や韓国ではそれほど報道されていないようである。資本主義経済だけ開放して他は独裁で国家体制を持ち続けられるだろうか、第二の天安門事件のようにみえる。独裁体制の中国政府がこのくらいで揺さぶられるかという態度であろうか。日本のメディアは公平的(?)に中国の環境汚染など頻繁に否定的なことを報道している。日中関係も悪くなっている。その中で日本の中国研究者156人が「新しい日中関係を考える研究者の会」を結成して、「もう黙ってはいられない」学者の出番であると論じた文(倉重篤郎「日中の死角」毎日新聞2013年10月30日)を読んだ。その文を昨日の「日本文化論」の授業で学生に読ませてから議論した。
日中関係悪化の理由として田中角栄、周恩来両首相による国交回復交渉において中国が500億ドルという巨額な対日賠償請求権を放棄したことについて日本側が正当に評価し感謝する儀礼をしなかったことと言っている。つまり日本側は感謝の国家意思表明という公式的な「感謝表明」がなかったという。「中国では、受けた恩はメンツにかけて返すのが流儀。それに対して日本は勝手に中国が放棄した、という構え。それ以来、中国民衆にとって日本は儀礼を欠く国と映り、その後の日本側の親中旧世代の退場、中国の愛国主義教育が重なり日中間の相互否定の感情が増幅してしまった」と言うのである。
政治的な日中問題を禮儀、特に日本側の欠礼にあるという。その政治問題より私は日本人の感謝について考えてみたい。日本では日常的に感謝の言葉として「ありがとう」が頻繁に使われる。ボールペンを貸しても有難うと感謝する。しかし形がないものには感謝を感じない。小銭でも貰ったら感謝するが給料やボーナスなどには当たり前であるかのようである。国費であれば乱用するような現象がないとは言えない。見えないものとして受けたり貰ったりしたことには感謝のこころが湧いてこない。経済的に成功した旧友に奨学会でも作って熱心に勉強する学生に賞として奨学金を出すことを助言したことがある。彼はいう。そのように制度化したお金に人は感謝しない、個人的にお金を上げることにしたいという。「ポケットから1万、10万だして上げると一生忘れないといわれる」という。私も言わせてもらうなら自費で色々情報を集めて予め準備したり、予約したりして案内しても彼らが感謝の心を持っているとは感じられないことが多い。見えないものにも感謝するよう新しく「倫理」を教育すべきである。
日中関係悪化の理由として田中角栄、周恩来両首相による国交回復交渉において中国が500億ドルという巨額な対日賠償請求権を放棄したことについて日本側が正当に評価し感謝する儀礼をしなかったことと言っている。つまり日本側は感謝の国家意思表明という公式的な「感謝表明」がなかったという。「中国では、受けた恩はメンツにかけて返すのが流儀。それに対して日本は勝手に中国が放棄した、という構え。それ以来、中国民衆にとって日本は儀礼を欠く国と映り、その後の日本側の親中旧世代の退場、中国の愛国主義教育が重なり日中間の相互否定の感情が増幅してしまった」と言うのである。
政治的な日中問題を禮儀、特に日本側の欠礼にあるという。その政治問題より私は日本人の感謝について考えてみたい。日本では日常的に感謝の言葉として「ありがとう」が頻繁に使われる。ボールペンを貸しても有難うと感謝する。しかし形がないものには感謝を感じない。小銭でも貰ったら感謝するが給料やボーナスなどには当たり前であるかのようである。国費であれば乱用するような現象がないとは言えない。見えないものとして受けたり貰ったりしたことには感謝のこころが湧いてこない。経済的に成功した旧友に奨学会でも作って熱心に勉強する学生に賞として奨学金を出すことを助言したことがある。彼はいう。そのように制度化したお金に人は感謝しない、個人的にお金を上げることにしたいという。「ポケットから1万、10万だして上げると一生忘れないといわれる」という。私も言わせてもらうなら自費で色々情報を集めて予め準備したり、予約したりして案内しても彼らが感謝の心を持っているとは感じられないことが多い。見えないものにも感謝するよう新しく「倫理」を教育すべきである。