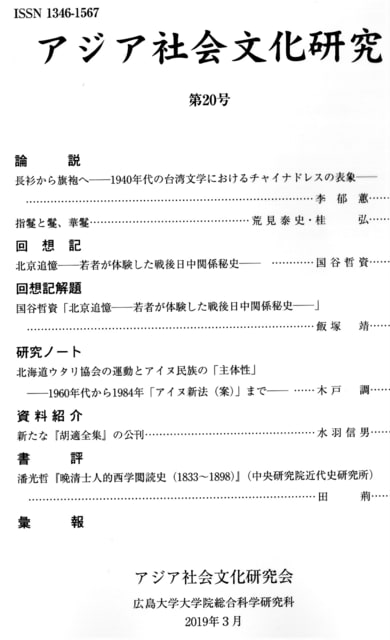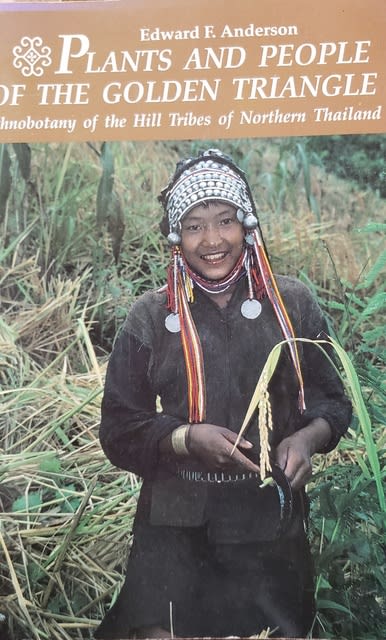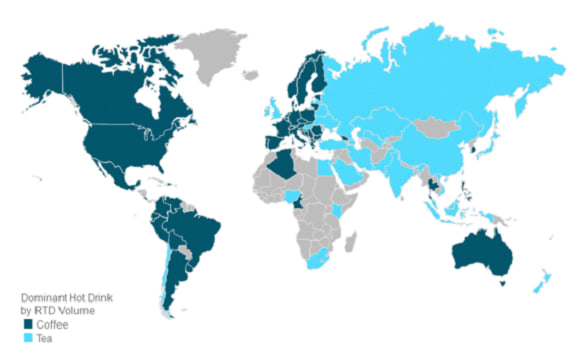トランプ大統領はサプライズ発言を連発する。彼のワンマンショーが世界を惑わせ、主導する。突然金氏とDMZ で会うという。日韓で反応も異なる。特に仲介役の文大統領の存在感が相反する。
韓国ではDMZというが日本では38度線の地点と言う。休戦線と38度線は曲線「S」と直線「ー」と異なるので区別して使ってほしい。昨日有名なキャスターも38線と言っていた。メディアが言えばそれで決まるのだろうか。慰安婦と挺身隊も混同して定着した。「38度線」と休戦線は歴史と意味が異なる。区別して欲しい。
広島大学から『アジア社会文化研究』20号が届いた。当時講義中、院生たちにハーバード大学の勉強ぶりを紹介しながらスタディグループを勧めたのが受け入れられ、私が2000年研究雑誌をデザインして発行した。その芽生えから20年、表紙などそのままの20号になって学会でも評価が高い。多くの教え子の活躍も嬉しい。自慢話に耐えられない人も我慢して欲しい。水羽信男先生に感謝する。