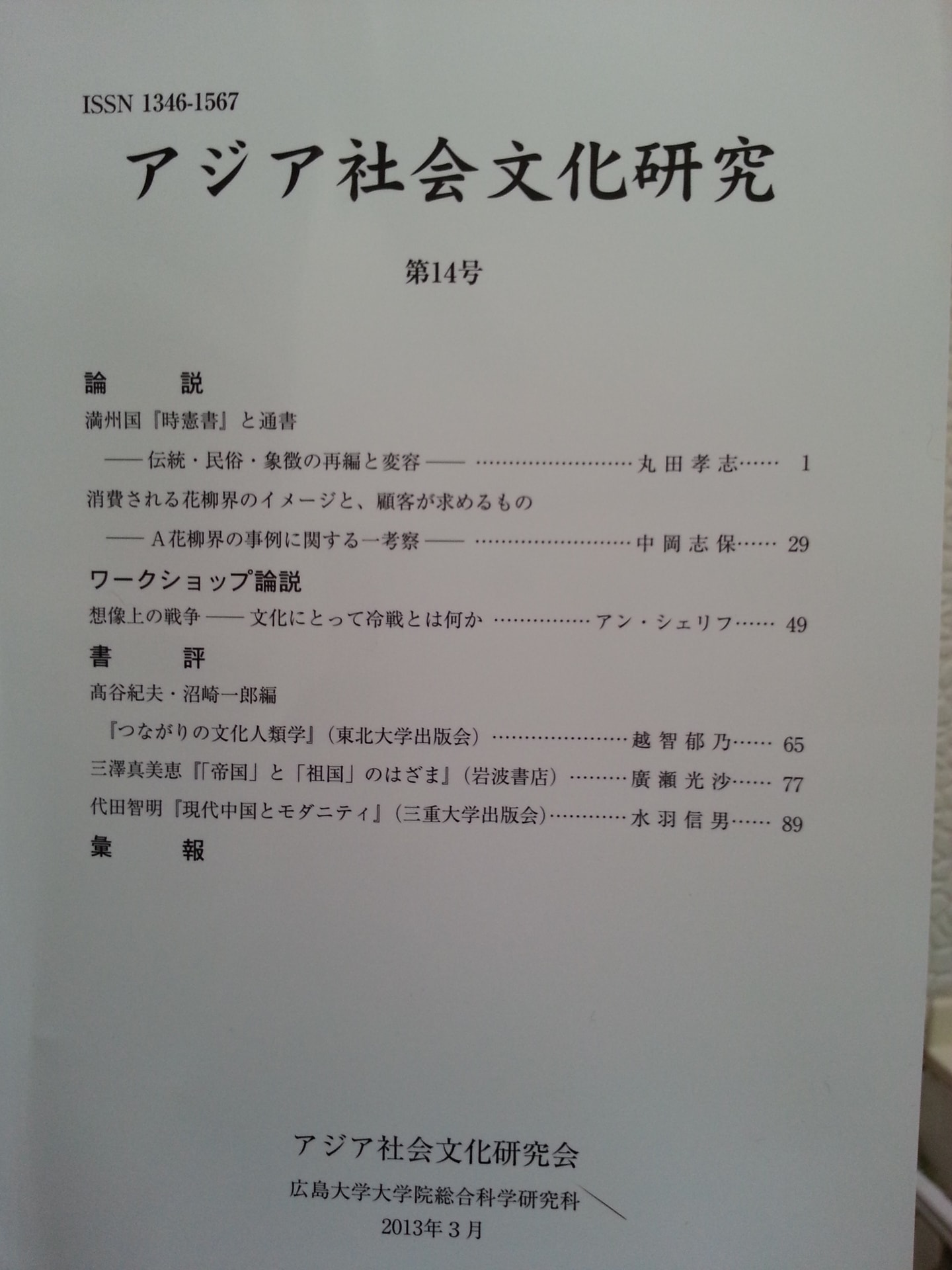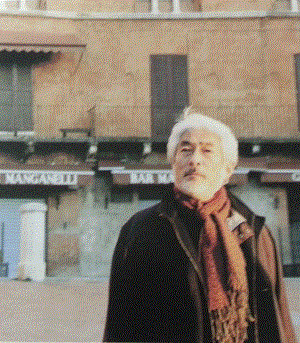冬と夏を往来するようなこの頃ではあるが季節は確実に変わっている。海辺のホームセンターの室内の天頂の処に2個の燕の巣を見つけたのが2週間ほど前であった。昨日寄って見上げた時には孵化したそれぞれ一羽の小鳥が巣立ちに向けて練習なのか羽ばたいていた。店の閉店時間にどうして出入りするのだろうか。ドアの閉開と燕の出入りのことについて店員に聞いた。日が暮れる頃親鳥が帰ってからドアが閉まり、店の開業と同時に日課が始まるという。安心した。
ツバメは昔私の生まれ故郷の農家の板の間の上に毎年巣を作ったことを思い出す。ツバメに障るとマラリアになるといわれ保護されたのである。東南アジアなどではツバメは険しい絶壁に巣を作ると言う。その巣を料理に使う話がある。そこではツバメが人との距離を持つのは当然であろう。
日本や韓国ではツバメは家禽ではない野生鳥としては最も人に親しいのではないだろうか。人はツバメの行動をよく観察している。韓国では「川水に擦れ触れたツバメ」を美女に比喩する。西洋では素晴らしい紳士に比喩するのか「燕尾服」がある。ツバメは夫婦が子供を産んで育てていく家族のモデルを人間に見せているようである。天頂の巣の子鳥は間もなく巣立ち、家族連れで南へ渡るだろう。そして懐かしい故郷へ戻る。国境なしに「渡り鳥」として生きる「越境の生き方」を我々に教えてくれるているのではないだろうか。
ツバメは昔私の生まれ故郷の農家の板の間の上に毎年巣を作ったことを思い出す。ツバメに障るとマラリアになるといわれ保護されたのである。東南アジアなどではツバメは険しい絶壁に巣を作ると言う。その巣を料理に使う話がある。そこではツバメが人との距離を持つのは当然であろう。
日本や韓国ではツバメは家禽ではない野生鳥としては最も人に親しいのではないだろうか。人はツバメの行動をよく観察している。韓国では「川水に擦れ触れたツバメ」を美女に比喩する。西洋では素晴らしい紳士に比喩するのか「燕尾服」がある。ツバメは夫婦が子供を産んで育てていく家族のモデルを人間に見せているようである。天頂の巣の子鳥は間もなく巣立ち、家族連れで南へ渡るだろう。そして懐かしい故郷へ戻る。国境なしに「渡り鳥」として生きる「越境の生き方」を我々に教えてくれるているのではないだろうか。