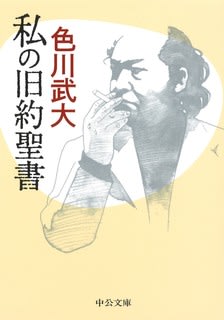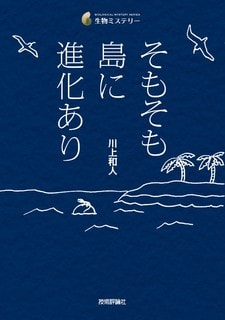色川武大 「私の旧約聖書」読了
著者は、阿佐田哲也というペンネームで、「麻雀放浪期」を書いた人である。この本は本名で書かれている。ちなみにペンネームの由来は、麻雀をやってて夜が明けてくると、「朝だ、徹夜だ。」とよく言っていたというところかららしい。
およそ信仰からは程遠いギャンブルの世界で名を成したひとからみる旧約聖書とはいったいどんなものであったのかという興味で手に取ってみた。
大部分はモーセ以降、再びイスラエルの民がカナンの地を追われるまでについていろいろ書かれている。
僕みたいな凡人は、聖書の中の登場人物は、そういう人なのだからそういう人なのだとしか思わなくて、プロファイリングみたいなことをしようなんて考えたこともなかったけれども、著者はまず、モーセというひとはどんな性格の人であったのだろうかというところからはじめている。
モーセはエジプトで奴隷にされていたイスラエル人のひとりだが、赤ちゃんの頃川に捨てられたところを王の娘に拾われて、そこで大きくなった。だから創世記に出てくる人々とは少しタイプを異にしている。善意の人であり、品格も高く、個人のスケールの中ではまことに申し分のない一生を送ることのできる人であったけれども、それだけに、自分の手に余る大きな事に対しては、内向的、傍観的になってしまう。
いわゆるナルシストだ。自分のバランスが崩れることを極端に嫌がり、自分の美意識の枠に入りきらないようなことにはしり込みしてしまう。
と分析している。
そんなモーセの前に神エホヴァが現れて、「私はお前の神である。民を率いてイスラエルへ戻れ。そこで幸せにしてやるからずっと私を奉り続けろ。」と言われてもなんでその役が僕なの??みたいな感じで、なかなかそれを受け入れることができないのだ。自分の中にはすでに自分の考えがあるのだから。
そして、イスラエルの地を得た民はそこで何世代も続いてゆくのだが、およそ神が必要なときは危機が訪れるときで、食べ物が豊富にあるときや敵が襲ってこないときは民も神様を崇めることを怠けるようになる。そうなると神様は困るのである。だからイスラエルの民をいじめて、やっぱり神様はいいだろうと再び崇めさせるように仕向ける。旧約聖書の列王記という項目にはひたすらその繰り返しが書かれているそうだ。
そういう物語のなかに著者は何を見たのか。筆者も小さい頃のコンプレックスからやはり自分の中に神を持ってしまった。そうなると他者との距離がどんどん遠くなる。集団の世界に入れなくなる。モーセは神の指示に従ってイスラエルを目指すわけだけれども、その葛藤はいかほどのものだっただろうかと、こういう見解になる。やはり自分ならモーセ以上にしり込みしてしり込みしてしまうのではないかと。
そして著者はひょんなことからギャンブルの世界に入り込むのであるが、ギャンブルは場が終わるごとにシャッフルしてカードが配りなおされる。それを列王記になぞらえている。
そこのところは勝負事にはまったくわからないのだが、著者がモーゼになぞらえている部分はこれはぼく自身のことでもあるのではないだろうかと思えてくるのである。
だから世間とうまく折り合いをつけることができないのだ・・・。
著者は、阿佐田哲也というペンネームで、「麻雀放浪期」を書いた人である。この本は本名で書かれている。ちなみにペンネームの由来は、麻雀をやってて夜が明けてくると、「朝だ、徹夜だ。」とよく言っていたというところかららしい。
およそ信仰からは程遠いギャンブルの世界で名を成したひとからみる旧約聖書とはいったいどんなものであったのかという興味で手に取ってみた。
大部分はモーセ以降、再びイスラエルの民がカナンの地を追われるまでについていろいろ書かれている。
僕みたいな凡人は、聖書の中の登場人物は、そういう人なのだからそういう人なのだとしか思わなくて、プロファイリングみたいなことをしようなんて考えたこともなかったけれども、著者はまず、モーセというひとはどんな性格の人であったのだろうかというところからはじめている。
モーセはエジプトで奴隷にされていたイスラエル人のひとりだが、赤ちゃんの頃川に捨てられたところを王の娘に拾われて、そこで大きくなった。だから創世記に出てくる人々とは少しタイプを異にしている。善意の人であり、品格も高く、個人のスケールの中ではまことに申し分のない一生を送ることのできる人であったけれども、それだけに、自分の手に余る大きな事に対しては、内向的、傍観的になってしまう。
いわゆるナルシストだ。自分のバランスが崩れることを極端に嫌がり、自分の美意識の枠に入りきらないようなことにはしり込みしてしまう。
と分析している。
そんなモーセの前に神エホヴァが現れて、「私はお前の神である。民を率いてイスラエルへ戻れ。そこで幸せにしてやるからずっと私を奉り続けろ。」と言われてもなんでその役が僕なの??みたいな感じで、なかなかそれを受け入れることができないのだ。自分の中にはすでに自分の考えがあるのだから。
そして、イスラエルの地を得た民はそこで何世代も続いてゆくのだが、およそ神が必要なときは危機が訪れるときで、食べ物が豊富にあるときや敵が襲ってこないときは民も神様を崇めることを怠けるようになる。そうなると神様は困るのである。だからイスラエルの民をいじめて、やっぱり神様はいいだろうと再び崇めさせるように仕向ける。旧約聖書の列王記という項目にはひたすらその繰り返しが書かれているそうだ。
そういう物語のなかに著者は何を見たのか。筆者も小さい頃のコンプレックスからやはり自分の中に神を持ってしまった。そうなると他者との距離がどんどん遠くなる。集団の世界に入れなくなる。モーセは神の指示に従ってイスラエルを目指すわけだけれども、その葛藤はいかほどのものだっただろうかと、こういう見解になる。やはり自分ならモーセ以上にしり込みしてしり込みしてしまうのではないかと。
そして著者はひょんなことからギャンブルの世界に入り込むのであるが、ギャンブルは場が終わるごとにシャッフルしてカードが配りなおされる。それを列王記になぞらえている。
そこのところは勝負事にはまったくわからないのだが、著者がモーゼになぞらえている部分はこれはぼく自身のことでもあるのではないだろうかと思えてくるのである。
だから世間とうまく折り合いをつけることができないのだ・・・。