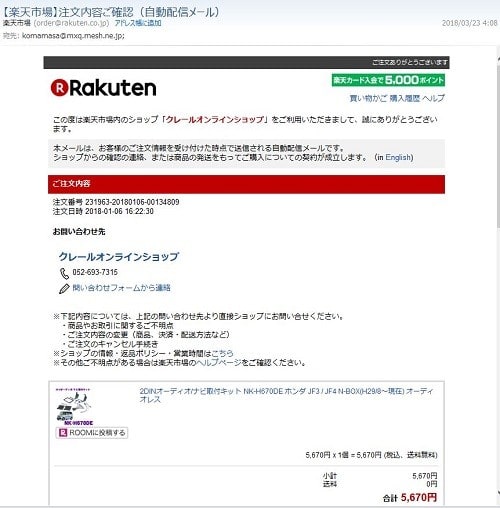掛川市には、新幹線駅に加えて東名高速道路の掛川インター、そして第二東名高速の森・掛川インターという、ほぼ現代日本の文明社会の最たるような施設があって、現代の便利社会の最たるものに感じられます。
ところがこの第二東名の森・掛川インターを降りてから車で走ること30分。掛川氏の北東部奥深く、「炭焼」という地区にあるのが「明ケ島(みょうがしま)キャンプ場」です。
ここはもう携帯電話の電波も届かない地区で、下界との連絡はできないし下界からも連絡が来ません。
私が十数年前にいたときにもこのキャンプ場はありました。当時はいかにも山奥の素朴なキャンプ場でしたが、便利なキャンプ場が数ある中で、そんな遠くて電波も届かないようなところでは人気も出るはずがありません。
ところが、「電波の届かない」ということを「便利・不便」軸で考えるのではなく、「それでいい・それじゃいやだ」軸で考えれば、「それでもいい」と考える人だけが来てくれればそれでも良いのです。
いや、それだけではありません。リニューアルの一つとして、川辺に張り出したウッドデッキが二つできました。大きい方のデッキは、まあるく作ってあるので「満月」と呼び、小さい方は半円に近いので「半月」と呼んでいます。
まだ開業シーズンは始まっていないのですが、ここのリニューアルをプロデュースしたマツヤマ君から、「一度ここでキャンプをしてアマゴ釣りをしましょうよ」と言われていたので、意を決してやってきました。
せっかく珍しいウッドデッキでのキャンプなので、東京に住む娘も「新幹線でおいでよ」と呼び寄せて、久々の家族キャンプ。
昨日までの寺巡りも個人的には大満足ですが、実はこれこそが今回の静岡の旅のメインイベントなのです。
◆
キャンプ場は、うねうねと左右に曲がり、上っては下る山道を延々と走ってようやく到着します。いやあ、遠い遠い。
看板を見落とすと、途中で「この道で本当にいいのかな?」と不安になります。
ようやく到着したキャンプ場は、入り口近くに二つのウッドデッキがあって、ワクワク感が広がります。

案内をしてくれたマツヤマ君がタープを張ってくれます。ウッドデッキは、道路から川の上に張り出して作られていて、タープは周りの杉の木を利用して張ります。

金属ポールすら使わずに、必要なら落ちている杉の枝を使って用を足せば良い。ワイルドだなー。
あとはイスとテーブルとカセットコンロをセットして夜の準備は万端です。
◆
やがて、一緒にキャンプをしてくれる友達が三々五々集まってきて、だんだんにぎやかに。初めて会う方もいますが、次に会うときはキャンプ仲間と呼べるでしょう。
ひと通りキャンプの用意ができたところで時刻は17時過ぎ。
「ちょっとだけ釣りをしてみたい」と言って、川に出て見たものの、夕方の気温はもう低くて憧れのアマゴは顔を見せてくれません。再チャレンジは明日の朝です。

さすがにこの時期の山の奥は底冷えする寒さですが、鍋を囲みながら飲むお酒に助けられて、笑いの絶えない夜になりました。

◆
さて、宮沢賢治の童話『注文の多い料理店』は、山奥に紛れ込んだ二人の漁師が、料理店から様々な求めを受けるお話。
店からの注文は、「髪をとかせ」、「靴の泥を落とせ」、挙句の果ては「金属製のものを全てはずせ」といった不可思議なものでしたが、端から好意的に考えると、それなりに理由がありそうなものでしたが、実はどんどん危ない目に近づいていきます。
ここ明ヶ島も、注文の多いキャンプ場かもしれません。
スピーカーから流れる音は禁止です。音は、川のせせらぎとバーナーがゴーと燃える音、そしてカエルや鳥の鳴き声で良いのです。
夜の街灯もほとんどありません。サービスだと思って回りを照らすよりも、自分のライトだけのほうが夜の星が美しく見えます。
キャンプ場からの注文は「センス良く満喫してくださいね」という事に尽きるのです。それは、豊かな時間に近づくための優しい注文と言えそうです。

翌朝のアマゴチャレンジ、狙った一投に一匹のアマゴが見事に食いついてくれましたが、残念ながら最後にばらしてサヨウナラ。
「会いたければ、またいらっしゃい」
うーん、目の前でスルリと逃げたアマゴには、また会いに来なくてはなりますまい。
キーワードは"デジタル・デトックス"。
不便は不幸じゃないね。不便が幸せになる時間でした。