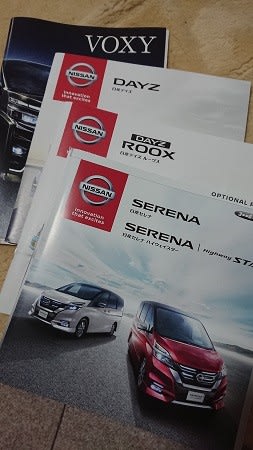ちょっとした飲み会がススキノであって、帰りはタクシーを使いました。
最近のタクシーは、前の助手席のヘッドレストの裏にタブレットが付いていて、ニュースや動画が観られるだけでなく、支払いもこの機械で行えます。
「Paypayは使えますか?」と興味半分に聞いてみたところ、「使えますよ。クレジットカードはもちろんですし、そのほかにもパスモやスイカなどの交通系カードも使えます」とのことで、こちらのタクシー会社はなかなか先進的な取り組みをしています。
◆
さて、我が家についたので支払いをクレジットカードで行おうと、カードを運転手さんに渡したところ、「あ、うちはご自身でやっていただくことになっているんです」と言われました。
「ええ?どうしたら良いのですか?」
「機械の横にクレジットカードを差し込むところがありますから、そこにカードを差し込んでください」

なるほど、横に差し込んで…、「あとはどうしますか」
「金額がそれでよろしければ、支払いのところを押してください、それで支払い終了です」
なるほど、運転手さんがカードを預かるというのも、セキュリティを考えるとリスクのある危険なことなのかもしれません。
自分で金額を確認して、自分でカードを差し込んで自分で支払いを完了させる。それがやはり一番安全な手続きと言えるでしょう。
しかも運転手さんが余計な機械の扱いをしなくても良いので、運転に集中をしてもらうことができそうです。
あらゆるカードが使えてどんどん便利になりますが、時代についてゆくのはなかなか大変です。
運転手さんの労働内容が軽減するような経営者の判断も求められそうです。