北海道は中国の映画で紹介されて以来、中国の人たちにとっての一度は行ってみたい憧れの観光地となりました。
そんな話題があったのでご紹介します。
---------- 【ここから引用】 ----------
【中国ブログ】美食に誘われて北海道へ、中国人のグルメツアー 2009/11/30(月) 22:25
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=1130&f=national_1130_052.shtml

2008年末に公開された映画『非誠勿擾』はインターネットで知り合った中国人男女が、北海道へと旅行にでかけ、恋に落ちるラブコメディ作品だ。中国大陸での興行成績は3億4000万元(約43億円)を突破する大ヒットを記録し、中国に『北海道ブーム』を巻き起こした。
北海道道観光振興機構もこのチャンスを逃すまいとばかりに、上海などで北海道観光をPRするセミナーを開催し、中国人観光客の取り込みに動いているが、実際に北海道を訪れ、北海道のグルメを堪能したという中国人ブロガーが自らのブログにグルメ体験記を綴っている。
ブロガーは北海道で体験したグルメの写真を掲載しながら、「北海道はグルメ好きの楽園だ」と語り、「新千歳空港は素晴らしい空港だ。海外ブランドの免税店は少ないものの、さまざまなグルメを提供するレストランが集結し、まるで北海道の美食を凝縮したかのような空港だからだ」と評価した。
まずブロガーは、北海道を訪れたなら寿司(すし)を食べずに帰国することはできないと語り、実際に食べた感想として、「口に入れた途端に溶けてしまうような濃厚なウニの寿司は忘れられない」と綴る。続けて、旭川ラーメンや札幌ラーメン、カニなど、北海道ならではのグルメを写真とともに紹介し、北海道グルメツアーの思い出を語った。
これに対し、ブログには多くの中国人ネットユーザーからコメントが寄せられている。「世界広しと言えども、私は北海道が最も好きだ。北海道の美しい大自然や豊富でおいしいグルメは最高だ」、「私も北海道にずっと行きたいと思っていた」、「ブログを見ているうちに涎(よだれ)が出てきた」など、中国人が北海道に対して大きな興味を持っていることがうかがえた。(編集担当:畠山栄)
---------- 【引用ここまで】 ----------
私も札幌にいた頃、地図を見ながら困った人を見かけたら声を掛けるように心がけていました。
あるとき、市内の中心地でホテルへの行き方が分からず困っている人を見かけたので声を掛けました。見せてもらったパンフレットに電話番号があったのでホテルへ電話して行き方を尋ねたのですが、そのホテルは割と離れたところへ専用バスで案内するというシステムでした。
そのバス停の位置がとても分かりづらかったので困っていたのです。しかもバスが来るのは1時間に2本!
バスを一緒に待ってはいられなかったので、バス停を探し当てて、「ここのバス停に15分後にバスが来ますからね」と教えて去ろうとしたら、お礼にと富良野で買ったらしいラベンダーのドライフラワーをくれました。
お国は台湾とのこと。こういうちょっとした親切が地域の魅力向上に繋がると良いのですが。
国際観光都市、国際観光島を目指してがんばれ北海道!
そんな話題があったのでご紹介します。
---------- 【ここから引用】 ----------
【中国ブログ】美食に誘われて北海道へ、中国人のグルメツアー 2009/11/30(月) 22:25
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=1130&f=national_1130_052.shtml

2008年末に公開された映画『非誠勿擾』はインターネットで知り合った中国人男女が、北海道へと旅行にでかけ、恋に落ちるラブコメディ作品だ。中国大陸での興行成績は3億4000万元(約43億円)を突破する大ヒットを記録し、中国に『北海道ブーム』を巻き起こした。
北海道道観光振興機構もこのチャンスを逃すまいとばかりに、上海などで北海道観光をPRするセミナーを開催し、中国人観光客の取り込みに動いているが、実際に北海道を訪れ、北海道のグルメを堪能したという中国人ブロガーが自らのブログにグルメ体験記を綴っている。
ブロガーは北海道で体験したグルメの写真を掲載しながら、「北海道はグルメ好きの楽園だ」と語り、「新千歳空港は素晴らしい空港だ。海外ブランドの免税店は少ないものの、さまざまなグルメを提供するレストランが集結し、まるで北海道の美食を凝縮したかのような空港だからだ」と評価した。
まずブロガーは、北海道を訪れたなら寿司(すし)を食べずに帰国することはできないと語り、実際に食べた感想として、「口に入れた途端に溶けてしまうような濃厚なウニの寿司は忘れられない」と綴る。続けて、旭川ラーメンや札幌ラーメン、カニなど、北海道ならではのグルメを写真とともに紹介し、北海道グルメツアーの思い出を語った。
これに対し、ブログには多くの中国人ネットユーザーからコメントが寄せられている。「世界広しと言えども、私は北海道が最も好きだ。北海道の美しい大自然や豊富でおいしいグルメは最高だ」、「私も北海道にずっと行きたいと思っていた」、「ブログを見ているうちに涎(よだれ)が出てきた」など、中国人が北海道に対して大きな興味を持っていることがうかがえた。(編集担当:畠山栄)
---------- 【引用ここまで】 ----------
私も札幌にいた頃、地図を見ながら困った人を見かけたら声を掛けるように心がけていました。
あるとき、市内の中心地でホテルへの行き方が分からず困っている人を見かけたので声を掛けました。見せてもらったパンフレットに電話番号があったのでホテルへ電話して行き方を尋ねたのですが、そのホテルは割と離れたところへ専用バスで案内するというシステムでした。
そのバス停の位置がとても分かりづらかったので困っていたのです。しかもバスが来るのは1時間に2本!
バスを一緒に待ってはいられなかったので、バス停を探し当てて、「ここのバス停に15分後にバスが来ますからね」と教えて去ろうとしたら、お礼にと富良野で買ったらしいラベンダーのドライフラワーをくれました。
お国は台湾とのこと。こういうちょっとした親切が地域の魅力向上に繋がると良いのですが。
国際観光都市、国際観光島を目指してがんばれ北海道!











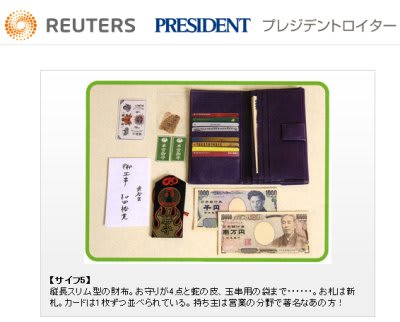



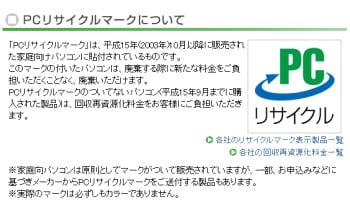










 以前、「北海道大好き~万年カレンダー」という記事をご紹介しました。
以前、「北海道大好き~万年カレンダー」という記事をご紹介しました。








