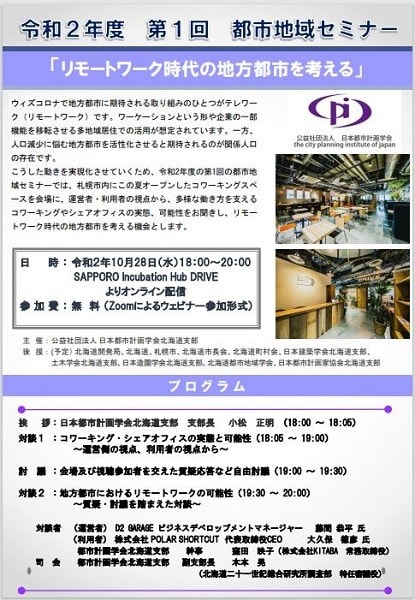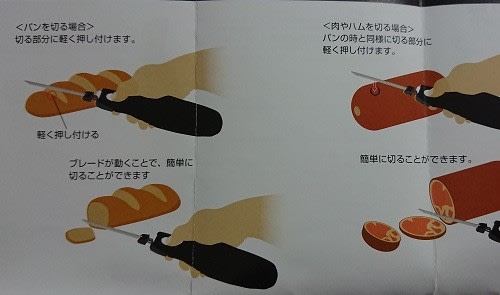先日も行った歯医者さん。
歯磨きは上手な方ですよ、とおだてられていい調子になったところで歯の悩みを相談しました。
「歯磨きをするのは良いのですが、歯茎が下がって歯の根っこがだんだん出てくるのはなんとかなりませんか」
そういうと若い歯科衛生士さんは優しく「あ~、それって一生懸命磨く方にそういう傾向がありますね」と言いつつも、「でもそれを恐れて磨かないと歯の汚れは取れないので、むずかしいですね」と思案顔。
また、「歯茎が下がるというのは歯茎が締まっている証ですし、逆に歯茎が下がっていない中には腫れて不健康は歯茎の方もいますしね…」とも。
そして「そうだ、小松さん、歯磨きはどうやっていますか?歯ブラシを5本指でがっちり握って磨いてはいないでしょう。それだと歯茎に力がかかりすぎるんですよ」

「僕は鉛筆のように3本持ちです」

「ははあ、なるほど。実は歯磨きの適切な力加減って、150g~200gと言われていて、これって実際にやってみるととても軽いんです」
そして「さらに力をかけない磨き方のためには2本指で持つという方法もありますよ」と驚きの磨き方を教えてくれました。
「2本指ですか?」
「そう、2本指」

これではただ歯ブラシを持っているというよりも、指で挟んでいるだけです。
でもこれが歯ブラシを軽く持つコツなんだと。
歯磨きに一生懸命になるあまり、歯茎を傷めてしまってはやりすぎの部類です。
何事も正しいやり方を身に着けたいものですね。