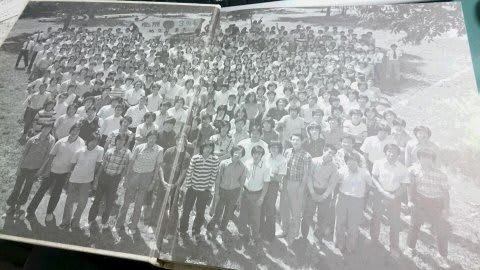本当ならば今頃は九州を旅行していたはずのですが、先週来の熊本県を中心とする地震のために今回はその旅行を中止したのでした。
しかしながら折角の休養を活かしてどこかに旅行に行きたいという思いは募るばかり。九州で合流しようと示し合わせていた次女も「どこかへ行きたいね」というので、彼女が札幌へ帰ってきたタイミングを見計らって今日から函館~松前~ニセコをめぐる旅に出ました。
人はどうしても旅に出たいという気持ちが満ちるときがあるようです。
娘のたっての希望は「函館のラッキーピエロでハンバーガーを食べたい」というもの。
テレビコマーシャルは打たずに口コミでファンを増やしてきたラッキーピエロの存在は、東京に住む娘も気になっていたようです。
ちょうどお昼時に森町のお店に飛び外国人の込んでハンバーガーを注文しましたが、予想以上のボリュームに驚きました。


私はお店のナンバーワン人気の「チャイニーズチキンバーガーセット」にしたのですが、大の大人でもお腹がいっぱいになりました。
台湾か中華系と思われるグループも列に並んでいて、爆買いならぬ爆食を大いに楽しんでいました。外国人観光客にも知られてきたんですねえ。
ラッキーピエロさんは地元では"ラッピ"と呼ばれているらしいですよ。知らなかった。
◆
そのあとは久しぶりに大沼へやってきて、大沼を一周。有名観光地でもそうそう何度も来るものではないので、「来たことがある」以外は昔の記憶がほとんどなくなっていました。

豊かな水面の湖面と駒ヶ岳とを有する美しい景観を誇る大沼国定公園ですが、観光の充実という面から見るとちょっと寂しいものを感じました。
沼を中心とした面積は大きいのですが、ではここでどういうことをして時間を費やして楽しめるかという観光コンテンツがあまり充実していない印象をもったのです。
湖面の遊覧船、手漕ぎボート、レンタル自転車に自然散策とあとはヘラブナ釣りを少々といったところでしょうか。
まだまだあるのかもしれませんが、フィールドの広さをうまく生かしきれないのは国定公園ということの制約もそうさせるのでしょうか。
「ではどうしたらよいと思うか?」と問われたらどうこたえましょうか。わが身に置き換えると(悩ましいなあ)と感じました。
◆
それに対して予想以上に面白かったのが大沼の後に行った「道の駅しかべ間歇泉公園」のほう。
十分に一度くらいの頻度で熱水を噴き上げる間歇泉と、それを見ながら足湯に浸かれるというのは旅の疲れを癒す効果抜群。間歇泉の見物に大人300円と有料ではありますが、タオルも貸してくれる足湯にも入れるので損はありません。

おまけに野菜を買って温泉の熱で蒸して食べるという企画も他にはないもので、ここならではの差別化のためのエッジの効いた面白いアイディアです。
道の駅も数が増えてきて、単なる休憩・情報提供&地域の物産販売というだけでは差別化をして特徴を売ることが難しくなってきました。
地域の財産にさらに磨きをかけて、他にはない特徴を前面に出して人気を博するようなものに仕立て上げるためにはそれなりのデザイン力が必要で、プロの力を大いに借りるべきでしょう。
昔の成功体験にしがみつくだけではなく新しい時間の過ごし方を提案する。それも地域の誇りを大切にした形で、来訪者の共感が得られるような観光拠点の作り方はどうしたらよいか。
楽しみながらもいろいろ考えさせられる一日でした。やはり地域の定点観測は大切ですね。
おまけに北海道新幹線の新函館北斗駅を見てきました。いずれ一度は乗って見なくては。