台風の影響で荒れた天気の関東地方。大変な天気でした。
さて、現代社会は食べなくて死ぬ人はいなくて、食べて死ぬ人の方が多い時代になりました。
---------- 【以下引用】 ----------
肥満は脳を萎縮させるらしい!?
http://digitallife.jp.msn.com/article/article.aspx/genreid=121/articleid=452012/
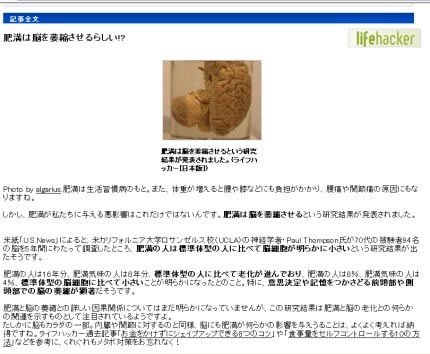
肥満は脳を萎縮させるという研究結果が発表されました。(ライフハッカー[日本版])
Photo by algarius.肥満は生活習慣病のもと。また、体重が増えると腰や膝などにも負担がかかり、腰痛や関節痛の原因にもなりますね。
しかし、肥満が私たちに与える悪影響はこれだけではないんです。肥満は脳を萎縮させるという研究結果が発表されました。
米紙「U.S.News」によると、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の神経学者・Paul Thompson氏が70代の被験者94名の脳を5年間にわたって調査したところ、肥満の人は標準体型の人に比べて脳細胞が明らかに小さいという研究結果が出たそうです。
肥満の人は16年分、肥満気味の人は8年分、標準体型の人に比べて老化が進んでおり、肥満の人は8%、肥満気味の人は4%、標準体型の脳細胞に比べて小さいことが明らかになったとのこと。特に、意思決定や記憶をつかさどる前頭部や側頭部での脳の萎縮が顕著だそうです。
肥満と脳の萎縮との詳しい因果関係についてはまだ明らかになっていませんが、この研究結果は肥満と脳の老化との何らかの関連を示すものとして注目されているようですよ。
たしかに脳もカラダの一部。内臓や関節に対するのと同様、脳にも肥満が何らかの影響を与えうることは、よくよく考えれば納得ですね。ライフハッカー過去記事「お金をかけずにシェイプアップできる8つのコツ(http://www.lifehacker.jp/2009/06/090623_8.html)」や「食事量をセルフコントロールする10の方法」(下記参照http://www.lifehacker.jp/2009/07/090726diettips10.html)などを参考に、くれぐれもメタボ対策をお忘れなく!
【食事量をセルフコントロールする10の方法】
体重を減らそうとしているにせよ、自分の「食餌療法」をうまく成功させているにせよ、ダイエットのキー・ポイントは「食べる量」です。と、いうことは食べ過ぎないようにするために「ちょうど良い分量」をどうやってコントロールするか? 知りたいですよね。
「Reader's Digest」では、食べる量をコントロールするための10の方法を紹介しています。
1.それが本当に食べたいのかよーく考える。10分待ってみよう。
2.お皿の中身をカンペキにキレイに食べつくすのは、もうやめよう。
3.食べ物が入っている袋・箱・パックから直接食べるのはやめよう。
4.たくさんお皿にないと満足できない? じゃお皿はちょっぴりドレッシングの山盛り野菜かスープで満たそう。
5.夕食には巨大なディナー皿じゃなくてサラダ皿を使おう。
6.何かを注文するときには、常に「Sサイズで」を決まり文句にしよう。
7.マルチパックやファミリーサイズはやめて、1人分のシングル・サイズを買おう。
8.栄養成分表示のラベルをまず読もう。
9.食べる前に「食べない分」を取り分けておこう。
10.フレッシュ・フルーツで食事の最後を締めくくろう。
---------- 【引用ここまで】 ----------
こんな話はいくらでも転がっているのですが、それでもなお出てくるというのは、それだけ実践出来ない人が多いと言うことなんでしょうね。
今日で8月も終わり。9月になると秋の味覚も増えますぞ~。本能と食欲をどれだけ押さえられるでしょうか。
さて、現代社会は食べなくて死ぬ人はいなくて、食べて死ぬ人の方が多い時代になりました。
---------- 【以下引用】 ----------
肥満は脳を萎縮させるらしい!?
http://digitallife.jp.msn.com/article/article.aspx/genreid=121/articleid=452012/
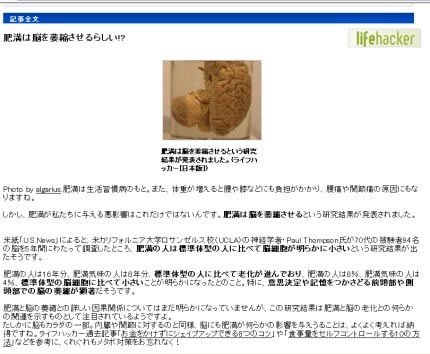
肥満は脳を萎縮させるという研究結果が発表されました。(ライフハッカー[日本版])
Photo by algarius.肥満は生活習慣病のもと。また、体重が増えると腰や膝などにも負担がかかり、腰痛や関節痛の原因にもなりますね。
しかし、肥満が私たちに与える悪影響はこれだけではないんです。肥満は脳を萎縮させるという研究結果が発表されました。
米紙「U.S.News」によると、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の神経学者・Paul Thompson氏が70代の被験者94名の脳を5年間にわたって調査したところ、肥満の人は標準体型の人に比べて脳細胞が明らかに小さいという研究結果が出たそうです。
肥満の人は16年分、肥満気味の人は8年分、標準体型の人に比べて老化が進んでおり、肥満の人は8%、肥満気味の人は4%、標準体型の脳細胞に比べて小さいことが明らかになったとのこと。特に、意思決定や記憶をつかさどる前頭部や側頭部での脳の萎縮が顕著だそうです。
肥満と脳の萎縮との詳しい因果関係についてはまだ明らかになっていませんが、この研究結果は肥満と脳の老化との何らかの関連を示すものとして注目されているようですよ。
たしかに脳もカラダの一部。内臓や関節に対するのと同様、脳にも肥満が何らかの影響を与えうることは、よくよく考えれば納得ですね。ライフハッカー過去記事「お金をかけずにシェイプアップできる8つのコツ(http://www.lifehacker.jp/2009/06/090623_8.html)」や「食事量をセルフコントロールする10の方法」(下記参照http://www.lifehacker.jp/2009/07/090726diettips10.html)などを参考に、くれぐれもメタボ対策をお忘れなく!
【食事量をセルフコントロールする10の方法】
体重を減らそうとしているにせよ、自分の「食餌療法」をうまく成功させているにせよ、ダイエットのキー・ポイントは「食べる量」です。と、いうことは食べ過ぎないようにするために「ちょうど良い分量」をどうやってコントロールするか? 知りたいですよね。
「Reader's Digest」では、食べる量をコントロールするための10の方法を紹介しています。
1.それが本当に食べたいのかよーく考える。10分待ってみよう。
2.お皿の中身をカンペキにキレイに食べつくすのは、もうやめよう。
3.食べ物が入っている袋・箱・パックから直接食べるのはやめよう。
4.たくさんお皿にないと満足できない? じゃお皿はちょっぴりドレッシングの山盛り野菜かスープで満たそう。
5.夕食には巨大なディナー皿じゃなくてサラダ皿を使おう。
6.何かを注文するときには、常に「Sサイズで」を決まり文句にしよう。
7.マルチパックやファミリーサイズはやめて、1人分のシングル・サイズを買おう。
8.栄養成分表示のラベルをまず読もう。
9.食べる前に「食べない分」を取り分けておこう。
10.フレッシュ・フルーツで食事の最後を締めくくろう。
---------- 【引用ここまで】 ----------
こんな話はいくらでも転がっているのですが、それでもなお出てくるというのは、それだけ実践出来ない人が多いと言うことなんでしょうね。
今日で8月も終わり。9月になると秋の味覚も増えますぞ~。本能と食欲をどれだけ押さえられるでしょうか。

























