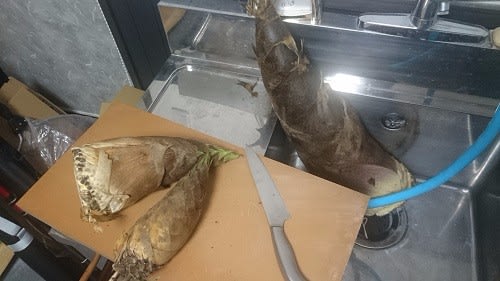掛川のもはや名物イベントになっている「ゆるゆる遠州2017春」に参加しました。
掛川の天候は曇り時々晴れ。最高気温は19℃とのことで、道東では雪が降っているような北海道と比べるととても暖かいのですが、この時期の静岡にしてはちょっと寒いかな。
今年はお茶やその他の作物も例年より一週間ほど遅れているようで、ここでも春は気温が低めで推移したようです。
しかし自転車部隊にしてみれば、走っても汗をかかないちょうどよい気温。快適な季節でした。
ツアーにエントリーするのに、自転車で掛川市役所に集合しましたが、そこここにかつての友達や知り合いがいて、温かくもてなしてくれます。やっぱり昔の友達に会えるというのはうれしいものですね。

◆
さて、今回の「ゆるゆる遠州」では、掛川をスタートゴールとして、全部で7つの珠玉のコースが設定されています。
そんななか、私は自転車の経験があまりない妻を連れていくことから、一番距離が短く、かつ美味しい掛川のソウルフードが味わえるという、「Gコース:新茶摘みとローカルフード&カルチャー」と名付けられたコースを選定しました。
掛川は工業都市でありながら、一歩郊外へ出ればまだまだ農業が盛んな中小地方都市であり、隠れた農産物、名産品が結構ありますし、また企業活動の延長にある企業文化なども見られます。今回は自転車でそれらを一筆書きで走って、掛川を味わいつくそうというコースに魅力を感じました。
スタートは朝の9時くらいになり、いよいよ市役所を出発です。

まず最初のポイントは、掛川城でこちらを忍者装束のガイドさんが案内してくれました。

ガイドの内容も、歴史的な勉強をしっかりしておられて、何を聞いても聞いた以上の答えが返ってくるうえに、時々ジョークで笑いを取る余裕も。
「なぜ忍者装束でガイドをしようと思ったのですか」と訊いてみると、「普通のガイドだと飽きちゃうでしょ?でもこのスタイルなら興味と感心を引き続けられるんです」とのこと。
懐には、昔の古銭や手裏剣、まきびしなども仕込んであって、空きそうになったらそれを見せるのだそう。掛川城を話題の中心に、教養が深まるお城ポイントでした。
続いては「松浦苺農園」さんを訪ねて、こちらで苺摘み体験をさせてもらいました。こちらの苺は、ふつうは観光農園はしていなくてもっぱら農協などを通じて首都圏などへ運ばれてゆくもの。
出荷の時はまだ白いところが残っている状態で出して、店先で売られるときに調度赤くなるという頃合いの時間差があるのですが、こちらで直接摘ませてもらう分には、今まさに真っ赤で食べごろの大ぶりの苺をもいで食べるのですから、美味しくないわけがありません。


色も形も味も、「本当にイチゴだー!」という感動に出会える松浦苺農園さんでした。
◆
次が、五明という地区にある「五明の丘」ポイント。ここは地元掛川のアマチュア天文家が新しい彗星を発見して、発見者の一人に名を連ねるという栄誉を得た場所。
こちらには地元の「五明シスターズ」と呼ばれる婦人会の皆さんが、手作りの総菜やお菓子でおもてなしをしてくれて、もうこの時点でおなかはいっぱいです。


「いくら頑張って自転車を漕いでも、使うカロリーより入ってくるカロリーが多いなあ。収支が合わない(笑)」と冗談を言いながら、それでもついつい手が出ちゃうのがこういう素朴な料理ですね。
こちらではお茶の新芽を摘む、茶摘みの経験もできました。「柔らかいのは一芯二葉」と教えられて、ちょうど手でちぎれる柔らかさを感じて、「これが優しい味の新茶になる」という実感がわきました。
◆
この後に、障碍者教育によって子供たちに美術の才能を花開かせた「ねむの木学園」、雨ごいに霊験あらたかな「天桜神社」、天竜浜名湖鉄道に並行するまっすぐな直線の滑走路の道、旧東海道の松並木がそのまま残る道路などをゆるゆると走り、掛川のカルチャーを満喫です。


そして最後の極めつけは、お城の近くの駄菓子屋の「すいのや」さんでの買い食い。

スタッフからお小遣いをもらって、それで好きな駄菓子を買ってみるという趣向に、昔は「無駄遣いしちゃだめよ」と言われてなかなか駄菓子屋へ行くことができなかった私も大人買い(おおげさ)です。
こちらには始まりがいつのことかわからないくらい秘伝の汁に付け込んだ静岡おでんが有名。私と妻で黒いイワシの練り物の「黒はんぺん」と「鶏皮」を買いましたが、これにちゃんと「イワシの粉」がかかっていてまたうまさ倍増。

素朴な駄菓子の味を堪能して、今日のローカルフードのポイント巡りは全て終了。最後は市役所で、それぞれが感想を述べあって旅の無事を祝いあいました。
【率直な感想】
わたしもようやくこの「ゆるゆる遠州」に参加させてもらって、サポートのレベルの高さを強く感じました。
お客が15人くらいのチームに、ガイドは6人+サポートカーがついて、途中の荷物や買い物品を預かってくれる手際の良さ。
また、ガイドの人たちも実に献身的で、一時停止の交差点などがあると、先行して車が来ていないかを確認したうえで、我々に通っても良いという合図を送ってくれます。これでかなり安全確認の苦労が軽減されました。
そして、これだけの充実したスタッフグループを全7コースで提供できるというのは、どれだけのガイド人材のプールがあるのかと、そのすそ野の広がりに感心します。
他の自治体で、同じようにガイドサイクリングを地域の観光コンテンツとして売り出したいと思うならば、これくらいの年月をかけてガイド人材を養成し、その人たちが見つけ出した地域の宝物をネットワークするルート開発を行わなければ、もう売れると思えません。
サイクルガイドツーリズムの最高水準を知りたければ、絶対に掛川へ来るべきだと確信をしました。全国の皆さんもぜひ掛川のガイドツーリングを一度経験してください。
【最後に】
今日のツーリングが終わったところで、夜七時から、全国他都市から参加してくれた人たちによる交流会がありました。
この場で、かつて自転車雑誌サイクルスポーツの編集長を長年勤めあげ、ご自身もサイクリストの宮内忍さんが、あいさつに立ち、台湾でのサイクルツーリズムのレベルが非常に高かったことを紹介してくれました。

宮内さんはいままで、「日本にサイクリングを根付かせるためには、優れたスキルを持ったサイクリストを育成しないとダメなのだろう」とずっと思っていたのだそう。
それが台湾へ行ってみると、まだ素人同然のサイクリストでも平気でトータル900㎞などといったツアーを楽しんで完走ができている。それは「ひとえにサポートサービスの充実だったんです。それさえ完備していれば、誰でもがロングライドを楽しめるんだ、ということが本当によくわかりました」と言うのです。
自分で重たい荷物を持たなくてもそれはサポートカーが運んでくれる。タイヤがパンクすればスタッフが来て直してくれる。困ったことも解決してくれる。
そんな自転車環境が整えば、サイクリングはもっと栄えるスポーツになる、と宮内さんは言います。
こういう話を、こんな場所で直に聞けるような人のつながりがあるのも掛川ならでは。
都市の魅力を支えるのは人の力です。どれだけ多くの地域の人たちが目覚めて人材になってゆくのか。そこがカギですね。
今日は楽しい掛川の一日でした。











 【オオウバユリ】
【オオウバユリ】 【ギョウジャニンニク】
【ギョウジャニンニク】