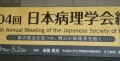
第104回の総会は名古屋です。

名古屋で大きな学会の会場と言えばここ。本当に大きなコンベンションには手狭で使いにくいし、周辺にホテルなどの施設がないため施設連携が組みにくいという難点があり、もう少し何とかならないかなあとは思います。

白鳥って周りに本当に何にもないですからね。全国から参加して頂いた方が寂しい思いをするのは、名古屋の町興しとしてはマイナスじゃないでしょうか。

向かいの中央卸売り市場は広くて立派です。しかし卸売り市場と学界場の組み合わせは使えないですね。水産学会などでは喜ばれるのかも。

そんな不満を打ち消すほど見事なヒトツバタゴの並木。

満開の白い花が雪のようです。街路樹として人気があるのでしょう。最近は増えてきた気がします。日本では自生地が遠く離れた木曽川流域と対馬だけという変わった分布をします。まあ原産は中国なんでしょう。雄花と雌花があるということですが素人が見てもわかりません。

メイン会場のセンチュリーホールです。感染症関連の腫瘍、つまり感染が原因になって発生すると見られている腫瘍の研究が世界中で進められており、その成果の一部を講演して頂きました。後半は酸化ストレスによる発病機構、と言うとわかりにくいですが、例えば鉄の過剰により発生すると推測されている癌があり、機序の解明により予防や治療への道が開けてきました。簡単には、定期的に献血することで過剰な鉄を減らせるため、ある種の癌の予防効果が期待できるということです。このような専門家向けの講演ばかりでなく、毎回一般向けの市民公開講座やオーケストラ演奏などもありますので、時間のある方は覗いてみて下さい。ちなみに来年の総会は仙台です。

講演に参加するとこんな証明書をもらえます。これは病理専門医を対象としたもので、専門医の資格を保持するためには持続して最新の知識を取り入れていないといけません。

周りに食事の施設が少ない地区なので、お昼は協賛企業提供のランチョンセミナー頼りになります。いくつか演題を選べるのですが、これは中外製薬提供の肺癌化学療法の話。

お昼の時間も惜しいので、弁当食べながら勉強と言えば聞こえがいいですかね?名古屋らしい弁当ということで天むすになったみたいです。癌の化学療法は、癌細胞のタイプ別の性質が地道に調べられてきたお陰で、初期のような大雑把な駆除的療法ではなく、本当に腫瘍細胞(実際は細胞の中の分子)だけを標的とした精度の高い療法に進化しつつあります。今回テーマになった第二世代のALK標的治療薬についても、有効性と安全性の改善は著明であり、ついに化学療法だけで癌を根絶できる時代の入り口がやって来たのかなと思わせてくれます。今のところは限られたタイプの癌にしか効かないのですが、それでもこういう話題だと弁当もおいしく頂けますね。中外製薬さん、ご馳走様でした。

病理学会の総会は春と秋の年2回です。春が本来の総会、秋は少し規模の小さい秋季特別総会。今年の秋季特別総会は名古屋駅で開催されました。主催は名古屋から少し出た藤田保健衛生大学ですが、参加者の利便を考えて名古屋駅になったのでしょう。

会場は名古屋駅前に威容を誇るトヨタのシンボル、ミッドランドスクエア…

の裏のパチンコ屋に隠れた愛知県産業労働センター、通称ウィンクあいちです。遠方よりお越しの皆様には場所がわかりにくかったかもしれません。

北側の桜通から見ると、もう少し格好良く見えます。この辺は一方通行が多くて裏通りの交通がわかりにくく、ウィンクあいちの駐車場に入ろうと思ったら、駅前からではなくてこの交差点から進入する必要があります。ウィンクの駐車場は名鉄協商が管理しており便利でかなり広いのですが、この入りにくさが祟って、ミッドランドのすぐ裏と言う絶好の場所にもかかわらず空いているという穴場。昼間の値段は周りの駐車場とあまり変わりませんが、お泊り料金が安いため、「名古屋駅まで車で行ってバスツアーに参加する」といった場合にはとても便利です。

今日は学会ネタなのに学会のことが出ていませんでした。会場内ではこれしか写真を撮っていないので、学会の雰囲気はわかりませんよね。私はこの研究に関与していませんが、出身教室のポスター発表です。
医学、医療に携わる者でアメリカ国立生物工学情報センター(National Center for Biotechnology Information、NCBI)の文献検索システム、PubMedのお世話になっていない人はいないでしょう。世界中どこからでも(通信費以外の)料金無料で膨大な学術文献を検索し、要約を読むことができます。
PubMedは図書館にこもって重い文献ファイルを1つ1つ検索したり、望みの文献がなくて他の図書館に出向いたり、という時間の空費をパソコンによる瞬時の検索に置き換えてくれたまさに魔法の道具であり、今更これなしで研究など成り立たない必須の環境です。
ところがこれは文献を出版してくれる学術誌の出版社にしてみれば利益の侵害ということになります。効率のいい文献検索ができなければ、研究者個人も、研究室も、図書館も、大学も、「もしかして必要になるかもしれない」という理由で多数、多種類の学術誌を購読しないといけないからです。今になって米国出版社協会(Association of American Publishers, AAP)が学術文献のオープン利用に反撃を強め、ついに今月、下院委員会に法案HR3699 (Research Works Act)の提出となりました。
出版側の言い分としては、委員であり法案の提出者の一人であるCAROLYN B. MALONEY下院議員(New York's 14th congressional district, Democratic Party)の簡潔な手紙が紹介されており、これがわかりやすいと思います。つまり公的資金を受けた研究経過や結果をオープンにすることはこれまで通り妨げないが、出版社がアクセプトして自前の経費を使用した出版物については、公的にオープンにすることが適当でないとしています。
それに出版社側も可能な範囲で検索サービスを提供しており、中国などアメリカ国外からのアクセスが3分の2におよぶPubMedを公的資金で維持し、結果として国外の研究者を利することは、アメリカでも研究予算が削減されてポストが減少している状況に鑑みると適当ではあるまい、ともありますね。またニューヨークとその周囲は東京と同じく出版が盛んな地域なので、公的資金を使った民業圧迫により同地域の雇用が失われることは好ましくない、とまとめています。納税者にはかなりアピールしそうですね。これがそのまま通過して法令となれば、PubMedの機能はほとんど使えなくなります。
この件はかなりのインパクトがあるため、日本でも科学技術振興機構の情報管理Webで紹介されています。ただ法案が提出されたばかりなのでまだ一般の研究者や医師には十分な認知がないと思われます。将来的にはPubMedに対する日本からのサポートの可能性も考えて、まずは問題が知られることが大事だと思います。
もっともアメリカでも研究者はPubMedの恩恵を受けてきたわけで、出版社協会の言い分がそのまま通るわけでもないでしょう。著作権で有名なLessigらがこの法案HR3699に憂慮を示しており、納税者アクセス同盟と称する団体も法案の成立阻止に向けて動いているようです。
PubMedは図書館にこもって重い文献ファイルを1つ1つ検索したり、望みの文献がなくて他の図書館に出向いたり、という時間の空費をパソコンによる瞬時の検索に置き換えてくれたまさに魔法の道具であり、今更これなしで研究など成り立たない必須の環境です。
ところがこれは文献を出版してくれる学術誌の出版社にしてみれば利益の侵害ということになります。効率のいい文献検索ができなければ、研究者個人も、研究室も、図書館も、大学も、「もしかして必要になるかもしれない」という理由で多数、多種類の学術誌を購読しないといけないからです。今になって米国出版社協会(Association of American Publishers, AAP)が学術文献のオープン利用に反撃を強め、ついに今月、下院委員会に法案HR3699 (Research Works Act)の提出となりました。
出版側の言い分としては、委員であり法案の提出者の一人であるCAROLYN B. MALONEY下院議員(New York's 14th congressional district, Democratic Party)の簡潔な手紙が紹介されており、これがわかりやすいと思います。つまり公的資金を受けた研究経過や結果をオープンにすることはこれまで通り妨げないが、出版社がアクセプトして自前の経費を使用した出版物については、公的にオープンにすることが適当でないとしています。
それに出版社側も可能な範囲で検索サービスを提供しており、中国などアメリカ国外からのアクセスが3分の2におよぶPubMedを公的資金で維持し、結果として国外の研究者を利することは、アメリカでも研究予算が削減されてポストが減少している状況に鑑みると適当ではあるまい、ともありますね。またニューヨークとその周囲は東京と同じく出版が盛んな地域なので、公的資金を使った民業圧迫により同地域の雇用が失われることは好ましくない、とまとめています。納税者にはかなりアピールしそうですね。これがそのまま通過して法令となれば、PubMedの機能はほとんど使えなくなります。
この件はかなりのインパクトがあるため、日本でも科学技術振興機構の情報管理Webで紹介されています。ただ法案が提出されたばかりなのでまだ一般の研究者や医師には十分な認知がないと思われます。将来的にはPubMedに対する日本からのサポートの可能性も考えて、まずは問題が知られることが大事だと思います。
もっともアメリカでも研究者はPubMedの恩恵を受けてきたわけで、出版社協会の言い分がそのまま通るわけでもないでしょう。著作権で有名なLessigらがこの法案HR3699に憂慮を示しており、納税者アクセス同盟と称する団体も法案の成立阻止に向けて動いているようです。
大方の医師の予想に反して責任者が逮捕された福島県大野病院産婦人科の医療事故で、「産科医が癒着胎盤による危険を予見して対応すべきだったので過失がある」という検察側の論告求刑公判が3月21日にありました。検察の立場は一貫して被告の加藤医師の医療過誤を主張するものであり、これに対して日本産婦人科学会をはじめ現場の医師は「癒着胎盤は稀な症例で予見不可能」と反論しています。
私も病理の立場から癒着胎盤についてコメントさせて頂きましょう。写真をご覧下さい。慣れていないとわかりにくい写真だと思いますが、placenta accreta又はaccreta of placentaで癒着胎盤のことです。この写真では子宮を摘出して縦に半割してあります。赤黒い部分が胎盤組織の一部で、これが子宮筋層に食い込んでしまってうまく剥離しないのが癒着胎盤です。
これがなぜ命にかかわるのでしょう?胎盤は出産と同時に不要になる器官です。普通は出産直後に胎盤も子宮から剥がれ落ち、「後産」となって排出されることはご存知かと思います。
さて、胎盤は極めて血量の多い器官、と言うか血管でできた迷路みたいな構造をしています。胎盤は母体と胎児の間の一種の交換機であって、薄い膜を隔てて双方の血液が大量に循環することで酸素や二酸化炭素、栄養分などが交換されます。胎児の成長は急速ですから、母体の血液が大量に胎盤を通過しないと胎児の生命を保つことができません。このため、子宮と胎盤との間には多数の動脈、静脈が連絡しています。これが危険なのです。
胎盤が剥がれ落ちることと、子宮と胎盤の間の血流が極めて多いことは矛盾する要素です。そのまま剥がれ落ちたら大出血で母親が死んでしまいます。これを解決するために子宮は特別な機能を持っています。子宮の内側には内膜という普段は薄い膜がありますが、妊娠時にはこれが発達して脱落膜というクッションを形成します。胎盤はこの脱落膜に食い込むことで子宮に接着し、子宮から脱落膜に伸びてくる多数のらせん動脈と言われる動脈から血液を取り込むことで血液供給を受けます。
出産後はその名の通り脱落膜ごと剥がれ落ちますので、胎盤も子宮からスムーズに剥離するようになります。これに先立って、らせん動脈が強く収縮して胎盤への血流を止めるため、致命的な出血を避けられるわけです。それでもこの状態が危険なのには変わりがなく、全例が「自然分娩」だった時代には生理的な止血がうまく働かず、産後の出血で亡くなった母親は多かったはずです。
癒着胎盤では脱落膜が欠落しており、胎盤が子宮の壁の中にある筋層に食い込んでしまうため、出産しても胎盤がうまく剥がれ落ちてくれません。筋層の動脈はらせん動脈ではなく普通の動脈です。もちろん普通の動脈にも傷を負えば止血する仕組みはありますが、特殊ならせん動脈ほどではありません。動脈を切るにしても、胎盤の破片を残すにしても、どうしても大出血につながってしまうのです。子宮と胎盤の間で止血できないなら、子宮ごと摘出することで止血するしかありません。細い動脈が無数にある子宮と胎盤の間ではなく、太い動脈が数本あるだけの子宮そのものの方が、手術で止血可能だからです。
ではこの危険な癒着胎盤を前もって診断することはできないでしょうか?癒着胎盤の頻度は1万例に1例とも、3,000例に1例とも記載がありばらついています。これは癒着の程度が様々だからだと思います。顕微鏡で見ないとわからない上に、臨床的にもたいした出血をしないものであれば、癒着胎盤と診断されることなく「正常分娩」と扱われているものもあるのでしょう。
ほとんどの癒着胎盤では、胎盤の全面が子宮筋層と癒着しているわけではなく、一部に危険な癒着があるに過ぎません。全面的な癒着胎盤というのはほとんどなくて、部分的な癒着で剥離するまでわかりにくいことが多く、しかもどれが大出血を起こすのか判断材料がほとんどないという産科泣かせの疾患です。事後に胎盤(と時には子宮も)を標本として採取し顕微鏡で見ないと病態の解明は難しいのです。
子宮を摘出する前の段階で、産科医としては「普通に剥がそうとしたけどうまく剥がれない」ことで癒着の可能性を考えるしかありません。この程度の小さな癒着でも、顕微鏡では子宮筋層の動脈にはっきり連絡していて、大出血の原因となるものは十分に考えられます。細い血管であっても動脈は静脈に比べて格段に血圧が高いため、大量出血につながりやすいからです。
それじゃ、胎盤が剥離しにくければ子宮を摘出すれば?それは無理です。「胎盤が剥離しにくい」と言っても、胎盤の位置や形による場合もあるでしょうし、胎盤を剥離した後のらせん動脈の収縮の程度や脱落膜の剥がれ方にも個人差があるでしょう。正確に判定(あるいは予測)するのは極めて難しいと思います。疑わしい場合は大量輸血を用意して子宮摘出を、というのが検察の立場のようですが、少し剥離しにくいだけで子宮を摘出していたら、相当な例で子宮摘出をすることになるでしょう。結果的に病理検査で「癒着胎盤ではない」と判定されれば、今度は「必要のない子宮摘出を行った」として産科医が業務上過失傷害で逮捕されるのでしょうか?そもそも顕微鏡レベルの癒着胎盤を触感で診断しろと言うのは無茶です。
問題の症例における癒着胎盤の程度は、検察側病理医が「広範で子宮筋層の半ばまで」の重篤な癒着、弁護側病理医が「範囲は狭く、子宮筋層の1/5まで」と見解が大きく分かれています。正しく作られた標本を見て、他の情報も正しければ病理診断もほぼ同じになるはずなので、この違いは奇異に映ります。
病理診断は組織を採取して顕微鏡で精査することから、最も確実な証拠を得られることが多く、医療における最終診断とされるのですが、それはパズルの最後のコマを嵌め込む意味で最終診断となるのであって、それまでの診断経過が間違っていれば間違った病理診断が出ることもあります。それに病理医による得手不得手は当然あります。
検察側の病理医は腫瘍が専門であり胎盤については一般的な病理医の域を出ないのに対し、弁護側病理医は胎盤病理の専門家であり5万例の症例を持っています。私が驚いたのは稀な症例である癒着胎盤を24例も経験しておられることで、この分野では医学会を代表する権威と言えるでしょう。これで検察側の鑑定がほとんど突き崩されているのですから、「癒着胎盤の程度は外見からは著しいものではなく、産婦人科専門医といえどもこの症例に対して癒着胎盤を予見することは無理だった」と考えるべきです。
検察は「病理医なんだから何でもわかるはず」と考えたのでしょうが、現場の病理医は極端な人手不足のため全分野を受け持っている人が多いだけで、それぞれの専門分野はあります。病理医の充足しているアメリカでは消化管なら消化管しか見ない専門化した病理医がたくさんいますし、皮膚病理でも腫瘍と炎症疾患の専門家は別です。日本では何でも見る(見ざるを得ない)一般病理医が多く、どうしても手に負えない場合だけ大学などの専門化した病理医に送って専門的な意見を頂くことになっています。
胎盤病理の専門家ではない病理医に鑑定を依頼して、「癒着胎盤を無理に剥がそうとして出血死させた医療過誤例です。鑑定お願いします。」と予断を与えた場合、正しい鑑定を期待するのは難しいのではないでしょうか。私たち病理医が顕微鏡で読み分けているのは、場合によっては(他科の医師に見せてあげるとそう言われるのですが)本当に微妙なものであり、そんな難解例を診断する際はどんな些細な情報でも欲しいものです。検察の「方針」が病理の鑑定に悪い影響を与え、そうしてできたあやふやな病理診断が、今度は「絶対の証拠」として裁判の行方を左右する。そんな悪しき連鎖はどこかで断ち切らないといけません。今度は5月に弁護側最終弁論があるそうで、裁判がより真実に近付くことを期待します。
私も病理の立場から癒着胎盤についてコメントさせて頂きましょう。写真をご覧下さい。慣れていないとわかりにくい写真だと思いますが、placenta accreta又はaccreta of placentaで癒着胎盤のことです。この写真では子宮を摘出して縦に半割してあります。赤黒い部分が胎盤組織の一部で、これが子宮筋層に食い込んでしまってうまく剥離しないのが癒着胎盤です。
これがなぜ命にかかわるのでしょう?胎盤は出産と同時に不要になる器官です。普通は出産直後に胎盤も子宮から剥がれ落ち、「後産」となって排出されることはご存知かと思います。
さて、胎盤は極めて血量の多い器官、と言うか血管でできた迷路みたいな構造をしています。胎盤は母体と胎児の間の一種の交換機であって、薄い膜を隔てて双方の血液が大量に循環することで酸素や二酸化炭素、栄養分などが交換されます。胎児の成長は急速ですから、母体の血液が大量に胎盤を通過しないと胎児の生命を保つことができません。このため、子宮と胎盤との間には多数の動脈、静脈が連絡しています。これが危険なのです。
胎盤が剥がれ落ちることと、子宮と胎盤の間の血流が極めて多いことは矛盾する要素です。そのまま剥がれ落ちたら大出血で母親が死んでしまいます。これを解決するために子宮は特別な機能を持っています。子宮の内側には内膜という普段は薄い膜がありますが、妊娠時にはこれが発達して脱落膜というクッションを形成します。胎盤はこの脱落膜に食い込むことで子宮に接着し、子宮から脱落膜に伸びてくる多数のらせん動脈と言われる動脈から血液を取り込むことで血液供給を受けます。
出産後はその名の通り脱落膜ごと剥がれ落ちますので、胎盤も子宮からスムーズに剥離するようになります。これに先立って、らせん動脈が強く収縮して胎盤への血流を止めるため、致命的な出血を避けられるわけです。それでもこの状態が危険なのには変わりがなく、全例が「自然分娩」だった時代には生理的な止血がうまく働かず、産後の出血で亡くなった母親は多かったはずです。
癒着胎盤では脱落膜が欠落しており、胎盤が子宮の壁の中にある筋層に食い込んでしまうため、出産しても胎盤がうまく剥がれ落ちてくれません。筋層の動脈はらせん動脈ではなく普通の動脈です。もちろん普通の動脈にも傷を負えば止血する仕組みはありますが、特殊ならせん動脈ほどではありません。動脈を切るにしても、胎盤の破片を残すにしても、どうしても大出血につながってしまうのです。子宮と胎盤の間で止血できないなら、子宮ごと摘出することで止血するしかありません。細い動脈が無数にある子宮と胎盤の間ではなく、太い動脈が数本あるだけの子宮そのものの方が、手術で止血可能だからです。
ではこの危険な癒着胎盤を前もって診断することはできないでしょうか?癒着胎盤の頻度は1万例に1例とも、3,000例に1例とも記載がありばらついています。これは癒着の程度が様々だからだと思います。顕微鏡で見ないとわからない上に、臨床的にもたいした出血をしないものであれば、癒着胎盤と診断されることなく「正常分娩」と扱われているものもあるのでしょう。
ほとんどの癒着胎盤では、胎盤の全面が子宮筋層と癒着しているわけではなく、一部に危険な癒着があるに過ぎません。全面的な癒着胎盤というのはほとんどなくて、部分的な癒着で剥離するまでわかりにくいことが多く、しかもどれが大出血を起こすのか判断材料がほとんどないという産科泣かせの疾患です。事後に胎盤(と時には子宮も)を標本として採取し顕微鏡で見ないと病態の解明は難しいのです。
子宮を摘出する前の段階で、産科医としては「普通に剥がそうとしたけどうまく剥がれない」ことで癒着の可能性を考えるしかありません。この程度の小さな癒着でも、顕微鏡では子宮筋層の動脈にはっきり連絡していて、大出血の原因となるものは十分に考えられます。細い血管であっても動脈は静脈に比べて格段に血圧が高いため、大量出血につながりやすいからです。
それじゃ、胎盤が剥離しにくければ子宮を摘出すれば?それは無理です。「胎盤が剥離しにくい」と言っても、胎盤の位置や形による場合もあるでしょうし、胎盤を剥離した後のらせん動脈の収縮の程度や脱落膜の剥がれ方にも個人差があるでしょう。正確に判定(あるいは予測)するのは極めて難しいと思います。疑わしい場合は大量輸血を用意して子宮摘出を、というのが検察の立場のようですが、少し剥離しにくいだけで子宮を摘出していたら、相当な例で子宮摘出をすることになるでしょう。結果的に病理検査で「癒着胎盤ではない」と判定されれば、今度は「必要のない子宮摘出を行った」として産科医が業務上過失傷害で逮捕されるのでしょうか?そもそも顕微鏡レベルの癒着胎盤を触感で診断しろと言うのは無茶です。
問題の症例における癒着胎盤の程度は、検察側病理医が「広範で子宮筋層の半ばまで」の重篤な癒着、弁護側病理医が「範囲は狭く、子宮筋層の1/5まで」と見解が大きく分かれています。正しく作られた標本を見て、他の情報も正しければ病理診断もほぼ同じになるはずなので、この違いは奇異に映ります。
病理診断は組織を採取して顕微鏡で精査することから、最も確実な証拠を得られることが多く、医療における最終診断とされるのですが、それはパズルの最後のコマを嵌め込む意味で最終診断となるのであって、それまでの診断経過が間違っていれば間違った病理診断が出ることもあります。それに病理医による得手不得手は当然あります。
検察側の病理医は腫瘍が専門であり胎盤については一般的な病理医の域を出ないのに対し、弁護側病理医は胎盤病理の専門家であり5万例の症例を持っています。私が驚いたのは稀な症例である癒着胎盤を24例も経験しておられることで、この分野では医学会を代表する権威と言えるでしょう。これで検察側の鑑定がほとんど突き崩されているのですから、「癒着胎盤の程度は外見からは著しいものではなく、産婦人科専門医といえどもこの症例に対して癒着胎盤を予見することは無理だった」と考えるべきです。
検察は「病理医なんだから何でもわかるはず」と考えたのでしょうが、現場の病理医は極端な人手不足のため全分野を受け持っている人が多いだけで、それぞれの専門分野はあります。病理医の充足しているアメリカでは消化管なら消化管しか見ない専門化した病理医がたくさんいますし、皮膚病理でも腫瘍と炎症疾患の専門家は別です。日本では何でも見る(見ざるを得ない)一般病理医が多く、どうしても手に負えない場合だけ大学などの専門化した病理医に送って専門的な意見を頂くことになっています。
胎盤病理の専門家ではない病理医に鑑定を依頼して、「癒着胎盤を無理に剥がそうとして出血死させた医療過誤例です。鑑定お願いします。」と予断を与えた場合、正しい鑑定を期待するのは難しいのではないでしょうか。私たち病理医が顕微鏡で読み分けているのは、場合によっては(他科の医師に見せてあげるとそう言われるのですが)本当に微妙なものであり、そんな難解例を診断する際はどんな些細な情報でも欲しいものです。検察の「方針」が病理の鑑定に悪い影響を与え、そうしてできたあやふやな病理診断が、今度は「絶対の証拠」として裁判の行方を左右する。そんな悪しき連鎖はどこかで断ち切らないといけません。今度は5月に弁護側最終弁論があるそうで、裁判がより真実に近付くことを期待します。


病理学会の総会は春と秋の年2回です。春が本来の総会で、秋は少し規模が小さく、小さな会場で開催されることが多いです。今回は江戸川区総合区民ホール(タワーホール船堀)でした。来年の春は金沢、秋は松山だそうです。

上にタワーがあるからタワーホールなんですね。上に上がってみる時間はありませんでしたが、きっと見晴らしはいいでしょう。都営新宿線から見ると江戸川近辺も新しい高層マンションがたくさん建っており、便利な住宅地として人気があるのでしょう。極楽家も東京勤務ならこの近辺でマンション暮らしだったかも。

クリスマスが近いのできれいに飾り付けてありました。ホールの中以外は自由に出入りできるので、近所の人がベンチで新聞を読んでいたり、クリスマスの装飾を楽しんだりしていました。暇つぶしに病理学会を覗いてみよう、という人はいなかったようです。

検査機器メーカーによるランチョンセミナーと言うと難しそうですが、要するに弁当付きの新製品説明会です。まさか今時、勤務医が贅沢な生活をしているなんて思っている人もいないでしょうが、この日の弁当を撮影してみました。どこのコンビニでも売ってる普通の弁当です。
この日は日帰りの日程だったので、乳癌の術前化学療法の効果判定について、ヴァーチャルスライドの利用について、脳腫瘍の診断、それから胸腺腫瘍の鑑別についてのセミナーを続けて聴いてから、とんぼ返りに名古屋に帰りました。病理は人手不足なので、学会でもなかなか2日続けては留守にできないのです。
東京は新宿で開催中の、日本病理学会総会です。病理学会は内科や外科などの臨床系の学会と違って、まず会員が少ないですし、製薬会社や機器メーカーとあまり接点がないためスポンサーが付きにくく、総会と言っても地味なものです。病理医が直接治療をするわけでもありませんので、一般の方の話題にもなりにくいでしょうね。
小児科や産婦人科の人手不足が深刻な問題となっていますが、病理や放射線科の人手不足についてはどれだけ知られているでしょうか。どちらも患者さんに接することが少ないため、新聞やテレビで取り上げられることはめったにありませんが、全国の総合病院で最も不足している医師と認識されています。
国際統計を見ると、日本の人口当たり医師数はアメリカやドイツ、フランスの3分の2といったところで、かなり少ないと言っていいでしょう。旧厚生省が「医師余り」キャンペーンを張っていましたが、当時はもっと少なかったので、これは証拠のない強弁もしくは詭弁でありました。実際に病院で診療を受けられた経験があれば、厚生省の嘘はすぐにわかったはずです。
その「3分の2しかいない」医師数ですが、どの科も均等に3分の2というわけじゃありません。たまたま検索してヒットした江別市民病院臨床病理科のわかりやすい紹介記事を参考にさせて頂くなら、人口比で日本の病理医はアメリカの5分の1。地方の基幹病院でも常勤病理医がいない施設は珍しくない、という危機的な状況です。
このような現況に鑑み、日本病理学会も対策を講じておりますが、なかなか実効を見ておりません。今回は総会への医学生や研修医の参加を歓迎するという企画を立てまして、若い人に病理への関心を持ってもらおうと努力しています。こうした政策はすぐに成果が得られるわけではないので、長く続けることが必要です。
小児科や産婦人科の人手不足が深刻な問題となっていますが、病理や放射線科の人手不足についてはどれだけ知られているでしょうか。どちらも患者さんに接することが少ないため、新聞やテレビで取り上げられることはめったにありませんが、全国の総合病院で最も不足している医師と認識されています。
国際統計を見ると、日本の人口当たり医師数はアメリカやドイツ、フランスの3分の2といったところで、かなり少ないと言っていいでしょう。旧厚生省が「医師余り」キャンペーンを張っていましたが、当時はもっと少なかったので、これは証拠のない強弁もしくは詭弁でありました。実際に病院で診療を受けられた経験があれば、厚生省の嘘はすぐにわかったはずです。
その「3分の2しかいない」医師数ですが、どの科も均等に3分の2というわけじゃありません。たまたま検索してヒットした江別市民病院臨床病理科のわかりやすい紹介記事を参考にさせて頂くなら、人口比で日本の病理医はアメリカの5分の1。地方の基幹病院でも常勤病理医がいない施設は珍しくない、という危機的な状況です。
このような現況に鑑み、日本病理学会も対策を講じておりますが、なかなか実効を見ておりません。今回は総会への医学生や研修医の参加を歓迎するという企画を立てまして、若い人に病理への関心を持ってもらおうと努力しています。こうした政策はすぐに成果が得られるわけではないので、長く続けることが必要です。
胃がん検診などで、内視鏡を飲みますね。内視鏡は基本的には光ファイバーの束で、先の部分が蛇の頭みたいにくねくねと左右に曲がるようにできており、胃の中を自在に観察できるものです。
これが実に多機能で、照明はつく、写真は撮れる、レンズが汚れたら水を出して洗う、薬剤を散布する、さらにオプションで注射はするし、止血操作や切開もする、レーザー光線で組織を焼くこともできる、という優れたもの。ここまでくると医療ロボットと言ってもいいほど。
この内視鏡の大切な役目に、組織のごく一部を摘み取ってくる「生検」があります。「胃角部に潰瘍があるけど、この形だと癌の可能性もあるな。」という場合に、その潰瘍の縁のところから組織の小片を採取して、ワイヤーで引っ張ると瞬時に問題の組織が医師の手元に。これを乾かないようにホルマリン溶液に漬けたところから、病理の仕事が始まります。
ホルマリンが組織の中まで浸透し、これを処理して顕微鏡標本(プレパラート)にするまで、小さな材料なら2,3日。検体の配送や登録、そして診断の手間を入れますと、もう少し時間を頂くことになります。内視鏡検査をしてもすぐに結果が出ないのはこのため。
プレパラートを見て「単なる胃炎」か「癌」かを決めるわけですが、その手掛かりになるのは細胞そのものや細胞が作る構造の形、つまり「形態」です。組織診断学の基本は形態学に他なりません。
簡単に言えば、「外見から中身を判断する」技術であります。人間の善悪を外見から判断するのは良くないこととされていますが、それはやり方の問題です。十分な情報と経験がないのに判断すれば、相手が何だって良くありません。十分な技術があれば、とても有効な手法になります。
「そろそろ雨かな」とか「この店まずそうだな」、「今日は調子良さそうだね」、「前の車は停まるんじゃないか」など、外見から中身を判断する術はいくらでもあります。人間の五感は非常に優れたセンサーですから、これを駆使して豊富な経験で判断すれば、かなりの真実は見抜けるもの。
この技能を個人の経験にとどめず、学問として共有し、高めていく。このような診断、評価の技術体系はいくつもあります。例えばワインのテイスティングや、美術品の鑑定、乗り心地や肌触りの検査など。
組織検査は膨大な医学の知見を背負ってはいますが、診断技術そのものはこうした官能検査に近い側面がありまして、胃炎か癌かの診断というのは、美術品や骨董の鑑定にも似ています。
これが実に多機能で、照明はつく、写真は撮れる、レンズが汚れたら水を出して洗う、薬剤を散布する、さらにオプションで注射はするし、止血操作や切開もする、レーザー光線で組織を焼くこともできる、という優れたもの。ここまでくると医療ロボットと言ってもいいほど。
この内視鏡の大切な役目に、組織のごく一部を摘み取ってくる「生検」があります。「胃角部に潰瘍があるけど、この形だと癌の可能性もあるな。」という場合に、その潰瘍の縁のところから組織の小片を採取して、ワイヤーで引っ張ると瞬時に問題の組織が医師の手元に。これを乾かないようにホルマリン溶液に漬けたところから、病理の仕事が始まります。
ホルマリンが組織の中まで浸透し、これを処理して顕微鏡標本(プレパラート)にするまで、小さな材料なら2,3日。検体の配送や登録、そして診断の手間を入れますと、もう少し時間を頂くことになります。内視鏡検査をしてもすぐに結果が出ないのはこのため。
プレパラートを見て「単なる胃炎」か「癌」かを決めるわけですが、その手掛かりになるのは細胞そのものや細胞が作る構造の形、つまり「形態」です。組織診断学の基本は形態学に他なりません。
簡単に言えば、「外見から中身を判断する」技術であります。人間の善悪を外見から判断するのは良くないこととされていますが、それはやり方の問題です。十分な情報と経験がないのに判断すれば、相手が何だって良くありません。十分な技術があれば、とても有効な手法になります。
「そろそろ雨かな」とか「この店まずそうだな」、「今日は調子良さそうだね」、「前の車は停まるんじゃないか」など、外見から中身を判断する術はいくらでもあります。人間の五感は非常に優れたセンサーですから、これを駆使して豊富な経験で判断すれば、かなりの真実は見抜けるもの。
この技能を個人の経験にとどめず、学問として共有し、高めていく。このような診断、評価の技術体系はいくつもあります。例えばワインのテイスティングや、美術品の鑑定、乗り心地や肌触りの検査など。
組織検査は膨大な医学の知見を背負ってはいますが、診断技術そのものはこうした官能検査に近い側面がありまして、胃炎か癌かの診断というのは、美術品や骨董の鑑定にも似ています。
外科の先生がお腹を触って、「うん、これは癌だ」と診断していたのは昔のこと。今では胃癌であれ、大腸癌であれ、あるいは肺癌、乳癌、前立腺癌などでも、手術の前に病巣の一部を採取して組織検査に出し、病理医が癌の診断をすることが常識になってきました。
また、手術で切除した胃などの組織も、癌の進行度や治癒度を調べるために病理に送られます。更に、不幸にして亡くなられた患者さんを解剖して、生前には診断のつかなかった病気の進行を調べるのも病理医の業務。
これだけ仕事の範囲が広く、ますます重要度が増しているのに、病理医の人数は全然増えていません。規模の大きな総合病院で、放射線科医と病理医は大学に要請しても人を出してくれない、という苦情をよく聞きます。そりゃそうでしょう。大学でも不足していますから。
病理への入局者を何とか確保したい、という医局の悲願にも関わらず、慢性的な人手不足が続くのはなぜでしょうか。簡単ではないですが、対策を考えてみたいと思います。
多くの医師が自分の専門を決定するのは、医師免許を取得して研修医となってからです。研修医にとって、病理医はどのように見えているのでしょう?
ローテート研修、と言いまして、研修医は各科を少しずつ回りながら、どの科のことも少しはわかるように経験を積み、その間に自分を生かせる専門科を選んで行くのが普通です。しかし、病理を回ってやろうという研修医は少数です。
研修医は国家試験に合格して、病院に配属された段階では、本当に何もできません。ゼロから経験を積むわけですから、ともかく患者さんを早く診療できるようになろう、ということで内科や外科、救急などの診療に直結した科で研修を受けたがります。これは当然のこと。
裏方である病理のことなど、ひとまず置いといて、というのが一般のパターンでしょう。かくして、研修はしたけど病理のことはよくわからない、という若手医師が次々に生まれるわけです。知らないのだから、入局など考えもしないでしょう。
これには我々にも責任があって、人手不足で研修医の相手がなかなかできないのです。意欲のある研修医が、外科で受け持った自分の症例について病理に質問に来る。あるいは学会発表のために病理所見を聞きに来る。これは病理にとって有難いことです。しかし、仕事を抱えているとなかなか時間が割けない。
このようにして病理医は、「検査部の奥でずっと座っている無愛想な親父」という評価を受けるわけです。いや、無愛想なんじゃなくて、顕微鏡の見過ぎで目が疲れているだけなんですけど。
仕事は多いし、患者さんにはお会いできないですが、病理にもいい点はたくさんあるのに、研修医がはなから入局先として考えてくれないのはもったいない。ちょっと宣伝させてもらいましょうか。
患者さんに会わない職種なので、「この人を診断して、治してあげよう」という実感の欲しい人には確かに向きません。しかし自分のペースで仕事がしやすいですし、人と話すのが苦手な人にも向いています。
あ、余談ですが、ある名医が、「我は包帯するのみ。神が治したもう。」と言ったのが美談になって、今でも「医者は謙虚なのがいい」と思っている方が多いようですが、私の実感には合いません。救急の多い外科など、徹夜や飯抜きは当たり前。手術と検査と救急の連続で、3日に1度しか横になれなかった、なんてことも珍しくありません。こんな生活が何年も続くのですよ。ここまできついと、職務意識とか義務の念だけで勤まるはずもなく、脳内麻薬が分泌されてハイになっていないともたないでしょう。
ですから、この中で成功する人というのは、並外れた強い意志の持ち主です。「神に成り代わって、この患者は俺が治してやる!!」というようなキャラクターでないと、抜きん出た努力などできるわけがありません。だいたい「我は包帯するのみ」と言った人の時代(16世紀)は、本当に包帯するしかなかったのです。謙虚さはもちろんいいことですが、その前にその医者の技術や経験、仕事に掛ける熱意をよく見られますように。
閑話休題。病理医の待遇は、病院に勤務する限りは他の科とたいして変わりません。まあ、内科の方が薬屋さんからボールペンとかメモ帳とかをもらい易い、というのはあります。最近は広告入りのUSBメモリをお土産にしている薬屋さんが多いですね。私もあれ欲しいんだけど、残念ながら病理には来てくれません。それから、病理で開業は難しいです。
仕事は疲れますが、少し減らしてもらえるなら高齢でも診療できるのは大きなメリットでしょう。極楽親父の所属する病理学教室で、最年長の現役病理医は確か84歳!だったと思います。これは特殊な例ではありますが、個人差はあるにしても、外科などより医師としての寿命が長いことは確かです。高齢になるともちろん視力は衰えますが、病理診断は視力検査よりはむしろ美術品の鑑定に近い作業なので、視力よりも経験が重要なのです。
若い医師にとって一般の臨床科と病理で一番違うのは、一人前になるまでの配属先じゃないでしょうか。一般の医師が初期研修を終えてからも長く市中病院でレジデントを続けるのに対し、病理は大学院に入学するのが基本なので、同級生よりも早く大学に戻って博士号を取ることができます。
だから早く大学に帰って研究したい人や、医学博士が早く欲しい人にはとても向いています。若手医師にとって、この「大学に帰って博士号のために研究をしている数年間」は体力的にも経済的にも非常に厳しい時期です。苦しい時期を先に終えてしまえば家庭を安定させることができるため、「医者同士のカップルで子供の世話ができない!」なんて危機も回避できます。
医者同士のカップルって、周りを見ると珍しくありません。大学時代から研修医時代にかけて、閉鎖的な環境で生活していますし、同じ理科系でも工学部などと比べて女性の割合が高いからでしょうか。同級生との結婚を予定している研修医の皆さん!どちらか1人が病理に入れば、子供の世話で悩まなくて済みますよ。
こんなことで病理医が倍増するかって?まあ、始めたばかりですから。個人の雑記のようなブログを続けることが、少しでも宣伝になればとささやかな期待を抱いています。
また、手術で切除した胃などの組織も、癌の進行度や治癒度を調べるために病理に送られます。更に、不幸にして亡くなられた患者さんを解剖して、生前には診断のつかなかった病気の進行を調べるのも病理医の業務。
これだけ仕事の範囲が広く、ますます重要度が増しているのに、病理医の人数は全然増えていません。規模の大きな総合病院で、放射線科医と病理医は大学に要請しても人を出してくれない、という苦情をよく聞きます。そりゃそうでしょう。大学でも不足していますから。
病理への入局者を何とか確保したい、という医局の悲願にも関わらず、慢性的な人手不足が続くのはなぜでしょうか。簡単ではないですが、対策を考えてみたいと思います。
多くの医師が自分の専門を決定するのは、医師免許を取得して研修医となってからです。研修医にとって、病理医はどのように見えているのでしょう?
ローテート研修、と言いまして、研修医は各科を少しずつ回りながら、どの科のことも少しはわかるように経験を積み、その間に自分を生かせる専門科を選んで行くのが普通です。しかし、病理を回ってやろうという研修医は少数です。
研修医は国家試験に合格して、病院に配属された段階では、本当に何もできません。ゼロから経験を積むわけですから、ともかく患者さんを早く診療できるようになろう、ということで内科や外科、救急などの診療に直結した科で研修を受けたがります。これは当然のこと。
裏方である病理のことなど、ひとまず置いといて、というのが一般のパターンでしょう。かくして、研修はしたけど病理のことはよくわからない、という若手医師が次々に生まれるわけです。知らないのだから、入局など考えもしないでしょう。
これには我々にも責任があって、人手不足で研修医の相手がなかなかできないのです。意欲のある研修医が、外科で受け持った自分の症例について病理に質問に来る。あるいは学会発表のために病理所見を聞きに来る。これは病理にとって有難いことです。しかし、仕事を抱えているとなかなか時間が割けない。
このようにして病理医は、「検査部の奥でずっと座っている無愛想な親父」という評価を受けるわけです。いや、無愛想なんじゃなくて、顕微鏡の見過ぎで目が疲れているだけなんですけど。
仕事は多いし、患者さんにはお会いできないですが、病理にもいい点はたくさんあるのに、研修医がはなから入局先として考えてくれないのはもったいない。ちょっと宣伝させてもらいましょうか。
患者さんに会わない職種なので、「この人を診断して、治してあげよう」という実感の欲しい人には確かに向きません。しかし自分のペースで仕事がしやすいですし、人と話すのが苦手な人にも向いています。
あ、余談ですが、ある名医が、「我は包帯するのみ。神が治したもう。」と言ったのが美談になって、今でも「医者は謙虚なのがいい」と思っている方が多いようですが、私の実感には合いません。救急の多い外科など、徹夜や飯抜きは当たり前。手術と検査と救急の連続で、3日に1度しか横になれなかった、なんてことも珍しくありません。こんな生活が何年も続くのですよ。ここまできついと、職務意識とか義務の念だけで勤まるはずもなく、脳内麻薬が分泌されてハイになっていないともたないでしょう。
ですから、この中で成功する人というのは、並外れた強い意志の持ち主です。「神に成り代わって、この患者は俺が治してやる!!」というようなキャラクターでないと、抜きん出た努力などできるわけがありません。だいたい「我は包帯するのみ」と言った人の時代(16世紀)は、本当に包帯するしかなかったのです。謙虚さはもちろんいいことですが、その前にその医者の技術や経験、仕事に掛ける熱意をよく見られますように。
閑話休題。病理医の待遇は、病院に勤務する限りは他の科とたいして変わりません。まあ、内科の方が薬屋さんからボールペンとかメモ帳とかをもらい易い、というのはあります。最近は広告入りのUSBメモリをお土産にしている薬屋さんが多いですね。私もあれ欲しいんだけど、残念ながら病理には来てくれません。それから、病理で開業は難しいです。
仕事は疲れますが、少し減らしてもらえるなら高齢でも診療できるのは大きなメリットでしょう。極楽親父の所属する病理学教室で、最年長の現役病理医は確か84歳!だったと思います。これは特殊な例ではありますが、個人差はあるにしても、外科などより医師としての寿命が長いことは確かです。高齢になるともちろん視力は衰えますが、病理診断は視力検査よりはむしろ美術品の鑑定に近い作業なので、視力よりも経験が重要なのです。
若い医師にとって一般の臨床科と病理で一番違うのは、一人前になるまでの配属先じゃないでしょうか。一般の医師が初期研修を終えてからも長く市中病院でレジデントを続けるのに対し、病理は大学院に入学するのが基本なので、同級生よりも早く大学に戻って博士号を取ることができます。
だから早く大学に帰って研究したい人や、医学博士が早く欲しい人にはとても向いています。若手医師にとって、この「大学に帰って博士号のために研究をしている数年間」は体力的にも経済的にも非常に厳しい時期です。苦しい時期を先に終えてしまえば家庭を安定させることができるため、「医者同士のカップルで子供の世話ができない!」なんて危機も回避できます。
医者同士のカップルって、周りを見ると珍しくありません。大学時代から研修医時代にかけて、閉鎖的な環境で生活していますし、同じ理科系でも工学部などと比べて女性の割合が高いからでしょうか。同級生との結婚を予定している研修医の皆さん!どちらか1人が病理に入れば、子供の世話で悩まなくて済みますよ。
こんなことで病理医が倍増するかって?まあ、始めたばかりですから。個人の雑記のようなブログを続けることが、少しでも宣伝になればとささやかな期待を抱いています。
病理医という存在すらあまり知られない日本では、何をやっているのか聞かれることも少ないのですが、それじゃ寂しいので自己紹介です。
病理、という言葉は、元来病気のメカニズムを調べる学問という意味なのでしょう。しかし、病気についての研究は今やどの科でも懸命にやっています。内科と名が付いても、病院での診療より研究室での実験が忙しい大学医局はいくつもありますから。
病理学教室のスタッフも多くは研究に時間を割いています。ただ、極楽親父こと私のように、病院での診療業務にほとんど専従している、いわゆる「病院病理医」の仕事も年々存在感を増しており、業務の増加、多様化に比べて新規入局者が少ないゆえに、深刻な専門医不足が懸念されています。医学生や研修医に対する宣伝も必要ですが、まず一般の皆様に我々の存在をアピールすることが大事だと痛感している次第です。
個人開設の診療所と違って、大きな病院では検査部門が発達しています。血液検査、細菌検査、呼吸機能、心電図、脳波、レントゲン、内視鏡などですね。大きな検査部門の中で、患者さんから採取した組織を観察して病気を診断する部門があります。これが病理検査。
例えばあなたが内視鏡を飲んで胃の検査をします。胃は柔らかい粘膜で被われた臓器なのですが、この粘膜から癌が発生しますので、その場合は早期発見して治療しなければいけません。内視鏡で「ここが気になるな」という個所があれば、消化器内科の医師は内視鏡に仕込まれた小型の鉗子を抜くが早いか、瞬時に粘膜の小さな切れっ端を検体として採取します。
この粘膜の小片が検査技師によって顕微鏡標本、つまりプレパラートに加工されて病理医の手に委ねられます。これを顕微鏡で観察して、「悪性像なし」とか「中分化型腺癌」とか診断するのが病理医の主要な業務です。病理医が出した検査レポートに基づいて、手術するとかしないとかが決定されるので、そりゃ責任は重いですよ。
こんな標本が山のようにあるため、病理医は朝から晩まで顕微鏡を覗いてレポートを書き続けています。ちょっとした規模の病院なら年間10,000件を軽く越えますが、常勤の病理医は1人かせいぜい2人。しかも1件でプレパラート30枚なんて手術標本もあるので、多い日は200枚ほどのプレパラートを真剣に見ないといけません。夕方になって眼精疲労がひどくなると、どんよりと頭が重くなって、もう何もする気力もなくなります。
こんな夜は何よりアルコール。一杯のテーブルワインで、鉛の重石が乗ったような目の重さが「すうっ」という感じで引いて行くと、まだ明日も何とかなるかなと思います。だから極楽親父はアルコールのことを目薬と信じて疑いません。
病理、という言葉は、元来病気のメカニズムを調べる学問という意味なのでしょう。しかし、病気についての研究は今やどの科でも懸命にやっています。内科と名が付いても、病院での診療より研究室での実験が忙しい大学医局はいくつもありますから。
病理学教室のスタッフも多くは研究に時間を割いています。ただ、極楽親父こと私のように、病院での診療業務にほとんど専従している、いわゆる「病院病理医」の仕事も年々存在感を増しており、業務の増加、多様化に比べて新規入局者が少ないゆえに、深刻な専門医不足が懸念されています。医学生や研修医に対する宣伝も必要ですが、まず一般の皆様に我々の存在をアピールすることが大事だと痛感している次第です。
個人開設の診療所と違って、大きな病院では検査部門が発達しています。血液検査、細菌検査、呼吸機能、心電図、脳波、レントゲン、内視鏡などですね。大きな検査部門の中で、患者さんから採取した組織を観察して病気を診断する部門があります。これが病理検査。
例えばあなたが内視鏡を飲んで胃の検査をします。胃は柔らかい粘膜で被われた臓器なのですが、この粘膜から癌が発生しますので、その場合は早期発見して治療しなければいけません。内視鏡で「ここが気になるな」という個所があれば、消化器内科の医師は内視鏡に仕込まれた小型の鉗子を抜くが早いか、瞬時に粘膜の小さな切れっ端を検体として採取します。
この粘膜の小片が検査技師によって顕微鏡標本、つまりプレパラートに加工されて病理医の手に委ねられます。これを顕微鏡で観察して、「悪性像なし」とか「中分化型腺癌」とか診断するのが病理医の主要な業務です。病理医が出した検査レポートに基づいて、手術するとかしないとかが決定されるので、そりゃ責任は重いですよ。
こんな標本が山のようにあるため、病理医は朝から晩まで顕微鏡を覗いてレポートを書き続けています。ちょっとした規模の病院なら年間10,000件を軽く越えますが、常勤の病理医は1人かせいぜい2人。しかも1件でプレパラート30枚なんて手術標本もあるので、多い日は200枚ほどのプレパラートを真剣に見ないといけません。夕方になって眼精疲労がひどくなると、どんよりと頭が重くなって、もう何もする気力もなくなります。
こんな夜は何よりアルコール。一杯のテーブルワインで、鉛の重石が乗ったような目の重さが「すうっ」という感じで引いて行くと、まだ明日も何とかなるかなと思います。だから極楽親父はアルコールのことを目薬と信じて疑いません。
アスベストを吸入することで何十年後に発症し、生命を脅かすと話題の悪性中皮腫。馴染みのない言葉だと思いますので簡単に解説を。
人間にはたくさんの「皮」があります。誰でも知っているのが体の外側にある皮膚。ところが、体の中にも「皮」があります。大まかに分けてみましょう。
まず、皮膚と連続している口の中の粘膜とか消化管、あるいは気管支の粘膜。これらは「上皮」に分類されます。
それから、血管やリンパ管の内側を被う薄い「皮」。これは「内皮」と呼ばれます。
「胸膜」とか「腹膜」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。そう言えば「腹膜炎」という言い方がありますね。手術で胸やお腹を開けると、臓器を収めるスペースがあります。簡単に言うと、横隔膜より上にあるのが「胸腔」、横隔膜より下にあるのが「腹腔」です。これらのスペースや臓器の表面は、「中皮」と呼ばれる薄くて滑りのいい「皮」で被われていて、お互いにくっつかないようになっています。
この「中皮」がアスベストの刺激などで勝手に増殖する腫瘍、つまり「できもの」になったものが「中皮腫」というわけです。
中皮腫はわかりましたね。なぜ癌じゃないかって?いい質問です。
腫瘍は元の組織の特徴をある程度持っていることが多いので、どこから発症した腫瘍かで性質が大きく違います。医学用語では、一般に「上皮組織」から出た悪性腫瘍のことを癌と呼んでいます。胃癌、肺癌、子宮頸癌など、悪性腫瘍の中では癌が最も多いため、一般のマスコミなどでは癌以外の悪性腫瘍も「癌」と表記することがあります。
ですから、日常会話では「悪性中皮腫」のことを「中皮の癌」と呼んでも差し支えありませんが、例えば肺癌と比べると経過や治療方針が違うため、専門家は厳密に区別しています。
人間にはたくさんの「皮」があります。誰でも知っているのが体の外側にある皮膚。ところが、体の中にも「皮」があります。大まかに分けてみましょう。
まず、皮膚と連続している口の中の粘膜とか消化管、あるいは気管支の粘膜。これらは「上皮」に分類されます。
それから、血管やリンパ管の内側を被う薄い「皮」。これは「内皮」と呼ばれます。
「胸膜」とか「腹膜」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。そう言えば「腹膜炎」という言い方がありますね。手術で胸やお腹を開けると、臓器を収めるスペースがあります。簡単に言うと、横隔膜より上にあるのが「胸腔」、横隔膜より下にあるのが「腹腔」です。これらのスペースや臓器の表面は、「中皮」と呼ばれる薄くて滑りのいい「皮」で被われていて、お互いにくっつかないようになっています。
この「中皮」がアスベストの刺激などで勝手に増殖する腫瘍、つまり「できもの」になったものが「中皮腫」というわけです。
中皮腫はわかりましたね。なぜ癌じゃないかって?いい質問です。
腫瘍は元の組織の特徴をある程度持っていることが多いので、どこから発症した腫瘍かで性質が大きく違います。医学用語では、一般に「上皮組織」から出た悪性腫瘍のことを癌と呼んでいます。胃癌、肺癌、子宮頸癌など、悪性腫瘍の中では癌が最も多いため、一般のマスコミなどでは癌以外の悪性腫瘍も「癌」と表記することがあります。
ですから、日常会話では「悪性中皮腫」のことを「中皮の癌」と呼んでも差し支えありませんが、例えば肺癌と比べると経過や治療方針が違うため、専門家は厳密に区別しています。

















