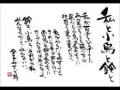論主の答え。
「然るに境界受は余の相に共ずるものには非ず。順等の相を領して定んで己に属する者を境界受と名づくるを以て余には共ぜざるが故に。」(『論』第三・三右)
境界受は外のものを受け入れるのです。自性受は、同字の触を受け入れる、つまり、触とか作意の心の働きを受け入れるというのが自性受なのですが、護法菩薩の論旨は、境界受なんです。外のものを受け入れた時、そこに感情が生まれてきます。それを非常に大切になさっています。
「所縁の境を領納す」、これが本当の受であるといわれます。理由は、「定んで己に属する」ということなんです。唯識無境といいますが、境が無いわけではないんですね。境そのものを認識するということが無い、認識できないというのが本当かもしれません。境は実体としては無い。自分の心が造り出したも、それが境である。
阿頼耶識は言語を超えた世界を種子として蔵しています。法の世界ですね。無自性なるが故に空なり。言語を用いた瞬間に、言語に囚われて執着を起こします。それを戯論として押さえられていますが、唯識は境そのものを受け入れている阿頼耶識から認識を起こす時に、自我意識というフイルターを通して、或は被せて意識の上に実体として認識を起こします。
いくら無自性で有ると言われても、無自性であることを解釈して、無自性なんだと実体化して認識を起こしています。何故なら、「私が」という囚われから離れられないからですね。囚われが、執われに変化して、固執を起こし、自他分別を起こしてきます。そこから生まれてくる感情、感受作用は、苦か、楽か、不苦不楽なんですね。
順境の時は、楽という感情が生まれ。違境の時は、苦という感情が生まれます。倶非(捨)と云う感情は、無意識の状態に於いてのみ働く感受作用でしょうね。
そこで、正理論師の説く自性受は否定され、認識される対象にもとづいて生じる感受作用である境界受をもって、受の本質としています。この辺の事情を『述記』は次のように述べています。
「此の義は如何となれば、能く順と違と倶非との境相を領して、定んで己に属するを境界受と名づく。」と。