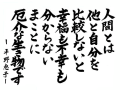おはようございます。お正月休みもほとんどの方が今日までですね。土日が重なったこともあり、長い連休になりました。お疲れ様です。さあ、一年の始まりです。ある人のブログを拝見させていただきまして、感じさせられたことは、お仕事に取り組まれる姿勢が素晴らしいんです。考え方や、人と接するときの気遣い等、お若いとは思えないほどしっかりされています。これからも頑張ってほしいです。
私たちが日常、良いこと、悪いことの判断として、他人に迷惑をかけることが悪、他人に良い影響を与えることが悪と、大雑把にいえばこういうことになるんだ労を思います。ところが、仏教では善・悪は他に対してではないのですね。簡単違説明しますと、
『善は私たちにとって大切な行為ですが、本来、自身が涅槃に向かう道なんです。それと共に他を利する道でもあるんですね。涅槃はニルバーナといい煩悩が滅した状態を指します。煩悩は私たちを悩ませ苦しめると思いがちですが、煩悩は自身の中から湧き出てくるものなんです。自身が自身の煩悩に纏われつかれている状態を苦悩というのですね。、ですから、涅槃は私たちが本来求めている世界なのだと思います。その世界を彼岸ともいいます。彼岸を拠り所にした生活が一番望ましい在り方なのではないでしょうか。ではどのようにしたら彼岸を拠り所に出来るのでしょう。それが『善』なのです。善は浄らかな心です。善の心に付随する法(心所有法)の一番最初に「信」が挙げられています。『正信偈』に「生死輪転の家に還来ることは、決するに疑情をもって所止とす。速やかに寂静無為の楽に入ることは、必ず信心をもって能入とす、といえり」(源空章・真聖P207)と述べておいでになります。「信」の定義は龍樹菩薩の『大智度論』に「仏法の大海は信をもって能入と為し、智を態度と為す」と記されています。信は智と密接不可分の関係で捉えられています。親鸞聖人ははっきりと生死輪転の家は、煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界と押さえておいでになります。これは仏法に疑いを持っていることから引き起こされる世界であるということです。そして涅槃を寂静無為の楽と、心澄浄の世界であると云われています。『歎異抄』に「煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろずのこと、みなもって、そらごとたわごと、まことあることなきに(機の深信)、ただ念仏のみぞまことにておわします(法の深信)」と真実信心のみが「生死いづべき道」として指し示しておられます。唯識では第七末那識が我執(自我意識)として第八阿頼耶識に執着すると言われているのですが、その末那識に出世の末那といわれる働きがあるといわれています。無染汚の末那・已転依の末那ともいわれます。「審らかに無我の相を思量す」と、末那識は自分だけのことを思量するといわれているなかで、それだけではない無我という真理を認めているのです。これによって末那識が転依することが可能となるのです。そして「信」は「心をして浄ならしむを以って性と為し、不信を対治して善を楽ふを以って業と為す」といわれ、信によって心が浄くなることをいわれているのです。こころが浄くなるということは無我・無漏の智慧ですから自分のことがはっきりと見えるのです。「自己とは何ぞや」に答えてあるのですね。自覚・自らに覚めることを以って信を語らなければ、何を信ずるのかがはっきりしなくなります。信は不信というエゴイズムを払拭するものなのです。」
私たちが日常、良いこと、悪いことの判断として、他人に迷惑をかけることが悪、他人に良い影響を与えることが悪と、大雑把にいえばこういうことになるんだ労を思います。ところが、仏教では善・悪は他に対してではないのですね。簡単違説明しますと、
『善は私たちにとって大切な行為ですが、本来、自身が涅槃に向かう道なんです。それと共に他を利する道でもあるんですね。涅槃はニルバーナといい煩悩が滅した状態を指します。煩悩は私たちを悩ませ苦しめると思いがちですが、煩悩は自身の中から湧き出てくるものなんです。自身が自身の煩悩に纏われつかれている状態を苦悩というのですね。、ですから、涅槃は私たちが本来求めている世界なのだと思います。その世界を彼岸ともいいます。彼岸を拠り所にした生活が一番望ましい在り方なのではないでしょうか。ではどのようにしたら彼岸を拠り所に出来るのでしょう。それが『善』なのです。善は浄らかな心です。善の心に付随する法(心所有法)の一番最初に「信」が挙げられています。『正信偈』に「生死輪転の家に還来ることは、決するに疑情をもって所止とす。速やかに寂静無為の楽に入ることは、必ず信心をもって能入とす、といえり」(源空章・真聖P207)と述べておいでになります。「信」の定義は龍樹菩薩の『大智度論』に「仏法の大海は信をもって能入と為し、智を態度と為す」と記されています。信は智と密接不可分の関係で捉えられています。親鸞聖人ははっきりと生死輪転の家は、煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界と押さえておいでになります。これは仏法に疑いを持っていることから引き起こされる世界であるということです。そして涅槃を寂静無為の楽と、心澄浄の世界であると云われています。『歎異抄』に「煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろずのこと、みなもって、そらごとたわごと、まことあることなきに(機の深信)、ただ念仏のみぞまことにておわします(法の深信)」と真実信心のみが「生死いづべき道」として指し示しておられます。唯識では第七末那識が我執(自我意識)として第八阿頼耶識に執着すると言われているのですが、その末那識に出世の末那といわれる働きがあるといわれています。無染汚の末那・已転依の末那ともいわれます。「審らかに無我の相を思量す」と、末那識は自分だけのことを思量するといわれているなかで、それだけではない無我という真理を認めているのです。これによって末那識が転依することが可能となるのです。そして「信」は「心をして浄ならしむを以って性と為し、不信を対治して善を楽ふを以って業と為す」といわれ、信によって心が浄くなることをいわれているのです。こころが浄くなるということは無我・無漏の智慧ですから自分のことがはっきりと見えるのです。「自己とは何ぞや」に答えてあるのですね。自覚・自らに覚めることを以って信を語らなければ、何を信ずるのかがはっきりしなくなります。信は不信というエゴイズムを払拭するものなのです。」