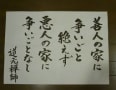今年一年、皆様方には大変お世話をおかけいたしました。また病いに臥しておりました折には大変なお気遣いと、御心配をおかけたしました。紙面上で申し訳ありませんが、お礼申し上
また、ブログはFBとも連携しておりまして、FB上でもたくさんの「いいね」をいただきました。ありがとうございます。大変な励みをいだき、皆様方の後押しで、更新させていただいております。年が明けましてもよろしくお願い申しあげます。 平成27年大晦日
護法の正義を述べる。
「有義は、不正知は倶の一分に摂めらる、前(さき)の二の文に影略(ようりゃく)して説けるに由るが故に。論に復、此は染心(ぜんしん)に遍すると説けるが故にと云う。」(『論』第六・三十一右)
(護法は、不正知とは、(慧と癡の)倶の一分であると云う。何故なら、前の二の文(『雑集論』と『瑜伽論』)に影略して説かれていることに由るからである。『論』(『瑜伽論』)にはまた、「(不正知は)染心に遍く存在する」と説かれているからである。)
読むポイントは、影略ですね。詳しくは影略互顕(ようりゃうごけん)といいます。昨日の投稿が一つのポイントになりますので再録します。
「第一師の説と第二師の説が相違するということではなく、『述記』は互相会文(ごそうえもん)といい、「此の第一第二師互に相い文を会するなり。皆是れ等流なり。と釈しています。つまり、第一師の引く文を第二師が会通し、第二師の引く文を第一師が会通し、「知ることを正しくさせないこと」が不正知であると説明しています。
第二師からの会通の意味は、「知ることを正しくさせないこと」は慧が正しく働いていないからであるとする第一師の主張は、慧が正しく働かないのは癡であり、癡こそが不正知の体であると会通しているのです。
また、第一師からの会通の意味は、『瑜伽論』に不正知が癡の一分と説かれているのは、不正知が癡と相応する慧であることを述べているもので、不正知が煩悩の癡の一分という意味で説かれているのではないと会通しているのです。」
このような説き方の解明が影略といい、それによって顕れてくるのが互顕であるとう会通のしかたです。
第一師 - 慧の一分であるとする。(癡の一分であることが隠されている。)
第二師 - 癡の一分であるとする。(慧の一分であることも含まれている。)
従って、「二の文は」共に不正知は慧と癡の一分であると説いている、これが第三師である護法の論拠となります。会通して表れてきた本意が倶の一分に摂めらる」ということなんですね。
表面に説かれていることに執われるのではなく、言葉の持っている側面、行間を読むことの必要性を教えられます。
文段は二つに分かれます。「論に復、此は染心(ぜんしん)に遍すると説けるが故にと云う」が後半の説明になります。『論』とは、『瑜伽論』巻第五十五と五十八を指します。 『瑜伽論』巻第五十五の記述、
「・・・無慚無愧は一切の不善と相応し、不信、懈怠、放逸、妄念、散乱、悪慧は一切の染汙心(ぜんましん)と相応し、睡眠(すいめん)、悪作(おさ)は一切の善・不善・無記と相応すと。」
『瑜伽論』巻第五十八の記述、
「・・・煩悩と倶行し煩悩の品類(ほんるい)なるを随煩悩と名づく。云何が随煩悩と名づくるや。略して四相の差別に由りて建立す。一には一切の不善心に通じて起こり、二には一切の染汙心に通じて起こり、三には各別の不善心に於て起こり、四には善・不善・無記心に起こるも、一切処に非ず、一切時に非ざるなり。謂く無慚無愧を一切の不善心に通じて起こると名づく。随煩悩の放逸、掉挙、惛沈、不信、懈怠、邪欲、邪勝解、邪念、散乱、不正知の十煩悩は一切の染汙心(ぜんましん)に通じて起こり、一切処三界の所繋(しょけ)に通ず。忿(ふん)、恨(kん)、覆(ふく)、悩(のう)、嫉(しつ)、慳(けん)、誑(おう)、諂(てん)、憍(きょう)、害(がい)此の十随煩悩は各別の不善心に起こる、若し一生ずる時は必ず第二無し。是の如き十種は皆な欲界繋なり。誑(おう)、諂(てん)、憍(きょう)を除く。誑及び諂は初静御慮に至り、憍は三界に通ずるに由る。此れ並に二の若し上地(じょうち)に在るは唯だ無記性なり。尋(じん)、伺(し)、悪作(おさ)、睡眠(すいめん)此の四の随煩悩はは善・不善・無記の心に通じて起こるも一切処にに非ず一切時に非ず。若し極めて久しく尋求(じんぐ)し、伺察(しさつ)することあれば、便ち身(しん)疲れ、念失し、心を亦た労損(ろうそん)せしむ、是の故に尋伺を随煩悩と名づく。此のニは乃ち初静慮地に至り、悪昨、睡眠は唯だ欲界にあり。・・・。」
と、詳細にわたって説かれています。
『瑜伽論』の記述から、不正知が染心に遍く存在する心所であることが解ります。しかし、慧は染心に遍く存在するものではありません。そうであるなら、慧の一分であるとする主張は成り立たなくなります。では何故慧の一分であると『雑集論』は述べるているのか。そこを会通しているのが本科段であり、『雑集論』と『瑜伽論』の二つの文にかげ略して説かれているのであり、不正知は慧と癡の倶一分摂になると主張します。この倶一分摂の義が正しい意義を顕したとされています。