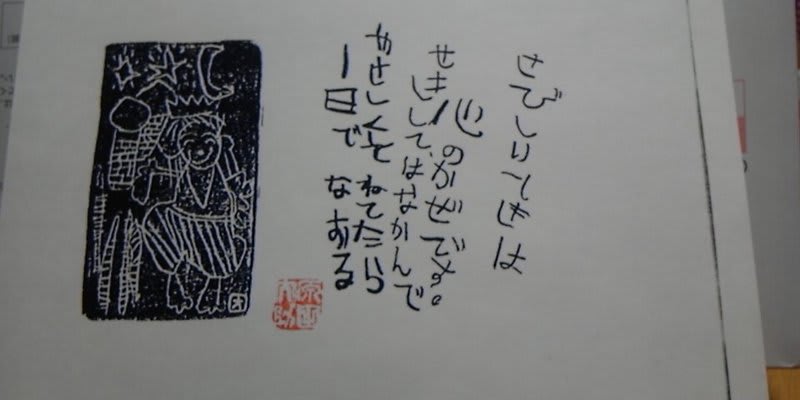「爾らば諸仏は遍智に非ざるべし。」(『論』第二・二十二左)
諸仏の智慧は遍く現象的存在を観察して、「我は無い」と覚られている。遍智です。遍智でなかったならば、仏とはいわないんだと。「無は是れ無なるを知る」智慧を備えたお方が仏様ということですね。それが大円鏡智であると云われているわけです。
無漏位のことは簡単に述べられまして、最後に結ばれます。
「故に、有漏の位の此の異熟識は但し器と身と及び有漏種とのみ縁ず。」(『論』第二・二十二左)
阿頼耶識は何を対象とするのかが、最初の論題でしたが、縷々述べて、阿頼耶識の所縁は種・根・器で有ることをはっきりさせたわけです。それは因縁変によるわけです。
「欲・色界に在って三の所縁を具す。無色界の中には有漏種のみを縁ず。」(『論』第二・二十二左)
三界の境の別を明らかにしています。阿頼耶識の所縁は有漏種と有根身と器界ですが、欲界と色界においては三の所縁すべてが備わっているけれども、無色界に在っては有漏種だけである、と。私たちはどう考えても欲望渦巻く世界を徘徊しています。しかしどこでどう間違ったのか、私は正しいという立場をはずしません。なんという愚かしい事でしょう。私は正しいという立場が欲界の特徴なんでしょうね。何を語っても、「私にとって利益あること」が最優先なんです。その代表が財欲であり、名利心であり、慢心ですね。これらを着飾ることに奔走しているのが私の姿そのものです。そして、これらを求めるのが何故悪いのかということがありますが、悪いのではないのですね。これらに執着する心が問題だと指摘しているんです。
少し前に戻りまして、業力所変、定力所変という問題が提起されていました。そこを読んでみます。
「前来は且く業力所変の外器と内身との界地の差別を説けり。若し定等の力による所変の器と身とは、界地自他に於て則ち決定せず。所変の身・器は多く恒に相続せり。変ぜらるる声・光当は多分暫時なり。現縁の撃発(きゃくほつ)するに随って起こるが故に。」
業力所縁は、因は是れ善か悪の結果としての対象を持っている。それが有漏種と有根身と器界なんです。阿頼耶識が変現したところの三つを所縁として見分の内容としている。これは動かすことができないものである。自分で自分の世界を作ってきた、そして今も作っているということなんですが、ここに定力所変という自己変革の鍵が提起されてきます。「果是無記」です。業の流れを受けて未来を切り開いていくチャンスが与えられているわけです。
ここで非常に大事なことは、法に触れるということなんです。
『三十頌』第二十一頌と第二十二頌を読んでみます。
依他起の自性は、分別の縁に生ぜらる。円成実は彼が於に、常に前のを遠離せる性なり。(第二十一頌)
故に此れは依他と、異にも非ず不異にも非ず。無常等のごとし。此れを見ずして彼をみるものには非ず。(第二十二頌)
多川俊映師の現代語訳を引用します。
「(第二十一頌)私たちの日常は、さきほどみたように、遍計所執の世界ですが、つぎに一般的にみて世界というものはどのようにして成り立っているのかを確認しましょう。むろん、勝手な思い計らいや執着はいけませんが、そういう世界も、ある絶対条件の下、単独に在るわけではありません。やはり、さまざまな原因が一定条件の下、一時的に和合しt成り立っています。つまり、元来は、縁起(さまざまな縁によって生起する)の性質のものです。唯識ではそれを、依他起(他に依って起こるもの)というのですが、どのような世界であれ、この依他起(えたき)ということが在り方の基本です。
さて問題は、私たちが真に求めるべき世界です。唯識ではこれを、円満に完成された真実の世界という意味で、円成実(えんじょうじつ)といいますが、これも、依他起の性質がベースになります。ただし、その上によからぬ思い計らいや執着を一切加味しない、というよりむしろ、つねにそうした遍計所執の無縄自縛を隔絶した世界――。それが円成実の世界です。
(第二十二頌)したがって、円成実と依他起との関係は、異なっているのでもないし、異なっていないのでもない。――という、はなはだ微妙な関係です。つまり、円成実と依他起とは、別のものでも同じものでもないのです。
それはたとえば、無常という事実と真実のようなものでしょうか。すべては無常だという事実も、勝手な思い計らいや執着が加われば、たちまち事実無根の遍計所執に成り下がります。そうならないためには、それがまず、曲げようのない真理・真実だと深く心に刻むことではないでしょうか。すなわち、円成実という真実を見ないかぎり、依他起の事実もみえてこないのです。」
聖書(ヨハネによる福音書・序・賛歌 神である言葉)に、「初めにロゴスありき」とでてきますね。原語はヘブライ語ですが、現代語訳では「1初めにみ言葉があった。み言葉は神と共にあった。み言葉は神であった。 2このみ言葉は初めに神と共にあった。 3すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。 4み言葉の内に命があった。そしてこの命は人の光であった。 5光は闇の中に輝いている。そして、闇は光に打ち勝たなかった。」
「ロゴス」は「言葉」と翻訳されますが、「理性」、「論理」、「概念」などの意味も含めて、それらを統一して初めて理解される概念であって、「言葉」に意味を限定されてしまうと、ここでヨハネが言っている意味そのものが理解されないのではないかと思います。ドイツの哲学者ヘーゲルは、世界をロゴスの現れ、ロゴスの歴史的展開だというふうに見ました。これが、「初めにロゴスありき」の意味です。ヘーゲルは、ロゴスを「あるがままのものとしての観念」と定義し、あるがままのものとしての観念が、非本来的な姿すなわち物質世界としての世界として現れてる、それがこの世界だと意味づけているようです。
意味はともかくとして、洋の東西を問わず、真理において在る者、それが命ある存在だということでしょう。キリスト教は原罪として神の許しを乞うことに信仰の在り方を見出したのでありましょうが、仏教は自身の中に、真理に反逆する心を見出し、断煩悩の道を歩むことになったのでしょう。断煩悩も真理に触れたからこそ求むべき方向性が見出されたものだと思います。そして、この真理に、真理そのものに能動的な働きを見出したのが他力回向の概念だと思います。ただ他力回向の概念は自己と離れているものではなく、自己自身の内に、煩悩と倶に歩んでいる根本の純粋意識に触れたんだと思います。なにものにも穢されることのない無垢なる識の発見が浄土の真宗として開顕されたのではないでしょうか。














 今日から映画「それいけアンパンマン ミージャと魔法のランプ」全国映画館で公開されます!子供も大人も楽しめるので観に行ってね!
今日から映画「それいけアンパンマン ミージャと魔法のランプ」全国映画館で公開されます!子供も大人も楽しめるので観に行ってね!