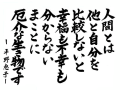唯識は難解ですか。私は何処に向かって歩いているのか。どうなりたいのかを思索する学問になると思うんですよ。いわば、無条件の救いを実現する学問です。では何故無条件の救いが完成しなのでしょう。何が邪魔をしてるのか。この状況を唯識は詳しく説き明かしています。一言でいえば、唯識無境です。境は対象ですね。識は私の心の構造になります。私の心の構造のみが存在して、対象である境は無いといっています。この「無い」は実体的に固定的に存在するものではないということなのです。実は、私も実体的に固定的に存在するものではないんですね。
それは縁に由って変化する存在であるわけです。ここで、我と法が語られます。唯識は我を明らかにし、無境は法を明らかにします。問題は我に囚われ、法に囚われている自己自身が問題であると指摘しているのです。
現在の社会問題、これからも波状的に襲ってくるだろうと想像されるウイルスですね。核に代わって、人類が取り組まなければならない問題です。これが縁なのです。
私個人が何ができるのか。無常である世界、無我である自己を明らかにすることが、最大限必要な課題であると思いますが、皆さんはどのように考えておられるのでしょうか。
『大経』に「然るに世人、薄俗にして共に不急の事を諍う」と現在の状況を予言していますが、これは、いかにして生き延びていけるのかが、不急の事を諍うことに発展してくると指摘しているのですね。
熏習に関しては、
「唯だ識のみあって境はなし」(識の所現は識の所変なり)を言葉を変えて教えています。他人の行為は熏習しませんが、他人の行為にたいして思うことは熏習します。これ能なるが故です。そして即時ですから、時の前後は熏習しないということです。ただしですね、昨日のことであっても、「今」考えたり、それに左右されることは今の出来事ですから熏習されます。厳密ですね。未来のことは熏習されませんが、未来のことを今思うことは熏習されます。すべては「今」(刹那生滅)今といっても動いていますからね、意識されたときは過去の出来事になりますね。ですからね、熏習というのは思量を超えている。私の思いからは計らうことはできないのです。こういうのを自然(ジネン)と言い表されているんだと思います。
私の判断というか、思いですね。思いから云うとですね、人生無駄だらけ、こんなはずではなかった、と。
僕なんかは特にそうですね。過去に想いを馳せるのは悪くはありませんが、後悔ばかりが先行します。「何故・何故、ばかり」。しかし、はからずもです、仏法に出遇わしていただくことによって、今ある自分に気づかせていただきますと、すべては御縁の世界であったと頷きを得ますね。一つでも条件が欠けていたなら、今はありません。命は大事だといいますが、その命の大事さに遇うこともないでしょう。裏を返せば、自分の思いで生きてきましたね。自分の思いで生きてきたことが、どれだけ世間様に無理強いをしてきたのかに深々と頭が下がっていくのではありませんか。頭が下がった時に「すべては無駄ではなかった」といえるのではないのかな。種子が熏習し現行を生起する、という構造を阿頼耶識縁起として唯識は教えているのでしょう。
「定散自力の称名は/果逐のちかいに帰してこそ/おしえざれども自然に/真如の門に転入する」 (『浄土和讃』)
自然(ジネン)は私の思い、計らいを超えている。超えているのは、私の思量の及ぶ範囲ではないということ。思いに先立って如来の用(ユウ)、働きが行きわたっているということなのでしょうか。そこを唯識は阿頼耶識の果相である異熟識(善悪業果位)であると明らかにしたのですね。因は善業か悪業(不善業)であるけれども、異熟識は無覆無記性であるという。転入ということが成り立つのは無覆無記に於いてですね。果は無記である、という所に聞法の大切さが伺えますが、如何なものでしょうか。